先日このブログで、指揮者の故・岩城宏之さんのことを書いた。その続きである。
 東京生まれの岩城さんは読売ジャイアンツのファンだった。親友だった故・武満徹さんが阪神ファンで、岩城さんがある新聞のコラムで「テレビの画面と一緒に六甲おろしを大声で歌っていた」「あのくだらない応援歌を」と懐かしみを込めて書いていた。また、岩城さんはクラシックを野球でたとえ、04年と05年の大晦日、ベートーベンの1番から9番の交響曲を一人で指揮したときも、作曲家の三枝成彰さんとのステージトークで「ベートーベンのシンフォニーは9打数9安打、うち5番、7番、9番は場外ホームランだね」と述べていた。面白いたとえである。
東京生まれの岩城さんは読売ジャイアンツのファンだった。親友だった故・武満徹さんが阪神ファンで、岩城さんがある新聞のコラムで「テレビの画面と一緒に六甲おろしを大声で歌っていた」「あのくだらない応援歌を」と懐かしみを込めて書いていた。また、岩城さんはクラシックを野球でたとえ、04年と05年の大晦日、ベートーベンの1番から9番の交響曲を一人で指揮したときも、作曲家の三枝成彰さんとのステージトークで「ベートーベンのシンフォニーは9打数9安打、うち5番、7番、9番は場外ホームランだね」と述べていた。面白いたとえである。
その岩城さんがことし6月13日に亡くなる前、ある野球プレイヤーに人生のエールを手紙にしたため送っていた。あて先はニューヨークヤンキースの松井秀喜選手である。松井選手はその時、故障で休場を余儀なくされた。
「今回あなたの闘志あふれる守備のため、負傷したことは、誠に残念です。しかしながら、これからの活躍のための一時の休養であると考えていただき、(中略)一番都合の良い夢を見てすごしてください。(中略)私も30回に及ぶ手術を受けましたが、次のコンサートのポスターをはって、あのステージにたつんだと、気持ちを奮い立たせました。(中略)お互い、仕事の世界は違いますが、世界を相手に、そして観客の前でプレーすることには変わりはありません。私も頑張ってステージに戻ります。」(06年6月1日の岩城宏之さんの手紙から)
岩城さんと松井選手の直接の接点はない。ただ、岩城さんは松井選手の故郷である石川県に拠点を置くオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の音楽監督をしていた。そして常々、「このオーケストラを世界のプレイヤーにしたい」と語っていた。岩城さん自らも、20代後半にクラシックの本場ヨーロッパに渡り、武者修行をした経験がある。その後、NHK交響楽団(N響)などを率いてヨーロッパを回り、武満作品を精力的に演奏し、日本の現代曲がヨーロッパで評価される素地をつくった。
岩城さんは挑戦者の気概を忘れなかった。2004年春、自らが指揮するOEKがベルリンやウイーンといった総本山のステージを飾ったときの気持ちを、「松井選手が初めてヤンキー・スタジアムにたったときのような喜び」とインタビューに答えた。クラシックのマエストロが、当時華々しくメジャーデビューを飾った松井選手の心境になぞらえたのである。
これは後日談になるが、73歳のマエストロはメジャーの並みいるピッチャーを睨みつけ撃ち続ける松井選手の姿にほれこんだのだろう。今年に入ってからは、松井選手のために応援歌をつくろうと、自ら歌詞の公募や作曲家の人選などの準備を進めていたのである。その矢先の「松井故障」の報だった。くだんの手紙はそのような背景があってしたためられた。
岩城さん自身、「私の元気のもとは手術」と言うくらい、後縦靭帯骨化症という職業病でもある難病を患い、その後も胃がんや咽頭がん、肺がんと数々の病と闘いながらも復帰を果たし、ステージに立った。手紙にある「これからの活躍のための一時の休養であると考えていただき、(中略)一番都合の良い夢を見てすごしてください。」とは、術後の養生の極意なのだろう。決して焦るな、と諭しているようにも解釈できる。
おそらく直接話したこともない2人の心のやりとりを手紙という1点で結んで地元テレビ局のHAB北陸朝日放送がドキュメンタリー番組にして放送する。HABは、高校野球の取材を通じて松井選手をプロデビュー以前から知り尽くしている。そして、7年に及ぶOEKのモーツアルト全集(95年-01年、東京・朝日新聞浜離宮ホール)の放送や、04年と05年の大晦日のべートーベンチクルス(連続演奏)の収録を通じ岩城さんの傍でその人となりを見てきた。2人を知るテレビ局をだからこそ制作できたドキュメンタリー番組だ。
それにしても、岩城さんが松井選手に手紙を送って、その2週間後に亡くなるとは・・・。死してなおエピソードを残した偉人だった。(写真は、06年1月1日、ベートーベン連続演奏を終えて乾杯する岩城さん=東京芸術劇場で)
※石川エリアでの放送日程 全国での放送日程
⇒24日(金)朝・金沢の天気 はれ
 潟では59人が死亡、4800人以上が負傷し、新幹線が脱線した。今回の能登でも庭で倒れた灯篭の下敷きになって52歳の女性1人が亡くなっている。
潟では59人が死亡、4800人以上が負傷し、新幹線が脱線した。今回の能登でも庭で倒れた灯篭の下敷きになって52歳の女性1人が亡くなっている。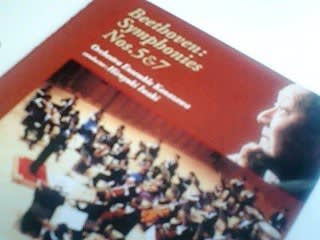 ヒトは都市化する動物であるとすれば地域の過疎化は当然至極、流れに棹をさす地域再生に向けた研究自体は無駄である。しかし、商品経済にほだされて、都会へと流れ生きる現代人の姿がヒトの一時的な迷いであるとすれば、自然と共生しながら生きようとするヒトを地域に招待し応援することは有意義である。私なりにこの命題を自問自答していたとき、これまで聴こうとしなかった7番の第1楽章と第2楽章に耳を傾けたみた。第2楽章の短調の哀愁的な響きにヒトの営みの深淵を感じ、目頭が熱くなるほどの感動を得た。そして、ベートーベンの曲想の壮大なスケールに気づき、7番の主題は「ヒトはどこから来て、どこへ行くのか」のテーマそのものではないのか、と考えるようになった。ここから「つまみ食い」の愚かさを知り、第1楽章から第4楽章までをトータルで聴くようになった。1月上旬のことだった。
ヒトは都市化する動物であるとすれば地域の過疎化は当然至極、流れに棹をさす地域再生に向けた研究自体は無駄である。しかし、商品経済にほだされて、都会へと流れ生きる現代人の姿がヒトの一時的な迷いであるとすれば、自然と共生しながら生きようとするヒトを地域に招待し応援することは有意義である。私なりにこの命題を自問自答していたとき、これまで聴こうとしなかった7番の第1楽章と第2楽章に耳を傾けたみた。第2楽章の短調の哀愁的な響きにヒトの営みの深淵を感じ、目頭が熱くなるほどの感動を得た。そして、ベートーベンの曲想の壮大なスケールに気づき、7番の主題は「ヒトはどこから来て、どこへ行くのか」のテーマそのものではないのか、と考えるようになった。ここから「つまみ食い」の愚かさを知り、第1楽章から第4楽章までをトータルで聴くようになった。1月上旬のことだった。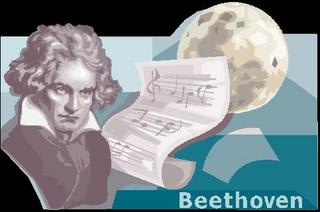 聴いているベト7は2002年9月にオーケストラ・アンサンブル金沢が石川県立音楽堂コンサートホールで録音したものだ。指揮者は岩城宏之さん(故人)。はまり込んだきっかけは、岩城さんがベートーベンのすべての交響曲を一晩で演奏したコンサート(2004年12月31日-05年1月1日・東京文化会館)での言葉を思い出したからだ。演奏会を仕掛けた三枝成彰さんとのトークの中で岩城さんはこんな風に話した。「ベートーベンの1番から9番はすべてホームラン。3番、5番、7番、9番は場外ホームランだね」「5番は運命、9番は合唱付だけど、7番には題名がない。でも、7番にはリズム感と同時に深さを感じる。一番好きなのは7番」と。
聴いているベト7は2002年9月にオーケストラ・アンサンブル金沢が石川県立音楽堂コンサートホールで録音したものだ。指揮者は岩城宏之さん(故人)。はまり込んだきっかけは、岩城さんがベートーベンのすべての交響曲を一晩で演奏したコンサート(2004年12月31日-05年1月1日・東京文化会館)での言葉を思い出したからだ。演奏会を仕掛けた三枝成彰さんとのトークの中で岩城さんはこんな風に話した。「ベートーベンの1番から9番はすべてホームラン。3番、5番、7番、9番は場外ホームランだね」「5番は運命、9番は合唱付だけど、7番には題名がない。でも、7番にはリズム感と同時に深さを感じる。一番好きなのは7番」と。 ミツバチの集団失踪が相次いでいる。アメリカでのこと。全米養蜂協会によると、元気だったハチが翌朝に巣箱に戻らないまま数匹を残して消える現象は、昨年の10月あたりから報告され始め、フロリダ州など24州で確認された。しかし、ハチの失踪数に見合うだけの死骸は行動圏で確認されないケースが多く、失踪したのか死んだのかも完全には特定できないという。そんな中、原因の一つとされているのが、養蜂業者の減少で、みつの採集などの作業で過度のノルマを課せられたことによる“過労死説”だ。国家養蜂局(NHB)が緊急調査に乗り出した。ハチを介した受粉に依存するアーモンドやブルーベリーといった140億ドル(約1兆6000億円)規模の農作物への深刻な影響が懸念され始めた。(3月1日・産経新聞インターネット版より)
ミツバチの集団失踪が相次いでいる。アメリカでのこと。全米養蜂協会によると、元気だったハチが翌朝に巣箱に戻らないまま数匹を残して消える現象は、昨年の10月あたりから報告され始め、フロリダ州など24州で確認された。しかし、ハチの失踪数に見合うだけの死骸は行動圏で確認されないケースが多く、失踪したのか死んだのかも完全には特定できないという。そんな中、原因の一つとされているのが、養蜂業者の減少で、みつの採集などの作業で過度のノルマを課せられたことによる“過労死説”だ。国家養蜂局(NHB)が緊急調査に乗り出した。ハチを介した受粉に依存するアーモンドやブルーベリーといった140億ドル(約1兆6000億円)規模の農作物への深刻な影響が懸念され始めた。(3月1日・産経新聞インターネット版より)  家人を列につけさせ、私は無料開放された兼六園にカメラのアングルを求めて入った。お目当ては兼六園の中でも見栄えがする、唐崎(からさき)の松の雪つりである。ごらんの通り、青空に映える幾何学模様の雪つりである。このほか、冬桜を撮影して列に戻った。思ったほど列は進んでいない。
家人を列につけさせ、私は無料開放された兼六園にカメラのアングルを求めて入った。お目当ては兼六園の中でも見栄えがする、唐崎(からさき)の松の雪つりである。ごらんの通り、青空に映える幾何学模様の雪つりである。このほか、冬桜を撮影して列に戻った。思ったほど列は進んでいない。 たとえば、キノコは合理的な施設栽培が主流となって、店頭では四季を問わず様々なキノコが並んでいる。しかし、それらのキノコからは味や香り、品質そして季節感が感じられない。味より合理性を重視した供給体制が多すぎる。
たとえば、キノコは合理的な施設栽培が主流となって、店頭では四季を問わず様々なキノコが並んでいる。しかし、それらのキノコからは味や香り、品質そして季節感が感じられない。味より合理性を重視した供給体制が多すぎる。 東京生まれの岩城さんは読売ジャイアンツのファンだった。親友だった故・武満徹さんが阪神ファンで、岩城さんがある新聞のコラムで「テレビの画面と一緒に六甲おろしを大声で歌っていた」「あのくだらない応援歌を」と懐かしみを込めて書いていた。また、岩城さんはクラシックを野球でたとえ、04年と05年の大晦日、ベートーベンの1番から9番の交響曲を一人で指揮したときも、作曲家の三枝成彰さんとのステージトークで「ベートーベンのシンフォニーは9打数9安打、うち5番、7番、9番は場外ホームランだね」と述べていた。面白いたとえである。
東京生まれの岩城さんは読売ジャイアンツのファンだった。親友だった故・武満徹さんが阪神ファンで、岩城さんがある新聞のコラムで「テレビの画面と一緒に六甲おろしを大声で歌っていた」「あのくだらない応援歌を」と懐かしみを込めて書いていた。また、岩城さんはクラシックを野球でたとえ、04年と05年の大晦日、ベートーベンの1番から9番の交響曲を一人で指揮したときも、作曲家の三枝成彰さんとのステージトークで「ベートーベンのシンフォニーは9打数9安打、うち5番、7番、9番は場外ホームランだね」と述べていた。面白いたとえである。 クマ出没に関して、現在はドングリなどのエサ不足に加え、里山と奥山の区別がつかないほど里山が荒れ、クマ自身がその領域の見分けがつかず、里山に迷い込んでくる…などの原因が考えられている。これを人災と見るか、害獣の侵入と理解するか意見は分かれる。
クマ出没に関して、現在はドングリなどのエサ不足に加え、里山と奥山の区別がつかないほど里山が荒れ、クマ自身がその領域の見分けがつかず、里山に迷い込んでくる…などの原因が考えられている。これを人災と見るか、害獣の侵入と理解するか意見は分かれる。 昨夜、金沢の繁華街・片町を歩くと、居酒屋などでは6日解禁となったズワイガニがさっそくお目見えしていた。例年、解禁初日には石川県内から100隻を越える底引き網漁船が出港し、近江町市場の店頭にはドンとカニが並ぶ。ご祝儀相場が立つので高値で売れるからだ。だが、庶民にはちょっと手が出せない。何しろ一匹数千円の食材なのである。
昨夜、金沢の繁華街・片町を歩くと、居酒屋などでは6日解禁となったズワイガニがさっそくお目見えしていた。例年、解禁初日には石川県内から100隻を越える底引き網漁船が出港し、近江町市場の店頭にはドンとカニが並ぶ。ご祝儀相場が立つので高値で売れるからだ。だが、庶民にはちょっと手が出せない。何しろ一匹数千円の食材なのである。 子どもたちにすれば、足で踏んでローターが回転するだけでも楽しく、さらにそこに稲穂を差し込むとモミが簡単に取れるから面白い。50人ほどの子どもたちが入れ替わり立ち代わり試みる。子どもたちの歓声は絶えなかった。
子どもたちにすれば、足で踏んでローターが回転するだけでも楽しく、さらにそこに稲穂を差し込むとモミが簡単に取れるから面白い。50人ほどの子どもたちが入れ替わり立ち代わり試みる。子どもたちの歓声は絶えなかった。