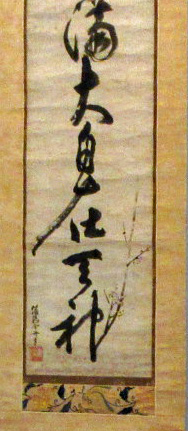★のと・かが小話・・連日猛暑、金沢すいか、ドクターイエロー

きのうきょうと金沢は猛烈な暑さだ。自宅近くの街路の温度計で35度、2日連続の猛暑だ=写真・上、22日正午すぎ、金沢市野田町の山側環状道路で撮影=。テレビニュースによると、金沢から南に位置する小松市ではきのう36.9度となり全国最高を観測、きょうも猛暑となっている。そして、石川県内ではきょう午後5時までに熱中症の疑いで11人が病院に搬送されたようだ。一方、能登半島の北部では午後から大気の状態が不安定となり、3市町(珠洲、穴水、志賀)には洪水警報が出された。ところによって1時間に30㍉の激しい雨が降る見込みで、金沢地方気象台では川の増水や土砂災害などに注意を呼びかけている。

早々と訪れた猛暑の日に合わせたかように、金沢市のJA販売所では「金沢すいか」の売り込みが始まっている。「夏到来 砂丘地より直送」との看板が出ていたので、店に入ってみた。Lサイズものでひと玉2200円。それにしても大玉だ。冷蔵庫に入るだろうかと思いながら見渡していると、4分の1にカットされた「カットすいか」=写真・中=が並んでいたので、これを2個買うことにした。1個780円。
金沢すいかは金沢港近くの砂丘地などで栽培されていて、ひと昔前までは「砂丘地すいか」などと呼ばれていた。それをブランド農産物として知名度を上げ、販路を広げようと生産者が奮闘しているようだ。この地域の農家では伝統野菜である「加賀野菜」の栽培も盛んで、サツマイモの「五郎島金時」や「加賀太きゅうり」、「源助だいこん」などがある。砂丘地だけに水の管理も大変だろうことは想像に難くない。

最近ちょっとした話題になっているのが、金沢市に隣接する白山市にある市立高速鉄道ビジターセンター「トレインパーク白山」で常設展示が始まった「ドクターイエロー」=写真・下=のこと。この黄色い列車は、走りながら線路のゆがみや電線の高さ、信号の動作などを細かく調べる役目を担っている。これらをチェックをすることで、新幹線が安全に走れるようなる。まるで医者の定期検診のような役目から、ドクター・イエローと呼ばれているそうだ。
白山市で常設展示されているのは東海道・山陽新幹線の点検車両として1979年に製造されたもので、2005年に引退した後は「リニア・鉄道館」(名古屋市)で先月まで展示されていた。ドクターイエローは運行ダイヤは不定期で、しかも非公表であるため、知る人ぞ知る列車でもある。このため、その黄色いボディは「幸運の黄色い新幹線」、「見ると幸せになれる」と鉄道ファンの評判を呼んでいた。きょう見学に行くと大勢の家族連れでにぎわっていた。3度目の鉄道人生を歩むことになったドクターイエロー氏、ようこそ北陸へ。
⇒22日(日)夜・金沢の天気 くもり時々あめ