☆寝まり牛起きて猛進す
 「金沢大学の地域連携」の一年を振り返る。大きく三つある。一つは、能登半島に大きく展開したということ。二つには、生物多様性条約第9回締約国会議(CBD-COP9、ボン)に参加し、石川県と国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットなどと連携して、COP10関連会議の誘致に向けて足がかりをつくったこと。三つ目として、里海とトキの研究事業に新たに着手できたということだ。
「金沢大学の地域連携」の一年を振り返る。大きく三つある。一つは、能登半島に大きく展開したということ。二つには、生物多様性条約第9回締約国会議(CBD-COP9、ボン)に参加し、石川県と国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットなどと連携して、COP10関連会議の誘致に向けて足がかりをつくったこと。三つ目として、里海とトキの研究事業に新たに着手できたということだ。
一つ目の能登半島に展開するプログラムでは、「能登半島 里山里海自然学校」と「能登里山マイスター」養成プログラムに加え、大気観測・能登スーパーサイト(黄砂研究)のチームが能登学舎に仲間入りし、能登における環境研究は3本柱となった。このほかにも能登で展開する研究チームと協力体制をつくり、「能登オペレーティング・ユニット」といった学内機構化を目指すバックグラウンドができた。こうした研究プログラムを地域に紹介し理解と協力を得るため、11月から12月にかけて輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の4ヵ所で地区懇談会も開催した。あわせて190人の参加があり、援軍を得た喜びがあった。
石川県と国連大学高等研究所オペレーティング・ユニットとの関係構築も大きな一歩だ。2010年のCOP10では関連会議を誘致するが、それに先立って生物多様性条約事務局(カナダ・モントリオール)のアハメド・ジョグラク事務局長を能登視察(9月16日、17日)に招待できた。1泊2日で能登を回ったジョグラフ氏は輪島市金蔵(かなくら)地区で棚田で稲刈りをする人々の姿を見て、「日本の里山の精神をここに見た」と高く評価したのだった。金蔵はいわゆる限界集落の村。それでもよき日本の里山の景観を維持し、自然と調和しバランスを保っている。
これまで里山の生物多様性や保全活動などを通して地域とかかわってきたが、里海にも目を向けた。手始めは「七尾湾創生プロジェクト」(環境省の事業助成)。これも大学単体ではなく石川県、国連大学高等研究所オペレーティング・ユニットなどと協働して進める。来年2月22日には環境省などとシンポジウムを開催する段取り。また、トキの分散飼育地に石川県、島根県出雲市、新潟県長岡市の3ヵ所が選ばれた(12月19日)。石川県能美市の「いしかわ動物園」に来年度、2つがい4羽のトキがやってくる。中村浩二教授が研究代表となり、トキが能登で生息するための生態学的な調査、地域合意形成のための調査を県からの委託で始めている。能登は本州最後の1羽のトキがいた場所だ。「まだ、生態学的な環境は十分残されている」と中村教授は強調する。環境に配慮した農林業が広まることでトキが生息する環境は再生できる。「トキが再び能登の空を舞う」をキーコンセプトに地域との連携を図っていく。
来年は「能登半島における里山里海復権と持続可能型の地域再生」をさらに追求していきたい。この復権という意味合いはそこで人の生業(なりわい)が成立する、端的にいえばビジネスができるということである。われわれはよく「自然との共生」を口にする。が、目指すべきはむしろ「自然との調和と活用」だろう。活用しなくなったから里山や里海が荒れた。つまり自然が持つ価値が失われた。もう一度、そこに価値を見出すことが必要になってきた。それが復権への行程の一歩だ。
「寝まり牛」は起きて猛進する…。新年をそんなダイナミックな変革の年にしたい。文章は少々粗いが、備忘録として書いた。
※写真は、伝統工芸のテーマパーク「ゆのくにの森」(小松市)で展示されている牛をモチーフにした竹細工
⇒31日(水)朝・金沢の天気 あめ
 食を豊かにするのは味付けや食材の多さだけではない。「もてなし」という情感のこもった気づかいや応対が伴ってこそ、膳に並ぶ食も輝きを増す。もてなしは英語でホスピタリティといい、最近では学問として研究されてもいる。ところで、このもてなしの原点ともいえる農耕儀礼が能登半島に伝承されており、先ごろ、文化庁はユネスコ(国連教育科学文化機関)が無形文化遺産保護条約に基づき作成するリスト(09年9月)の登録候補の一つとして申請した。「あえのこと」である。「あえ」は饗応(ご馳走をしてもてなすこと)を意味する。
食を豊かにするのは味付けや食材の多さだけではない。「もてなし」という情感のこもった気づかいや応対が伴ってこそ、膳に並ぶ食も輝きを増す。もてなしは英語でホスピタリティといい、最近では学問として研究されてもいる。ところで、このもてなしの原点ともいえる農耕儀礼が能登半島に伝承されており、先ごろ、文化庁はユネスコ(国連教育科学文化機関)が無形文化遺産保護条約に基づき作成するリスト(09年9月)の登録候補の一つとして申請した。「あえのこと」である。「あえ」は饗応(ご馳走をしてもてなすこと)を意味する。 金沢大学地域連携推進センターが主催する「金沢大学タウン・ミーティング in 内灘」が12月20日、内灘町役場で開催された。金沢大学はタウン・ミーティングを平成14年度からこれまで石川県内7地区(輪島市、加賀市、鶴来町、珠洲市、能登町、羽咋市、穴水町)で開催しており、今回で8回目.。地域からの話題提供の中で、内灘町のボランティア団体「クリーンビーチ内灘作戦」代表の野村輝久さんが「内灘砂丘を蘇らせる」と題して、角間の里山から切り出したモウソウチクを利用した砂丘の復元運動を紹介した。
金沢大学地域連携推進センターが主催する「金沢大学タウン・ミーティング in 内灘」が12月20日、内灘町役場で開催された。金沢大学はタウン・ミーティングを平成14年度からこれまで石川県内7地区(輪島市、加賀市、鶴来町、珠洲市、能登町、羽咋市、穴水町)で開催しており、今回で8回目.。地域からの話題提供の中で、内灘町のボランティア団体「クリーンビーチ内灘作戦」代表の野村輝久さんが「内灘砂丘を蘇らせる」と題して、角間の里山から切り出したモウソウチクを利用した砂丘の復元運動を紹介した。 石の胸像が配置されている。カトリック教会から異端者として審問にかけられ、自説を取り消さなかったため、軟禁され8年後にこの世を去った(1642年)。裁判の後、ガリレオはつぶやいたという。「それでも地球は動く」
石の胸像が配置されている。カトリック教会から異端者として審問にかけられ、自説を取り消さなかったため、軟禁され8年後にこの世を去った(1642年)。裁判の後、ガリレオはつぶやいたという。「それでも地球は動く」
 想像したのは強盗が入るなどの最悪の事態。すると奥の方で懐中電灯の明かりが揺れている。「やっぱり」と思い。大声で「誰かいるのか」と凄んだ。すると奥から家内の声、「停電なの」。力が抜ける。
想像したのは強盗が入るなどの最悪の事態。すると奥の方で懐中電灯の明かりが揺れている。「やっぱり」と思い。大声で「誰かいるのか」と凄んだ。すると奥から家内の声、「停電なの」。力が抜ける。 もともとは、ことし3月に出版された「パラダイス鎖国 忘れられた大国・日本」 (海部美知、アスキー新書)のタイトルから引用された言葉だ。ことし1月のダボス会議で、「Japan: A Forgotten Power?(日本は忘れられた大国なのか)」というセッションが開かれ、国際的に日本の内向き志向が論議になったという。高度経済成長から貿易摩擦の時代を経て、日本はいつの間にか、世界から見て存在感のない国になってしまっている。その背景には、安全や便利さ、そしてモノの豊かさ日本は欧米以上になり、外国へのあこがれも昔ほど持たなくなったことがある。明治以来の欧米に追いつけ追い越せのコンプレックスは抜け切ったともいえる。ハングリー精神とかチャレンジ精神という言葉は死語になりつつあり、リスクを取らないことが美徳であるかのような社会の風潮だ。これでは人は育たず、社会も会社も停滞する。
もともとは、ことし3月に出版された「パラダイス鎖国 忘れられた大国・日本」 (海部美知、アスキー新書)のタイトルから引用された言葉だ。ことし1月のダボス会議で、「Japan: A Forgotten Power?(日本は忘れられた大国なのか)」というセッションが開かれ、国際的に日本の内向き志向が論議になったという。高度経済成長から貿易摩擦の時代を経て、日本はいつの間にか、世界から見て存在感のない国になってしまっている。その背景には、安全や便利さ、そしてモノの豊かさ日本は欧米以上になり、外国へのあこがれも昔ほど持たなくなったことがある。明治以来の欧米に追いつけ追い越せのコンプレックスは抜け切ったともいえる。ハングリー精神とかチャレンジ精神という言葉は死語になりつつあり、リスクを取らないことが美徳であるかのような社会の風潮だ。これでは人は育たず、社会も会社も停滞する。 さて、シリーズ「能登の旋風(かぜ)」は里山里海国際交流フォーラム「能登エコ・スタジアム2008」のイベントで拾った話題を紹介している。9月13日から17日にかけての「能登エコ・スタジアム2008」は3つのフォーラム、6つのプログラム、1つのツアーから構成されていたが、17日にシニアコース(シニア短期留学)の修了式をもって、すべてのメニューを完了した。また、同日は生物多様性条約のムハマド・ジョグラフ事務局長の能登視察も終了した。一連のイベントメニューの中でのVIP視察だった。
さて、シリーズ「能登の旋風(かぜ)」は里山里海国際交流フォーラム「能登エコ・スタジアム2008」のイベントで拾った話題を紹介している。9月13日から17日にかけての「能登エコ・スタジアム2008」は3つのフォーラム、6つのプログラム、1つのツアーから構成されていたが、17日にシニアコース(シニア短期留学)の修了式をもって、すべてのメニューを完了した。また、同日は生物多様性条約のムハマド・ジョグラフ事務局長の能登視察も終了した。一連のイベントメニューの中でのVIP視察だった。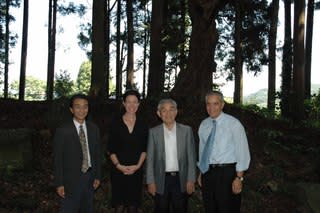 今回のイベントで印象に残った2枚の写真。持続可能なこと、それは地下に封じ込められた化石燃料を掘り出して、燃焼させ、二酸化炭素を排出することではない。二酸化炭素を吸収し、光合成によって成長した植物をエネルギー化すること。里の生えるススキ、カヤ類を燃料化する試みが始まっている。それらをペレット化して燃料、あるいは家畜の飼料にする。奥能登では戦後、1800haもの畑地造成が行われたが、そのうち1000haが耕作放棄されススキ、カヤが生い茂っている。それをなんとかしたいとの発想でバイオマス研究から実用化の段階に向けて試行が続いている。能登エコ・スタジアムのコース「バイオエコツーリズム」ではその試みに興味を持った若者たちが大勢集まってきた。そして実際にススキを刈り取り、ペレット化を体験したのである。上の写真はその刈り入れの様子だ。地域エネルギーの可能性を感じさせる光景に見えた。
今回のイベントで印象に残った2枚の写真。持続可能なこと、それは地下に封じ込められた化石燃料を掘り出して、燃焼させ、二酸化炭素を排出することではない。二酸化炭素を吸収し、光合成によって成長した植物をエネルギー化すること。里の生えるススキ、カヤ類を燃料化する試みが始まっている。それらをペレット化して燃料、あるいは家畜の飼料にする。奥能登では戦後、1800haもの畑地造成が行われたが、そのうち1000haが耕作放棄されススキ、カヤが生い茂っている。それをなんとかしたいとの発想でバイオマス研究から実用化の段階に向けて試行が続いている。能登エコ・スタジアムのコース「バイオエコツーリズム」ではその試みに興味を持った若者たちが大勢集まってきた。そして実際にススキを刈り取り、ペレット化を体験したのである。上の写真はその刈り入れの様子だ。地域エネルギーの可能性を感じさせる光景に見えた。 能登半島地震の発生翌日、被害がもっとも大きいとされた門前地区に入った。住民のうち65歳以上が47%を占める。金沢大学の地域連携コーディネーターとして、学生によるボランティア支援をどのようなかたちで進めたらよいかを調査するのが当初の目的だった。そこで見たある光景をきっかけに、「震災とメディア」をテーマに調査研究を実施することになる。震災当日からテレビ系列が大挙して同町に陣取っていた。現場中継のため、倒壊家屋に横付けされた民放テレビ局のSNG(Satellite News Gathering)車をいぶかしげに見ている被災者の姿があった。この惨事は全国中継されるが、被災地の人たちは視聴できないのではないか。また、半壊の家屋の前で茫然(ぼうぜん)と立ちつくすお年寄り、そしてその半壊の家屋が壊れるシーンを撮影しようと、ひたすら余震を待って身構えるカメラマンのグループがそこにあった=写真・上=。こうしたメディアの行動は、果たして被災者に理解されているのだろうか。それより何より、メディアはこの震災で何か役立っているのだろうか、という素朴な疑問があったからだ。 当時、カメラマンたちが狙っていた半壊の家はいまどうなっているのか確認したかった。その家はカメラマンたちが期待したようにはならなかった。つまり、余震での倒壊は免れた。しかし、住めるような状態ではなかったので、そのままになっているのか、取り壊して更地なっているのか、再建されているのか…。何かの折に再び訪ねてみたいと思っていた。
能登半島地震の発生翌日、被害がもっとも大きいとされた門前地区に入った。住民のうち65歳以上が47%を占める。金沢大学の地域連携コーディネーターとして、学生によるボランティア支援をどのようなかたちで進めたらよいかを調査するのが当初の目的だった。そこで見たある光景をきっかけに、「震災とメディア」をテーマに調査研究を実施することになる。震災当日からテレビ系列が大挙して同町に陣取っていた。現場中継のため、倒壊家屋に横付けされた民放テレビ局のSNG(Satellite News Gathering)車をいぶかしげに見ている被災者の姿があった。この惨事は全国中継されるが、被災地の人たちは視聴できないのではないか。また、半壊の家屋の前で茫然(ぼうぜん)と立ちつくすお年寄り、そしてその半壊の家屋が壊れるシーンを撮影しようと、ひたすら余震を待って身構えるカメラマンのグループがそこにあった=写真・上=。こうしたメディアの行動は、果たして被災者に理解されているのだろうか。それより何より、メディアはこの震災で何か役立っているのだろうか、という素朴な疑問があったからだ。 当時、カメラマンたちが狙っていた半壊の家はいまどうなっているのか確認したかった。その家はカメラマンたちが期待したようにはならなかった。つまり、余震での倒壊は免れた。しかし、住めるような状態ではなかったので、そのままになっているのか、取り壊して更地なっているのか、再建されているのか…。何かの折に再び訪ねてみたいと思っていた。 MさんとNさんをお誘いして門前入りした9月16日午前、車を降りて、問題のシーンと遭遇した場所に再び立ってみた。その民家は再建途中だった=写真・下=。まもなく完成するだろう。おそらくこの家の家族はまだ避難所生活と想像するが、まもなく新居での生活が始まるだろう。そう考えると、正直にうれしかった。震災から1年6ヵ月余り。それにしても、被災者とメディア側の溝は深い。メディア側で被災者の目線というものを体験しなければこの溝は埋まらない。そこで、「震災とメディア」の調査報告書には下記の一文をつけた。
MさんとNさんをお誘いして門前入りした9月16日午前、車を降りて、問題のシーンと遭遇した場所に再び立ってみた。その民家は再建途中だった=写真・下=。まもなく完成するだろう。おそらくこの家の家族はまだ避難所生活と想像するが、まもなく新居での生活が始まるだろう。そう考えると、正直にうれしかった。震災から1年6ヵ月余り。それにしても、被災者とメディア側の溝は深い。メディア側で被災者の目線というものを体験しなければこの溝は埋まらない。そこで、「震災とメディア」の調査報告書には下記の一文をつけた。 た。9月16日午前のプログラム自由時間を利用して、MさんとNさんを誘って門前地区を訪ねた。
た。9月16日午前のプログラム自由時間を利用して、MさんとNさんを誘って門前地区を訪ねた。 次に訪れた総持寺もまた被災し再興途中だった。僧堂の再建工事は屋根の部分まで進んでいた。MさんとNさんはここで「瓦寄進」をした。瓦に祈願の文字を書き、お布施をする。亡き父親が当地出身というMさんは「先祖供養」と書いていた。鶴見の総持寺と縁があるNさんは「一家繁栄」を祈願した。Nさんはさらに総持寺と縁を感じることになる。僧堂の建築現場に近づいてみると、長男が勤める建築事務所(東京都)がこの僧堂の設計・管理に携わっていたのだ。「大変名誉な仕事をさせてもらっている。親として素直にうれしい」と目を輝かせた。
次に訪れた総持寺もまた被災し再興途中だった。僧堂の再建工事は屋根の部分まで進んでいた。MさんとNさんはここで「瓦寄進」をした。瓦に祈願の文字を書き、お布施をする。亡き父親が当地出身というMさんは「先祖供養」と書いていた。鶴見の総持寺と縁があるNさんは「一家繁栄」を祈願した。Nさんはさらに総持寺と縁を感じることになる。僧堂の建築現場に近づいてみると、長男が勤める建築事務所(東京都)がこの僧堂の設計・管理に携わっていたのだ。「大変名誉な仕事をさせてもらっている。親として素直にうれしい」と目を輝かせた。 とき腫瘍を患って他界しました。それから12年経ちます…」と語り始めた。約束を果たさぬまま先立った息子への思いも募ったのか、Mさんの顔は曇りがちだった。
とき腫瘍を患って他界しました。それから12年経ちます…」と語り始めた。約束を果たさぬまま先立った息子への思いも募ったのか、Mさんの顔は曇りがちだった。 参加者の構成は東京都3人、兵庫県3人、大阪府2人、滋賀県1人、京都府1人、神奈川県1人である。年齢は60歳から84歳。男女比は女性7人、男性4人の構成。11日に開講式があり、懇親会があった。さっそく「シニア短期留学を研究する協議会をつくってはどうか」「金沢人、不親切論」なども飛び出して、侃侃諤諤(かんかんがくがく)の状態となった。「論客が多すぎる」。これが第一印象だった。反省もあった。参加者には予めパンフレットで講義内容を簡単に説明してあったが、金沢大学がどのような学習サービスを提供してくれるのか、イメージとしてはインプットされていなかったのだろう。要は、説明不足。だから、懇親会での話が講義内容に集中するのではなく、ベクトルがバラバラな方向に展開したのだった。出だしはこんなふうだった。
参加者の構成は東京都3人、兵庫県3人、大阪府2人、滋賀県1人、京都府1人、神奈川県1人である。年齢は60歳から84歳。男女比は女性7人、男性4人の構成。11日に開講式があり、懇親会があった。さっそく「シニア短期留学を研究する協議会をつくってはどうか」「金沢人、不親切論」なども飛び出して、侃侃諤諤(かんかんがくがく)の状態となった。「論客が多すぎる」。これが第一印象だった。反省もあった。参加者には予めパンフレットで講義内容を簡単に説明してあったが、金沢大学がどのような学習サービスを提供してくれるのか、イメージとしてはインプットされていなかったのだろう。要は、説明不足。だから、懇親会での話が講義内容に集中するのではなく、ベクトルがバラバラな方向に展開したのだった。出だしはこんなふうだった。