☆09総選挙の行方~5
私の知人の話である。知人は10年ほど前、インドを旅行した。コルカタ(かつてカルカッタと称した)の広場で、群集が静かに、ある一点をじっと見つめていた。その目線の向こうはカメだった。「異様な光景だった」という。ところが人々の様子をつぶさに観察すると、静かな群集なのだが、手は盛んに動いていた。お金を右に左に手渡している。カメがどちらの方向に動くかで、賭けをしていたのだ。
1か0か、デジタル政権の時代に
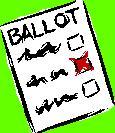 この話を聞いて、今回の総選挙を連想した。政権というカメがどちらの方向に向くかをじっと観察している有権者が静かに手を動かす(投票)。これまでの選挙は、闘牛やスポーツを観戦するかのごとく国民は熱狂した。お祭り騒ぎをした。だから、誰が、どんな世代が何を政治に求めているのかが見えやすく、実感でき、論議もでき、そして自らの投票行動の基準が分かりやすかった。ところが、今回の選挙は政権交代で誰が何を求めているのか見えにくい、分かりにくい、可視化できなかった。
この話を聞いて、今回の総選挙を連想した。政権というカメがどちらの方向に向くかをじっと観察している有権者が静かに手を動かす(投票)。これまでの選挙は、闘牛やスポーツを観戦するかのごとく国民は熱狂した。お祭り騒ぎをした。だから、誰が、どんな世代が何を政治に求めているのかが見えやすく、実感でき、論議もでき、そして自らの投票行動の基準が分かりやすかった。ところが、今回の選挙は政権交代で誰が何を求めているのか見えにくい、分かりにくい、可視化できなかった。
この選挙期間、テレビメディアでも取り上げられたエピソードがある。選挙期間中、民主党の鳩山由紀夫代表が青森・八戸市で演説していたら、前列にいた女性が泣き出した。後で鳩山氏が尋ねると、「仕事がなく帰郷した息子が自殺した。この政治を何とかしてほしい」と訴えたという。テレビではたまたま鳩山氏が婦人の話に耳を傾ける姿が映されていた。このエピソードにも象徴されるように、訴えは個々である。ある党のマニフェストに異議を申し立てる団体とか、あるいはマニフェストに賛同して行動する「勝手連」とか、有権者側の行動が見えにくい選挙だった。
こうした静かなる選挙はある意味で怖い。もちろんこれまでも、争点らしきものはなく静かなる選挙はたびたびあった。しかし、勢力図を完全にひっくり返すような静かな選挙はなかった。が、世界を眺めれば、政権交代は普通のことである。その意味で、日本もようやく「普通の国」になったと言える。日本の場合、議会制民主主義なので、アメリカ大統領選や、韓国の大統領選のような熱狂はない。民意は反映されるが、その民意は見えにくい。308議席のマンモス政党といえども、またひっくり返される可能性も十分にある。有権者の静かで激しい民意を汲み取らねば政権が維持できない時代に入ったのだろう。民意は移ろいやすい。長期政権の時代の終焉である。あるいは、1か0か、政権のデジタル化と言えるかもしれない。
⇒1日(火)朝・金沢の天気 はれ
 公職選挙法第6条2では、選挙の結果を有権者に速やかに知らせるように努めなければならないとしており、開票所は公開されている。ただ、テレビ各局は午後8時から一斉に「選挙特番」を放送するので、不思議な感じがする。携帯電話のワンセグ放送で視聴すると、開票所に到着した午後9時ごろ、全国200人余りにすでに「当確(当選確実)」が出ていた。ところが、この金沢市の開票所は開票のスタートが午後9時30分なのである。都市部の開票はだいたい午後9時ごろからなので、「メディア開票」がずっと先行していた。
公職選挙法第6条2では、選挙の結果を有権者に速やかに知らせるように努めなければならないとしており、開票所は公開されている。ただ、テレビ各局は午後8時から一斉に「選挙特番」を放送するので、不思議な感じがする。携帯電話のワンセグ放送で視聴すると、開票所に到着した午後9時ごろ、全国200人余りにすでに「当確(当選確実)」が出ていた。ところが、この金沢市の開票所は開票のスタートが午後9時30分なのである。都市部の開票はだいたい午後9時ごろからなので、「メディア開票」がずっと先行していた。 26日付の朝日新聞では、テレビの選挙報道が前回より「半減している」と報じていた。解散した日から1週間の間で、NHKや民放が取り上げた選挙に関する映像を時間で計測したデータの05年と今回の比較である。それを見ると、テレビ朝日の場合、前回がトータルで25時間、今回は16時間ほどなっている。フジテレビなどは3分の1だ。全体でデータを眺めると確かに今回はトーンダウンしている。テレビはある意味で正直だ。視聴率という数字が取れない、あるいは「絵にならない」(映像的に面白くない)と判断すると取り上げないものだ。確かに、前回は「刺客」「小泉敵情」の取り上げが過熱して、「テレポリティクス」と揶揄(やゆ)されたように、テレビが選挙を誘導しているとの批判の声もあった。テレビはその反省に立って、今回自重しているのか。「否」である。テレビはそんな殊勝な業界ではない。数字が取れると思えば、どこまでも食いついて行く。要は、選挙では数字が取れない、「酒井法子で行こう」と視聴者の心を読み取っているのである。
26日付の朝日新聞では、テレビの選挙報道が前回より「半減している」と報じていた。解散した日から1週間の間で、NHKや民放が取り上げた選挙に関する映像を時間で計測したデータの05年と今回の比較である。それを見ると、テレビ朝日の場合、前回がトータルで25時間、今回は16時間ほどなっている。フジテレビなどは3分の1だ。全体でデータを眺めると確かに今回はトーンダウンしている。テレビはある意味で正直だ。視聴率という数字が取れない、あるいは「絵にならない」(映像的に面白くない)と判断すると取り上げないものだ。確かに、前回は「刺客」「小泉敵情」の取り上げが過熱して、「テレポリティクス」と揶揄(やゆ)されたように、テレビが選挙を誘導しているとの批判の声もあった。テレビはその反省に立って、今回自重しているのか。「否」である。テレビはそんな殊勝な業界ではない。数字が取れると思えば、どこまでも食いついて行く。要は、選挙では数字が取れない、「酒井法子で行こう」と視聴者の心を読み取っているのである。 さて、公示日に候補者が出そろった。中で、興味深い顔ぶれも。比例代表北信越ブロックで、民主党は元自民党参院議員で国家公安委員長や内閣府特命担当大臣(防災担当)を歴任した沓掛(くつかけ)哲男氏(79歳)を、単独で名簿登載した。沓掛氏は金沢市在住で、もともと建設省技監を務めた官僚だ。3年前、議員会館を訪ねたことがある。大学のプロジェクトの立ち上げに際して、協力を求めに訪れたのだが、非常に丁寧な応対で、「お昼でもどうかね」と誘っていただいた。「政治家らしからぬ」柔軟さが好印象だった。
さて、公示日に候補者が出そろった。中で、興味深い顔ぶれも。比例代表北信越ブロックで、民主党は元自民党参院議員で国家公安委員長や内閣府特命担当大臣(防災担当)を歴任した沓掛(くつかけ)哲男氏(79歳)を、単独で名簿登載した。沓掛氏は金沢市在住で、もともと建設省技監を務めた官僚だ。3年前、議員会館を訪ねたことがある。大学のプロジェクトの立ち上げに際して、協力を求めに訪れたのだが、非常に丁寧な応対で、「お昼でもどうかね」と誘っていただいた。「政治家らしからぬ」柔軟さが好印象だった。 問われているのはメディアなのか。新聞各社の世論調査が圧倒的な「民主勝利」を早々と伝えている。ところが、最近出始めているインターネットによるアンケート調査は結果がまったく違う。
問われているのはメディアなのか。新聞各社の世論調査が圧倒的な「民主勝利」を早々と伝えている。ところが、最近出始めているインターネットによるアンケート調査は結果がまったく違う。 初日は、金沢からバスで出発し、石川県七尾市の能登演劇堂で開催された「環境国際シンポジウムin能登」に参加した。ノーベル平和賞を受賞した国連組織「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)のラジェンドラ・パチャウリ議長の基調講演を楽しみにしていたが、博士は体調不良を理由に欠席。その代わり、ビデオレターが上映され、その中で「今、何かの手を打たなければ、多くの生態系が危機にさらされる」と訴えていた。翌朝は船に乗り、ぐるりと能登島を回る七尾湾洋上コースと能登島をバスで巡るコースに分かれてのエクスカ-ション。能登島のカタネという入り江にミナミバンドウイルカのファミリーの親子(5頭)がコロニーをつくっていて、船からは、時折背ビレを海面に突き出して回遊する様子を見ることができた。午後からは、奥能登・珠洲で実施されている「生き物田んぼ」を見学し、直播(じかまき)の水田で水生昆虫の調査の説明を聞いた=写真=。両日とも雨にたたられずに済んだ。
初日は、金沢からバスで出発し、石川県七尾市の能登演劇堂で開催された「環境国際シンポジウムin能登」に参加した。ノーベル平和賞を受賞した国連組織「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)のラジェンドラ・パチャウリ議長の基調講演を楽しみにしていたが、博士は体調不良を理由に欠席。その代わり、ビデオレターが上映され、その中で「今、何かの手を打たなければ、多くの生態系が危機にさらされる」と訴えていた。翌朝は船に乗り、ぐるりと能登島を回る七尾湾洋上コースと能登島をバスで巡るコースに分かれてのエクスカ-ション。能登島のカタネという入り江にミナミバンドウイルカのファミリーの親子(5頭)がコロニーをつくっていて、船からは、時折背ビレを海面に突き出して回遊する様子を見ることができた。午後からは、奥能登・珠洲で実施されている「生き物田んぼ」を見学し、直播(じかまき)の水田で水生昆虫の調査の説明を聞いた=写真=。両日とも雨にたたられずに済んだ。 今からちょうど120年前の明治22年(1889)5月、東京に滞在していたアメリカの天文学者パーシバル・ローエル(1855-1916)は能登半島の地形とNOTOという地名の語感に惹(ひ)かれ、鉄道や人力車を乗り継いで当地にやってきた。七尾湾では魚の見張り台である「ボラ待ち櫓(やぐら)」によじ登り、「ここは、フランスの小説でも読んでおればいい場所」と、後に著した「NOTO: An Unexplored Corner of Japan」(1891)で記した。ローエルが述べた「フランスの小説」とは、当時流行したエミ-ル・ガボリオの「ルコック探偵」など探偵小説のことを指すのだろうか。ローエルの好奇心のたくましさはその後、宇宙へと向かって行く。
今からちょうど120年前の明治22年(1889)5月、東京に滞在していたアメリカの天文学者パーシバル・ローエル(1855-1916)は能登半島の地形とNOTOという地名の語感に惹(ひ)かれ、鉄道や人力車を乗り継いで当地にやってきた。七尾湾では魚の見張り台である「ボラ待ち櫓(やぐら)」によじ登り、「ここは、フランスの小説でも読んでおればいい場所」と、後に著した「NOTO: An Unexplored Corner of Japan」(1891)で記した。ローエルが述べた「フランスの小説」とは、当時流行したエミ-ル・ガボリオの「ルコック探偵」など探偵小説のことを指すのだろうか。ローエルの好奇心のたくましさはその後、宇宙へと向かって行く。 なぜ蓄養かというと、市場では小さなタコは値がしない。すくなくとも1キロは必要で、キロ1000円が相場。難しいのは、水温が上がるとタコが弱ってしまうこと。このタコ牧場では海水をそのまま汲み上げている。太平洋側に比べ、日本海側は海水温が一定していない。そこで、水温が高くなるころを見計らって、大きなものから出荷する調整も必要とのこと。タコを飼うのも簡単ではない。
なぜ蓄養かというと、市場では小さなタコは値がしない。すくなくとも1キロは必要で、キロ1000円が相場。難しいのは、水温が上がるとタコが弱ってしまうこと。このタコ牧場では海水をそのまま汲み上げている。太平洋側に比べ、日本海側は海水温が一定していない。そこで、水温が高くなるころを見計らって、大きなものから出荷する調整も必要とのこと。タコを飼うのも簡単ではない。 大宮神社の狛犬は、獅子(ライオン)が千尋の谷に子供を落として、その子供を見守っているという姿で、左手の子は千尋の谷に落ちて仰向けになり、右手の子供は崖を這い上がっているという構図=写真=になっている。説明書きには、台座に使われている岩は富士山から運んだ溶岩であると記されている。これが黒く、ゴツゴツした感じで、崖というイメージにぴったり合っている。
大宮神社の狛犬は、獅子(ライオン)が千尋の谷に子供を落として、その子供を見守っているという姿で、左手の子は千尋の谷に落ちて仰向けになり、右手の子供は崖を這い上がっているという構図=写真=になっている。説明書きには、台座に使われている岩は富士山から運んだ溶岩であると記されている。これが黒く、ゴツゴツした感じで、崖というイメージにぴったり合っている。 戦後長らくアメリカの占領下にあり、1950年に朝鮮戦争が、1959年にはベトナム戦争が起き、戦時の緊張感を沖縄の人たちも同時に余儀なくされ、日本への復帰は1972年(昭和47年)5月15日である。しかも県内各地にアメリカ軍基地があり、沖縄県の総面積に10%余りを占める(沖縄県基地対策課「平成19年版沖縄の米軍及び自衛隊基地」)。時折、新聞で掲載される沖縄の反戦や反基地の気運は、北陸や東京に住む者にはリアリティとして伝わりにくい。沖縄は今でも闘っている。
戦後長らくアメリカの占領下にあり、1950年に朝鮮戦争が、1959年にはベトナム戦争が起き、戦時の緊張感を沖縄の人たちも同時に余儀なくされ、日本への復帰は1972年(昭和47年)5月15日である。しかも県内各地にアメリカ軍基地があり、沖縄県の総面積に10%余りを占める(沖縄県基地対策課「平成19年版沖縄の米軍及び自衛隊基地」)。時折、新聞で掲載される沖縄の反戦や反基地の気運は、北陸や東京に住む者にはリアリティとして伝わりにくい。沖縄は今でも闘っている。 沖縄県立博物館・美術館のメインの展示は「アトミックサンシャインの中へin沖縄~日本国平和憲法第九条下における戦後美術」(4月11日-5月17日)。ニューヨーク、東京での巡回展の作品に加え、沖縄現地のアーチストの作品を含めて展示している。「第九条と戦後美術」というテーマ。作品の展示に当たっては、当初、昭和天皇の写真をコラージュにした版画作品がリストにあり、美術館・県教委側とプロモーター側との事前交渉で展示から外すという経緯があった、と琉球新報インターネット版が伝えている。さまざまな経緯はあるものの、美術館側が主催者となって、「第九条と戦後美術」を開催するというところに今の「沖縄の気分」が見て取れる。
沖縄県立博物館・美術館のメインの展示は「アトミックサンシャインの中へin沖縄~日本国平和憲法第九条下における戦後美術」(4月11日-5月17日)。ニューヨーク、東京での巡回展の作品に加え、沖縄現地のアーチストの作品を含めて展示している。「第九条と戦後美術」というテーマ。作品の展示に当たっては、当初、昭和天皇の写真をコラージュにした版画作品がリストにあり、美術館・県教委側とプロモーター側との事前交渉で展示から外すという経緯があった、と琉球新報インターネット版が伝えている。さまざまな経緯はあるものの、美術館側が主催者となって、「第九条と戦後美術」を開催するというところに今の「沖縄の気分」が見て取れる。