★こだわり農家の未来
 奥能登で生産された米の販売会が、20日と21日に金沢市にあるスーパー「どんたく金沢西南部店」であった。店頭に並んだ奥能登の米は、海洋深層水を利用したもの、鶏ふんなどの有機肥料を用いたり、棚田ではざ干し、女性たちが耕す棚田米などそれぞれ特徴を打ち出した「こだわり米」なのだ。NPOや農業法人、生産組合など10つの団体が出品した=写真=。
奥能登で生産された米の販売会が、20日と21日に金沢市にあるスーパー「どんたく金沢西南部店」であった。店頭に並んだ奥能登の米は、海洋深層水を利用したもの、鶏ふんなどの有機肥料を用いたり、棚田ではざ干し、女性たちが耕す棚田米などそれぞれ特徴を打ち出した「こだわり米」なのだ。NPOや農業法人、生産組合など10つの団体が出品した=写真=。
どのくらいのこだわりかいくつか紹介する。農業法人すえひろ(珠洲市)が耕す田んぼは見ればわかる。一面に稲のじゅうたんの水田で飛びぬけて草(ヒエなど)が生えている田んぼがそれ。「農家では普通3回、除草剤をまくが、うちは1回しかまかないから」(北風八紘さん)。さらに売りは「完熟堆肥」だ。。牛ふんにもみ殻や糠(ぬか)、小豆の殻を入れて混ぜ、それを一冬寝かせて堆肥をつくる。完熟した堆肥は臭みがほとんどない。この堆肥を、苗を植える前の春先に田んぼに混ぜて土づくりを行う。いまでは350戸から耕作委託を受け、水田を65㌶に広げている。
川原農産(輪島市)のこだわりは、米も人間と同様に「伸び伸びと元気良く育てる」をモットーとしてる。稲株の間隔を広げ、葉っぱを伸ばさせる植え方をしている。一坪(3.3平方㍍)で45株が目安だ。普通は60から70株と言われるので、随分ゆとりある環境だ。自家製の堆肥は米糠ともみ殻を使い、田んぼに還元するやりかた。売れ筋は「能登ひかり」だ。一昔前まで能登の気候に合う品種ということで生産されていたが、モチモチ感のあるコシヒカリに押されて生産する農家は少なくなった。ところが、京都や大阪といった関西の寿司屋から見直されている。「ベタベタとした粘りがない分、握りやすく、食べたときにも口中でパラッとバラけるので、寿司によいのだという」(講談社新書『日本一おいしい米の秘密』)。さらに、このバラける食感がスープ料理にも合うということで、川原農産の能登ひかりは金沢市のレストラン「ポトフぅ」(同市里見町)で使用されている。
さらなるこだわりが、川原伸章さんにはある。「能登の米がおいしいのは、新潟・魚沼地方と同じ緯度にあるからって、よく農家自身が説明するでしょう。でも、こんな表現をしたらいつまでたっても能登の米は魚沼を超えられない。一番になれない」と心意気にもこだわる。川原農産も耕作委託を受け、水田を20㌶に広げている。平地に比べ、条件不利地であるがゆえに奥能登の生産農家はこだわらなければ生きていけない。その精神がものづくりのマインドを高める。
TPP(環太平洋経済協定)の論議が白熱している。加盟国間で取引される全品目の関税が2015年を目標に撤廃される。もし日本がTPPに加盟すれば、農家が生き抜く道は2つだろう。経営の大規模化か、黒毛和牛のような高品質の「こだわり農産品」だろう。面白いことに、先に紹介した「すえひろ」「川原農産」のように、こだわった米づくりに挑戦し続ける農家には耕作委託が舞い込み、期せずして経営規模も広がる傾向にある。これは奥能登だけでなく全国の傾向だろう。TPP時代のパイオニアとして光り輝き、生き抜くのはこうした「こだわり農家」ではないだろうか。そんなことをスーパーの店頭で思った。
⇒21日(日)夜・金沢の天気 はれ
 小田さんは、登山家の長谷川恒夫が「生きぬことが冒険」と語ったその生涯を紹介しながら話した。彼の登山人生は15歳のときにはじめて丹沢に登り、17歳で岩登りを知ることから始まる。26歳のとき、エベレスト登山隊に参加した。48人という大所帯での登山で、サミッター(登頂者)の生還を助けたが、自身の登頂はならならずに「組織登山」から、単独登山を志す。31歳で、アルプス三大北壁冬期単独登頂を果たし有名となる。その後も、アコンカグア南壁フランスルート冬期単独初登頂。その後、ダウラギリ、エベレストなどを目指したが敗退の連続で、ヒマラヤではサミッターにはなれなかった。1991年に未踏峰ウルタルIIに挑戦し、雪崩に巻き込まれ亡くなる。43歳だった。「挑戦し続ける人生こそ」と小田さんは言う。最後に、「好きこそものの上手なれ」という有名な言葉の説明をした。これには前文があり、「器用さ、稽古と好きのうち、好きこそものの上手なれ」だ。つまり、最初は下手でも、「好き」という人が最終的に名人になる。「好きなことに挑戦し続けよう、これが生きるセンス」と結んだ。
小田さんは、登山家の長谷川恒夫が「生きぬことが冒険」と語ったその生涯を紹介しながら話した。彼の登山人生は15歳のときにはじめて丹沢に登り、17歳で岩登りを知ることから始まる。26歳のとき、エベレスト登山隊に参加した。48人という大所帯での登山で、サミッター(登頂者)の生還を助けたが、自身の登頂はならならずに「組織登山」から、単独登山を志す。31歳で、アルプス三大北壁冬期単独登頂を果たし有名となる。その後も、アコンカグア南壁フランスルート冬期単独初登頂。その後、ダウラギリ、エベレストなどを目指したが敗退の連続で、ヒマラヤではサミッターにはなれなかった。1991年に未踏峰ウルタルIIに挑戦し、雪崩に巻き込まれ亡くなる。43歳だった。「挑戦し続ける人生こそ」と小田さんは言う。最後に、「好きこそものの上手なれ」という有名な言葉の説明をした。これには前文があり、「器用さ、稽古と好きのうち、好きこそものの上手なれ」だ。つまり、最初は下手でも、「好き」という人が最終的に名人になる。「好きなことに挑戦し続けよう、これが生きるセンス」と結んだ。 西日本や東日本の各地で12日、黄砂が観測されたと夕方のNHKニュースで知った。気象庁によると、東京都心で秋(9~11月)に黄砂が観測されたのは記録が電子化された1967年以降で初めてという。12月も含めると28年ぶり2回目という。そんな記録的なことだとは知らなかったが、穴水湾で見た霞がかった光景も「そういえば黄砂か」と、このニュースを見て改めて気づいたのだった。
西日本や東日本の各地で12日、黄砂が観測されたと夕方のNHKニュースで知った。気象庁によると、東京都心で秋(9~11月)に黄砂が観測されたのは記録が電子化された1967年以降で初めてという。12月も含めると28年ぶり2回目という。そんな記録的なことだとは知らなかったが、穴水湾で見た霞がかった光景も「そういえば黄砂か」と、このニュースを見て改めて気づいたのだった。 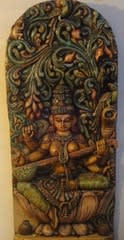 その豊穣の海は、その後に争いの海となる。1945年(昭和20年)8月11日にソビエト連邦軍が侵攻し、樺太の戦いが勃発し全島が制圧された。8月14日午後11時に日本がポツダム宣言の受諾を連合国に通達した。降伏の意図を明確に表明したあとにソ連軍が北方四島に侵攻し、8月28日から9月5日にかけて、択捉、国後、色丹島、歯舞群島を占領した。日本人の島民を強制的に追い出し、さらには北方四島を一方的にソ連領に編入した。
その豊穣の海は、その後に争いの海となる。1945年(昭和20年)8月11日にソビエト連邦軍が侵攻し、樺太の戦いが勃発し全島が制圧された。8月14日午後11時に日本がポツダム宣言の受諾を連合国に通達した。降伏の意図を明確に表明したあとにソ連軍が北方四島に侵攻し、8月28日から9月5日にかけて、択捉、国後、色丹島、歯舞群島を占領した。日本人の島民を強制的に追い出し、さらには北方四島を一方的にソ連領に編入した。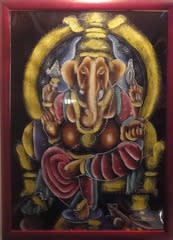 その話を聞いて、こんなニュースが気になった。東南アジア諸国連合(ASEAN)会議出席のためにベトナムを訪問した菅直人・温家宝首相の会談を中国側が拒否したことについて、中国側外交部が「日本側はASEANの会議期間中に、中国の主権の領土の完備性を侵犯する発言を、メディアを通じてまき散らし、両国の首脳が意思疎通をする雰囲気をぶち壊した。その結果は日本側がすべて責任を負わねばならない」と述べたという。
その話を聞いて、こんなニュースが気になった。東南アジア諸国連合(ASEAN)会議出席のためにベトナムを訪問した菅直人・温家宝首相の会談を中国側が拒否したことについて、中国側外交部が「日本側はASEANの会議期間中に、中国の主権の領土の完備性を侵犯する発言を、メディアを通じてまき散らし、両国の首脳が意思疎通をする雰囲気をぶち壊した。その結果は日本側がすべて責任を負わねばならない」と述べたという。 もう一つのサブイベント。国連大学高等研究所などが中心になって、研究者や行政担当者ら200人が携わった研究「日本の里山・里海評価(JSSA)」の成果報告会が22日に開催された=写真・上=。評価の中核を担う「科学評価パネル」の共同議長を務める中村教授が総括発言を行った。2007年にスタートしたJSSAは過去50年の国内の里山里海をテーマに自然がもたらす生態系サービス(恩恵)の変化を調べたもので、日本人の思い入れが深い里山里海について、初めて科学的な分析でまとめられたことになる。評価は、従来の研究や数値データを集約する手法で、里山や里海の荒廃と生態系サービスの劣化が日本各地で広がっている状況が裏づけられました。総括の中で、中村教授は「今後10年間の研究プログラムを組み、政策提言することが必要」と述べた。
もう一つのサブイベント。国連大学高等研究所などが中心になって、研究者や行政担当者ら200人が携わった研究「日本の里山・里海評価(JSSA)」の成果報告会が22日に開催された=写真・上=。評価の中核を担う「科学評価パネル」の共同議長を務める中村教授が総括発言を行った。2007年にスタートしたJSSAは過去50年の国内の里山里海をテーマに自然がもたらす生態系サービス(恩恵)の変化を調べたもので、日本人の思い入れが深い里山里海について、初めて科学的な分析でまとめられたことになる。評価は、従来の研究や数値データを集約する手法で、里山や里海の荒廃と生態系サービスの劣化が日本各地で広がっている状況が裏づけられました。総括の中で、中村教授は「今後10年間の研究プログラムを組み、政策提言することが必要」と述べた。 次にブース展開。石川県・国際生物多様性年クロージングイベント開催実行委員会のブースで「金沢大学の日」(21日、22日)を設け、里山里海プロジェクト(代表・中村教授)の取り組みをPRした=写真・中=。ブースでは、プロジェクトの「能登里山マイスター」養成プログラムや里山里海アクティビティ、里山里海自然学校、角間の里山自然学校、いきものマイスター養成講座などを円形写真を使って紹介。見学者へのノベルティでつくった「能登ゴマ」が人気だった。演出は、輪島市在住のデザイナーの萩野由紀さんに協力いただいた。
次にブース展開。石川県・国際生物多様性年クロージングイベント開催実行委員会のブースで「金沢大学の日」(21日、22日)を設け、里山里海プロジェクト(代表・中村教授)の取り組みをPRした=写真・中=。ブースでは、プロジェクトの「能登里山マイスター」養成プログラムや里山里海アクティビティ、里山里海自然学校、角間の里山自然学校、いきものマイスター養成講座などを円形写真を使って紹介。見学者へのノベルティでつくった「能登ゴマ」が人気だった。演出は、輪島市在住のデザイナーの萩野由紀さんに協力いただいた。 COP10公認の「石川エクスカーション」が23日と24日の2日間の日程で開催された。石川県の自然の魅力や保全の努力をアピールしようと石川県が企画、金沢大学が支援した。参加したのは、世界17カ国の研究者や環境NGO(非政府組織)メンバーら約50人。能登町の長龍寺本堂で行われた里山里海セミナーでは中村教授が金沢大学の能登半島での取り組みを紹介した。参加者から、どのような仕組みで大学と地域が連携するのかについて質問も。地元の地域起こしの組織「春蘭の里実行委員会」のメンバーが手入れしたアカマツ林のキノコ山を見学した。少々旬は過ぎていたが、見事なサマツがあちこちに。昼食では地元の人々たちの心尽くしの山菜料理を味わった。赤御膳が外国人には珍しく、会話が弾んだ=写真・下=。
COP10公認の「石川エクスカーション」が23日と24日の2日間の日程で開催された。石川県の自然の魅力や保全の努力をアピールしようと石川県が企画、金沢大学が支援した。参加したのは、世界17カ国の研究者や環境NGO(非政府組織)メンバーら約50人。能登町の長龍寺本堂で行われた里山里海セミナーでは中村教授が金沢大学の能登半島での取り組みを紹介した。参加者から、どのような仕組みで大学と地域が連携するのかについて質問も。地元の地域起こしの組織「春蘭の里実行委員会」のメンバーが手入れしたアカマツ林のキノコ山を見学した。少々旬は過ぎていたが、見事なサマツがあちこちに。昼食では地元の人々たちの心尽くしの山菜料理を味わった。赤御膳が外国人には珍しく、会話が弾んだ=写真・下=。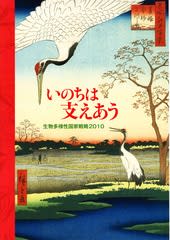 地元に残る言葉に「四刻八刻十二刻」がある。これは大雨が降った際に木曽三川に洪水が到達する予測時間のこと。揖斐川は四刻(8時間)、長良川は八刻(16時間)、木曽川は十二刻(24時間)で洪水が到達することを意味している。流域住民が水害に対して敏感であったことが実に良く分かる。
地元に残る言葉に「四刻八刻十二刻」がある。これは大雨が降った際に木曽三川に洪水が到達する予測時間のこと。揖斐川は四刻(8時間)、長良川は八刻(16時間)、木曽川は十二刻(24時間)で洪水が到達することを意味している。流域住民が水害に対して敏感であったことが実に良く分かる。 午前から午後にかけて開かれた「農業と生物多様性を考えるワークショップ」の会場=写真=をのぞいた。農業による開発と生態系保全のバランスをどう取ればよいのか、先進国や途上国の立場から発言が相次いでいた。会場で知り合いの日本人研究者と出会った。水田の生態学者である。「食料自給率が40%そこそこの日本は食料の超輸入国だ。日本は世界から見透かされている」と憤っていた。世界は農業と生態系のあり様を真剣に論じている。ところが、食料を外国に依存し、耕作放棄地が問題になっている日本はこの問題で何を言っても迫力がない、というのだ。「日本の農業をどう立て直すか考えねば」。確かにもどかしさを感じる。
午前から午後にかけて開かれた「農業と生物多様性を考えるワークショップ」の会場=写真=をのぞいた。農業による開発と生態系保全のバランスをどう取ればよいのか、先進国や途上国の立場から発言が相次いでいた。会場で知り合いの日本人研究者と出会った。水田の生態学者である。「食料自給率が40%そこそこの日本は食料の超輸入国だ。日本は世界から見透かされている」と憤っていた。世界は農業と生態系のあり様を真剣に論じている。ところが、食料を外国に依存し、耕作放棄地が問題になっている日本はこの問題で何を言っても迫力がない、というのだ。「日本の農業をどう立て直すか考えねば」。確かにもどかしさを感じる。
 日本でいったん絶滅した国際保護鳥のトキはかつて能登半島などで「ドォ」と呼ばれていた。田植えのころに田んぼにやってきて、早苗を踏み荒らすとされ、害鳥として農家から目の敵(かたき)にされていた。ドォは、「ドォ、ドォ」と追っ払うときの威嚇の声からその名が付いたとも言われる。米一粒を大切にした時代、トキを田に入れることでさえ許さなかったのであろう。昭和30年代の食料増産の掛け声で、農家の人々は収量を競って、化学肥料や農薬、除草剤を田んぼに入れるようになった。人に追われ、田んぼに生き物がいなくなり、トキは絶滅の道をたどった。
日本でいったん絶滅した国際保護鳥のトキはかつて能登半島などで「ドォ」と呼ばれていた。田植えのころに田んぼにやってきて、早苗を踏み荒らすとされ、害鳥として農家から目の敵(かたき)にされていた。ドォは、「ドォ、ドォ」と追っ払うときの威嚇の声からその名が付いたとも言われる。米一粒を大切にした時代、トキを田に入れることでさえ許さなかったのであろう。昭和30年代の食料増産の掛け声で、農家の人々は収量を競って、化学肥料や農薬、除草剤を田んぼに入れるようになった。人に追われ、田んぼに生き物がいなくなり、トキは絶滅の道をたどった。 2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議のハイレベル会議でのことだ。この会議では、「日本の里山里海における生物多様性」をテーマに、生物多様性条約事務長のジョグラフ氏や国連大学高等研究所(UNU-IAS)のA.H.ザクリ所長(当時)のほか、環境省の審議官、石川県と愛知県の知事、名古屋市長らが顔をそろえ、生物多様性を保全するモデルとして里山について言及した。120席余りの会場は人であふれた。COP9全体とすると、遺伝子組み換え技術や、バイオ燃料が生物多様性に及ぼす負の影響を最低限に抑え込むことなどが争点だったが、<SATOYAMA>が国際会議の場で、新しいキーワードとして浮上した感があった。これは、次回COP10の開催国が日本に固まっていたことや、先立って開催されたG8環境大臣会合(神戸)で採択された「生物多様性のための行動の呼びかけ」で、日本が「里山(Satoyama)イニシアティブ」という概念を国際公約として掲げたというタイミングもあった。
2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様性条約第9回締約国会議のハイレベル会議でのことだ。この会議では、「日本の里山里海における生物多様性」をテーマに、生物多様性条約事務長のジョグラフ氏や国連大学高等研究所(UNU-IAS)のA.H.ザクリ所長(当時)のほか、環境省の審議官、石川県と愛知県の知事、名古屋市長らが顔をそろえ、生物多様性を保全するモデルとして里山について言及した。120席余りの会場は人であふれた。COP9全体とすると、遺伝子組み換え技術や、バイオ燃料が生物多様性に及ぼす負の影響を最低限に抑え込むことなどが争点だったが、<SATOYAMA>が国際会議の場で、新しいキーワードとして浮上した感があった。これは、次回COP10の開催国が日本に固まっていたことや、先立って開催されたG8環境大臣会合(神戸)で採択された「生物多様性のための行動の呼びかけ」で、日本が「里山(Satoyama)イニシアティブ」という概念を国際公約として掲げたというタイミングもあった。