★畠山重篤氏の森への想い
「森は海の恋人」運動の提唱者で、気仙沼市在住の畠山重篤さんが、2011年の国際森林年を記念した国連森林フォーラム(UNFF)のフォレストヒーロー(世界で6人)に選ばれ、先月9日、ニューヨークの国連本部で表彰された。畠山さんは20年以上も前から広葉樹の植林を通じて森の環境を育て、川をきれいに保ち、カキ養殖の海を健康にしてきたことで知られる。
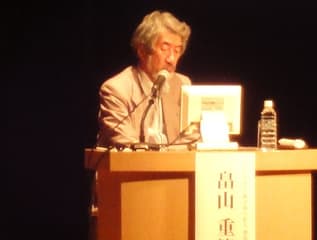 震災後、畠山さんとは3回お話をさせていただくチャンスを得た。1回目は震災2ヵ月後の5月12日にJR東京駅でコーヒーを飲みながら近況を聞かせていただき、9月に開催するシンポジウムでの基調講演をお願いした。その時に、間伐もされないまま放置されている山林の木をどう復興に活用すればよいか、どう住宅材として活かすか、まずはカキ筏(いかだ)に木材を使いたいと、長く伸びたあごひげをなでながら語っておられた。2回目は9月2日、輪島市で開催したシンポジウム「地域再生人材大学サミットin能登」(主催:能登キャンパス構想推進協議会)で。シンポジウムが終わり、居酒屋で地域の人たちと畠山さんを囲んで話し込んだ。3回目はことし2月2日、仙台市でのシンポジウム「市民による東日本大震災からの復興~創造と連携~」(主催:三井物産)の交流会で。9月のシンポジウムのお礼の挨拶をした。すると畠山さんの方から、「内緒なんだけれど、今度ニューヨークに表彰式があるんだ」とうれしそうに話された。UNFFのフォレストヒーローのことが新聞記事になったのはその数日後だった。
震災後、畠山さんとは3回お話をさせていただくチャンスを得た。1回目は震災2ヵ月後の5月12日にJR東京駅でコーヒーを飲みながら近況を聞かせていただき、9月に開催するシンポジウムでの基調講演をお願いした。その時に、間伐もされないまま放置されている山林の木をどう復興に活用すればよいか、どう住宅材として活かすか、まずはカキ筏(いかだ)に木材を使いたいと、長く伸びたあごひげをなでながら語っておられた。2回目は9月2日、輪島市で開催したシンポジウム「地域再生人材大学サミットin能登」(主催:能登キャンパス構想推進協議会)で。シンポジウムが終わり、居酒屋で地域の人たちと畠山さんを囲んで話し込んだ。3回目はことし2月2日、仙台市でのシンポジウム「市民による東日本大震災からの復興~創造と連携~」(主催:三井物産)の交流会で。9月のシンポジウムのお礼の挨拶をした。すると畠山さんの方から、「内緒なんだけれど、今度ニューヨークに表彰式があるんだ」とうれしそうに話された。UNFFのフォレストヒーローのことが新聞記事になったのはその数日後だった。
しかし、畠山さんの受賞の喜びは半ばだろう、と想像している。輪島での講演でこう述べていた。「戦後の拡大造林計画により雑木林が広がっていたのですが、エネルギー革命により薪炭林が役に立たなくなり、お金になるスギ、ヒノキを植えることになったのです。問題は木の種類ではなく、きちんと管理されているかどうかです。昨夕(9月1日)、飛行機に乗って上空から見ていたら、能登半島でもいかに真っ黒の山が多いかがよく分かります。つまり、貿易の自由化と為替などの問題があり、外材を買った方が安い時代になったため、せっかく植えたスギが伐期を迎えているのに、山に全然手が入らず、枝と枝が重なって日の光が差し込まない、下草が生えない、雨が降れば赤土が一気に流れる。つまり、海にとって良くないことばかりが川の流域にはあるということです」。受賞はしたものの、日本の山林では問題が山積している、と忸怩(じくじ)たる思いがあるのではと察している。5月12日にお会いしたとき、山林をもう一度何とかしたいと語っておられたことと重なる。
「森は海の恋人運動」を続けてきた畠山さん。海の復興、山の復権、地域の再生、どれも重いテーマを訴えて全国各地で講演が続く。来たる4月3日、受賞を記念して畠山さんの「海と共に生きる~よみがえる海の生き物・復興へのメッセージ~」と題した講演が日経ホール(東京)である。(※写真は、2月2日、仙台市でのシンポジウムでパネリストとして意見を述べる畠山重篤氏)
⇒20日(祝)夜・金沢の天気 くもり
 今回の大震災から学んだことが多々ある。その一つが日本は「災害列島」であるということだ。地震だけではない。津波、水害、雪害、火災、落雷などさまざまな災害がある。「天災は忘れたころにやってくる」(寺田寅彦の言葉とされる)は現代人への災害に備えよとの戒めの言葉だろう。改めてかみしめる言葉だ。
今回の大震災から学んだことが多々ある。その一つが日本は「災害列島」であるということだ。地震だけではない。津波、水害、雪害、火災、落雷などさまざまな災害がある。「天災は忘れたころにやってくる」(寺田寅彦の言葉とされる)は現代人への災害に備えよとの戒めの言葉だろう。改めてかみしめる言葉だ。 上勝町に宿泊して一番美味と感じたのは「かみカツ」だった。豚カツではない。地場産品の肉厚のシイタケをカツで揚げたものだ。上勝の地名とひっかけたネーミングなのだが、この「かみカツ丼」=写真=がお吸い物付きで800円。シイタケがかつ丼に化けるのである。こんなアイデアがこの地では次々と生まれている。全国的に上勝町といってもまだ知名度は低いが、「葉っぱビジネス」なら知名度は抜群だ。このビジネスはいろいろ考えさせてくれる。女性や高齢年齢層の住民を組織し、生きがいを与えるということ。「つま物」を農産物と同等扱いで農協を通じて全国に流通するとうこと。ビジネスの仕組みを創り上げたこと。たとえば、注文から出荷までの時間が非常に短い。畑に木を植えて収穫する。山に入って見つけていたのでは時間のロスが多いからだ。ただし、市場原理でいえば、つま物の需要が高くなって価格が跳ね上がることはありえないだろう。
上勝町に宿泊して一番美味と感じたのは「かみカツ」だった。豚カツではない。地場産品の肉厚のシイタケをカツで揚げたものだ。上勝の地名とひっかけたネーミングなのだが、この「かみカツ丼」=写真=がお吸い物付きで800円。シイタケがかつ丼に化けるのである。こんなアイデアがこの地では次々と生まれている。全国的に上勝町といってもまだ知名度は低いが、「葉っぱビジネス」なら知名度は抜群だ。このビジネスはいろいろ考えさせてくれる。女性や高齢年齢層の住民を組織し、生きがいを与えるということ。「つま物」を農産物と同等扱いで農協を通じて全国に流通するとうこと。ビジネスの仕組みを創り上げたこと。たとえば、注文から出荷までの時間が非常に短い。畑に木を植えて収穫する。山に入って見つけていたのでは時間のロスが多いからだ。ただし、市場原理でいえば、つま物の需要が高くなって価格が跳ね上がることはありえないだろう。 イツ製の木質チップボイラーを導入し、温泉や暖房設備に利用している=写真=。重油ボイラーは補助的に使っている。木質チップは1日約1.2トン使われ、すべて同町産でまかなわれている。チップ製造者の販売価格はチップ1t当たり16,000円。重油を使っていたころに比べ、3分の2程度のコストで済む。町内では薪(まき)燃料の供給システムのほか、都市在住の薪ストーブユーザーへ薪を供給することも試みている。地域内で燃料を供給する仕組みを構築することで、化石燃料の使用削減によるCO2排出抑制を図り、地域経済も好循環するまちづくりを目指している。さらに、森林の管理と整備が進むことになり、イノシシなどの獣害対策にもなる。
イツ製の木質チップボイラーを導入し、温泉や暖房設備に利用している=写真=。重油ボイラーは補助的に使っている。木質チップは1日約1.2トン使われ、すべて同町産でまかなわれている。チップ製造者の販売価格はチップ1t当たり16,000円。重油を使っていたころに比べ、3分の2程度のコストで済む。町内では薪(まき)燃料の供給システムのほか、都市在住の薪ストーブユーザーへ薪を供給することも試みている。地域内で燃料を供給する仕組みを構築することで、化石燃料の使用削減によるCO2排出抑制を図り、地域経済も好循環するまちづくりを目指している。さらに、森林の管理と整備が進むことになり、イノシシなどの獣害対策にもなる。 事を創るという発想に乏しい。日本全体がチャレンジ性が薄まっている中、受け身型になっていると常々考えている。事業をすることで地域が活性化し、社会貢献の意識があっても事業性がなければ継続しない。しかし、社会貢献をしようという若者を受け入れることは大いにプラスである。それはなぜか、現代は「役割ビジネス」だと思うからだ。
事を創るという発想に乏しい。日本全体がチャレンジ性が薄まっている中、受け身型になっていると常々考えている。事業をすることで地域が活性化し、社会貢献の意識があっても事業性がなければ継続しない。しかし、社会貢献をしようという若者を受け入れることは大いにプラスである。それはなぜか、現代は「役割ビジネス」だと思うからだ。 29日朝、徳島県の山間部にある上勝町(かみかつちょう)は雪だった=写真=。28日夜からの寒波のせいで積雪は5㌢ほどだが、まるで水墨画のような光景である。ただ、土地の人達にとって、この寒波は31年前の出来事を思い起こさせたことだろう。1981年2月2月、マイナス13度という異常寒波が谷あいの上勝地区を襲い、ほとんどのミカンの木が枯死した。当時、主な産物であった木材や温州みかんは輸入自由化や産地間競争が激しく、伸び悩んでいた。売上は約半分にまで減少し、上勝の農業は打撃を受けていた。そこへ追い打ちをかけるように強力な寒波が襲ったのだ。主力農産品を失って過疎化に拍車がかかった。若年人口が流出し、1950年に6356人あった上勝町の人口は一気に減り、2011年には1890人にまで低下した。高齢化率は49%となった。人口の半分が65歳以上の超高齢化社会がやってきた。
29日朝、徳島県の山間部にある上勝町(かみかつちょう)は雪だった=写真=。28日夜からの寒波のせいで積雪は5㌢ほどだが、まるで水墨画のような光景である。ただ、土地の人達にとって、この寒波は31年前の出来事を思い起こさせたことだろう。1981年2月2月、マイナス13度という異常寒波が谷あいの上勝地区を襲い、ほとんどのミカンの木が枯死した。当時、主な産物であった木材や温州みかんは輸入自由化や産地間競争が激しく、伸び悩んでいた。売上は約半分にまで減少し、上勝の農業は打撃を受けていた。そこへ追い打ちをかけるように強力な寒波が襲ったのだ。主力農産品を失って過疎化に拍車がかかった。若年人口が流出し、1950年に6356人あった上勝町の人口は一気に減り、2011年には1890人にまで低下した。高齢化率は49%となった。人口の半分が65歳以上の超高齢化社会がやってきた。 のつま物として商品化したもの。山あいの村では自生しているが、市場出荷が本格的になるにつれ、栽培も盛んに行われるようになった。採取は掘り起こしたり、機械を用いない。しかも、野菜などと比べて軽くて小さいので高齢者には打ってつけの仕事なのである。懐石料理など日本食には欠かせない、このつま物はこれまで店が近くの農家と契約したり、料理人が山に取りに行ったりすることが多かった。これを市場参入させたのが当時、農協の営農指導担当だった横石知二氏(1958年生)=写真=だった。
のつま物として商品化したもの。山あいの村では自生しているが、市場出荷が本格的になるにつれ、栽培も盛んに行われるようになった。採取は掘り起こしたり、機械を用いない。しかも、野菜などと比べて軽くて小さいので高齢者には打ってつけの仕事なのである。懐石料理など日本食には欠かせない、このつま物はこれまで店が近くの農家と契約したり、料理人が山に取りに行ったりすることが多かった。これを市場参入させたのが当時、農協の営農指導担当だった横石知二氏(1958年生)=写真=だった。 世界遺産でもあるイフガオの棚田でブランド米と呼ばれるのが、「WONDER」の米。赤米で、粒が日本のジャポニカ米と似てどちらかといえば丸い。値段は1㌔100ペソ。マニラのマーケットでは米は1㌔35ペソから40ペソなので、ざっと3倍くらいの値段だ。この米をアメリカのNGOなどが買い付けてイフガオの棚田耕作者の支援に動いているという。もう一つ、「棚田米ワイン」も味わった。甘い味でのど越しが粘つく。アルコール度数は表示されてなかったが25~30度くらいはありそうだ。ブタ肉のバーベキューと合いそうだ。イフガオでは棚田米に付加価値をつけて販売する動き出ているのだ。こうした取り組みが一つ、また一つと成功することを願う。
世界遺産でもあるイフガオの棚田でブランド米と呼ばれるのが、「WONDER」の米。赤米で、粒が日本のジャポニカ米と似てどちらかといえば丸い。値段は1㌔100ペソ。マニラのマーケットでは米は1㌔35ペソから40ペソなので、ざっと3倍くらいの値段だ。この米をアメリカのNGOなどが買い付けてイフガオの棚田耕作者の支援に動いているという。もう一つ、「棚田米ワイン」も味わった。甘い味でのど越しが粘つく。アルコール度数は表示されてなかったが25~30度くらいはありそうだ。ブタ肉のバーベキューと合いそうだ。イフガオでは棚田米に付加価値をつけて販売する動き出ているのだ。こうした取り組みが一つ、また一つと成功することを願う。 ちの田から心が離れてしまっていることではないかという印象を受けたのですが、そういう解釈でよいか」と質問を投げた。
ちの田から心が離れてしまっていることではないかという印象を受けたのですが、そういう解釈でよいか」と質問を投げた。 いまでもイフガオ族には一神教には違和感を持つ人が多いといわれる。コメに木に神が宿る「八百万の神」を信じるイフガオ族にとって、一神教は受け入れ難い。一方で、それゆえに少数民族が住む小中学校では、欧米の思想をベースとした文明化の教育、「エデュケーション(Education)」が徹底されてきた。今回の訪問では、14日に現地イフガオ州立大学で世界農業遺産(GIAHS)をテーマにしたフォラーム「世界農業遺産GIAHSとフィリピン・イフガオ棚田:現状・課題・発展性」(金沢大学、フィリピン大学、イフガオ州立大学主催)を開催したが、発表者からはこのクリスチャニティとエデュケーションの言葉が多く出てきた。どんな場面で出てくるのかというと、「イフガオの若い人たちが棚田の農業に従事したがらず、耕作放棄が増えるのは特にエデュケーション、そしてクリスチャニティに起因するのではないか」と。
いまでもイフガオ族には一神教には違和感を持つ人が多いといわれる。コメに木に神が宿る「八百万の神」を信じるイフガオ族にとって、一神教は受け入れ難い。一方で、それゆえに少数民族が住む小中学校では、欧米の思想をベースとした文明化の教育、「エデュケーション(Education)」が徹底されてきた。今回の訪問では、14日に現地イフガオ州立大学で世界農業遺産(GIAHS)をテーマにしたフォラーム「世界農業遺産GIAHSとフィリピン・イフガオ棚田:現状・課題・発展性」(金沢大学、フィリピン大学、イフガオ州立大学主催)を開催したが、発表者からはこのクリスチャニティとエデュケーションの言葉が多く出てきた。どんな場面で出てくるのかというと、「イフガオの若い人たちが棚田の農業に従事したがらず、耕作放棄が増えるのは特にエデュケーション、そしてクリスチャニティに起因するのではないか」と。 られたとされる棚田は「天国への階段」とも呼ばれ、イフガオ族が神への捧げものとして造ったとの神話があるという。村々の様子はまるで、私が物心ついた、50年前の奥能登の農村の光景である。男の子は青ばなを垂らして鬼ごっこに興じている。女子はたらいと板で洗濯をしている。赤ん坊をおんぶしながら。車が通ると車道に木の枝を置き、タイヤが踏むバキッという音を楽しんいる子がいる。家はどこも掘っ建て小屋のようで、中にはおらくそ3世代の大家族が暮らしている。ニワトリは放し飼いでエサをついばんでいる。器用にガケに登るニワトリもいる。七面鳥も放し飼い、ヤギも。家族の様子、動物たちの様子は冒頭に述べた「昭和30年代の明るい農村」なのだ。イフガオの今の光景である。
られたとされる棚田は「天国への階段」とも呼ばれ、イフガオ族が神への捧げものとして造ったとの神話があるという。村々の様子はまるで、私が物心ついた、50年前の奥能登の農村の光景である。男の子は青ばなを垂らして鬼ごっこに興じている。女子はたらいと板で洗濯をしている。赤ん坊をおんぶしながら。車が通ると車道に木の枝を置き、タイヤが踏むバキッという音を楽しんいる子がいる。家はどこも掘っ建て小屋のようで、中にはおらくそ3世代の大家族が暮らしている。ニワトリは放し飼いでエサをついばんでいる。器用にガケに登るニワトリもいる。七面鳥も放し飼い、ヤギも。家族の様子、動物たちの様子は冒頭に述べた「昭和30年代の明るい農村」なのだ。イフガオの今の光景である。
 つぶさにその様子を観察していると一つだけ気になることがあった。人と犬の関係が離れている。子供の後をついてきたり、子供が犬を抱きかかえたり、「人の友は犬」という光景ではないのだ。今回の訪問に同行してくれた、イフガオの農村を研究しているA氏にそのことを尋ねると、こともなげに「イフガオでは犬も家畜なんですよ。それが理由ですかね…」と答えた。人という友を失ったせいか、その運命を悟っているのか、犬たちに元気がない、そしてどれも痩せている。気のせいか。
つぶさにその様子を観察していると一つだけ気になることがあった。人と犬の関係が離れている。子供の後をついてきたり、子供が犬を抱きかかえたり、「人の友は犬」という光景ではないのだ。今回の訪問に同行してくれた、イフガオの農村を研究しているA氏にそのことを尋ねると、こともなげに「イフガオでは犬も家畜なんですよ。それが理由ですかね…」と答えた。人という友を失ったせいか、その運命を悟っているのか、犬たちに元気がない、そしてどれも痩せている。気のせいか。 ちで車が停まると、少女が手作りのネックスレのよなものを売りに来た。初めてのフィリピン、初日からカルチャーショックを受けた。それにしても、フィリピンは新旧、貧富がはっきりと浮かび上がる都市だ=写真=。
ちで車が停まると、少女が手作りのネックスレのよなものを売りに来た。初めてのフィリピン、初日からカルチャーショックを受けた。それにしても、フィリピンは新旧、貧富がはっきりと浮かび上がる都市だ=写真=。
 一方で、発表までに51時間余りという時間を費やす必要があったのかどうか。考察するヒントとなるニュースがいくつかあった。韓国中央日報インターネット版(日本語)によると、韓国の国家情報院の元世勲院長が20日、「北朝鮮が金正日総書記死去の時間と発表した17日午前8時30分に金総書記の専用列車は平壌竜城駅に停車中だった」と報告したと複数の与野党情報委員が伝えた。さらに引用すると、元院長は「金総書記は15日に現地指導をはじめ色々な行事があり、列車の動線を確認したが16~17日の2日間は動かなかったものと把握している」と説明した。金総書記が「走る野戦列車の中で重症急性心筋梗塞により死去した」という北朝鮮当局の公式発表とは違い、「待機中の列車」あるいは「第3の場所」で死去したということだ。ただし元院長は、「金総書記がどこかに行こうと列車に乗ってすぐに死去した可能性はある」と付け加えたという。
一方で、発表までに51時間余りという時間を費やす必要があったのかどうか。考察するヒントとなるニュースがいくつかあった。韓国中央日報インターネット版(日本語)によると、韓国の国家情報院の元世勲院長が20日、「北朝鮮が金正日総書記死去の時間と発表した17日午前8時30分に金総書記の専用列車は平壌竜城駅に停車中だった」と報告したと複数の与野党情報委員が伝えた。さらに引用すると、元院長は「金総書記は15日に現地指導をはじめ色々な行事があり、列車の動線を確認したが16~17日の2日間は動かなかったものと把握している」と説明した。金総書記が「走る野戦列車の中で重症急性心筋梗塞により死去した」という北朝鮮当局の公式発表とは違い、「待機中の列車」あるいは「第3の場所」で死去したということだ。ただし元院長は、「金総書記がどこかに行こうと列車に乗ってすぐに死去した可能性はある」と付け加えたという。