★世界農業遺産の潮流=2=
 世界農業遺産(GIAHS)の国際ワークショップが開催されている紹興市は中国・浙工省の江南水郷を代表する都市とされる。市内には川や運河が流れ、 その水路には大小の船が行き交っている。歴史を感じさせる建造物や石橋などと共に見える風景は「東洋のベニス」だろうか。人口60万人の水の都だ。
世界農業遺産(GIAHS)の国際ワークショップが開催されている紹興市は中国・浙工省の江南水郷を代表する都市とされる。市内には川や運河が流れ、 その水路には大小の船が行き交っている。歴史を感じさせる建造物や石橋などと共に見える風景は「東洋のベニス」だろうか。人口60万人の水の都だ。
「国策」としてGIAHSを推進する中国の思惑
紹興と言えば「紹興酒」、中国を代表する酒だ。ワークショップが開催され、われわれの宿泊場所ともなっている「咸亨酒店(Xianheng Hotel)」は、「酒店」の名の通り、紹興酒の造り酒屋がルーツ。『阿Q正伝』を表した文豪、魯迅の叔父が1894年に開業した酒屋として中国では知られる。その咸亨酒店が出しているのが紹興酒「太雕酒(たいちょうしゅ)」。8年間貯蔵し熟成された上質の紹興酒は琥珀色、さらに熟成18年ものとなると赤黒くふくよかな味わいなのだ。これが浙江料理と呼ばれるラインナップに合う。とくに豆腐料理。浙江の豆腐は独特のにおいがする。「豆腐」の意味がなとなく理解できる。このにおいはすぐ慣れる。
前回のブログで中国にいることを知った友人からメールが届いた。「こんなややこしい時期に中国に行って大丈夫か」との助言である。28日と29日の両日の街の様子など見た限りでは、テレビのニュースにあるような政治的なスローガンを掲げた喧騒は見当たらない。また、現地の浙江日報(28日付)を広げても、日本関係の記事は国際面に「日否決東京都登島申請」などと通常の記事扱いである。宿泊しているホテルの1階に「日本料理」の店もあるが、客は入っている。
話を世界農業遺産のワークショップに戻す。国連の食料農業機関(FAO)はGIAHSサイトを100から150ヵ所で認定したいと述べている。このGIAHS認定で一番熱心なのは中国だろう。すでに世界で12件が認定されているが、このうち中国は4件。「Rice-Fish Agriculture(水田養魚農業)」(浙江省青田県)、「Hani Rice Terraces System(ハニ族の棚田群のシステム)」(雲南省ハニ族イ族自治州など)、「Wannian traditional rice culture system(万年の伝統的な稲作文化の仕組み)」(江西省万年県)、「Dong’s Rice Fish Duck System(トン族の稲作・養魚・養鴨システム)」(貴州省従エ県)である。これに、昨日の中国側の発表によると、来月(9月)に雲南省の「プーアル茶」の産地と内モンゴルの「乾燥地農業」が認定され、2件加わる。さらに、浙江省のカヤの林「会稽山の古香榧林」を準備中だ。広大で農業の歴史がある中国は有利だ。ここれほどまでになぜ中国はGIAHSに積極的なのだろうか。
中国側の参加者のスピーチだ。「山に住んでいると、その山の景観や価値というものは分からない。下りて振り返って眺める、他の山から自分の山を眺めて初めて自分の山の価値が分かるものだ」と。GIAHS認定では、日本の場合(佐渡と能登)は地域の自治体が名乗りを上げて、申請書きを行う。中国は政府が主導している。農業振興という面もあるが、ハニ族やイ族、トン族といった少数民族への配慮もあるだろう。少数民族が守ってきた伝統の農業に国際評価をつける、その「山の価値」を見直してもらい、プライドを持たせるという明確な意図があるように思える。日本の地域活性化というレベルを超えた「国策」という勢いを感じたのは自分だけだろうか。 ※写真は、水郷の都・紹興をイメージした咸亨酒店の中庭
⇒30日(木)朝・中国の紹興市の天気 はれ
 きょう29日から中国・浙江省紹興市で開催されている「世界農業遺産の保全と管理に関する国際ワークショップ」(主催:中国政府農業部、国連食糧農業機関、中国科学院)の席上で中国側から披露された。昨年6月、国連食糧農業遺産(FAO、本部ローマ)が制定する世界農業遺産に「能登の里山里海」と佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」が認定された。この国際的な評価をどう維持、発展させたらよいか、ワークショップでは中国と日本のGIAHS関係者120人が集まり、GIAHSに認定されたサイト(地域)の現状や環境保全、将来に向けての運営管理など意見交換するものだ。日本から農林水産省、東京大学、国連大学、石川県、佐渡市の関係者17人が参加した。石川県から泉谷満寿裕・能登地域GIAHS推進協議会会長(珠洲市長)、金沢大学の中村浩二教授、渡辺泰輔・石川県環境部里山創成室長らが出席している。
きょう29日から中国・浙江省紹興市で開催されている「世界農業遺産の保全と管理に関する国際ワークショップ」(主催:中国政府農業部、国連食糧農業機関、中国科学院)の席上で中国側から披露された。昨年6月、国連食糧農業遺産(FAO、本部ローマ)が制定する世界農業遺産に「能登の里山里海」と佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」が認定された。この国際的な評価をどう維持、発展させたらよいか、ワークショップでは中国と日本のGIAHS関係者120人が集まり、GIAHSに認定されたサイト(地域)の現状や環境保全、将来に向けての運営管理など意見交換するものだ。日本から農林水産省、東京大学、国連大学、石川県、佐渡市の関係者17人が参加した。石川県から泉谷満寿裕・能登地域GIAHS推進協議会会長(珠洲市長)、金沢大学の中村浩二教授、渡辺泰輔・石川県環境部里山創成室長らが出席している。
 佐渡の金山跡=写真・上=に入った(16日)。当時の坑道の様子が手に取るように分かる。鉱脈に沿って掘り進んでいくと大量の地下水が噴出したので、掘り進むために水上輪(手動のポンプ)が導入されていた。紀元前3世紀にアルキメデスが考案したアルキメデス・ポンプを応用したもの。長さ9尺(2.7m)、上口径1尺(30.3㎝)、下口径1尺2寸(30.9㎝)位の円錐の木筒で、内部がらせん堅軸が装置されていて、上端についたクランクを回転させると、水が順々に汲み上げられて、上部の口から排出されるようになっていた。
佐渡の金山跡=写真・上=に入った(16日)。当時の坑道の様子が手に取るように分かる。鉱脈に沿って掘り進んでいくと大量の地下水が噴出したので、掘り進むために水上輪(手動のポンプ)が導入されていた。紀元前3世紀にアルキメデスが考案したアルキメデス・ポンプを応用したもの。長さ9尺(2.7m)、上口径1尺(30.3㎝)、下口径1尺2寸(30.9㎝)位の円錐の木筒で、内部がらせん堅軸が装置されていて、上端についたクランクを回転させると、水が順々に汲み上げられて、上部の口から排出されるようになっていた。 そのトキがいまでは佐渡の人々に農業の展望、知恵と夢を与えている。7月16日から18日の日程で開催された「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)=写真・中=に参加した。同会議の佐渡市での開催は初めてで、期間中、日本、中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。2008年9月のトキ放鳥に伴い、トキとの共生を掲げた地域づくりが住民に浸透し始め、2011年6月に国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS)に登録されたことで、佐渡の人々の視野が世界に広がった。今回の国際会議はその意気込みを示すものだ。
そのトキがいまでは佐渡の人々に農業の展望、知恵と夢を与えている。7月16日から18日の日程で開催された「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)=写真・中=に参加した。同会議の佐渡市での開催は初めてで、期間中、日本、中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。2008年9月のトキ放鳥に伴い、トキとの共生を掲げた地域づくりが住民に浸透し始め、2011年6月に国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS)に登録されたことで、佐渡の人々の視野が世界に広がった。今回の国際会議はその意気込みを示すものだ。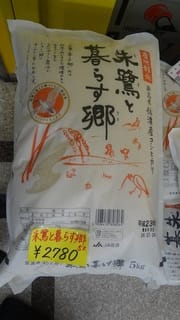 に2割(1200ha)にも達している。さらに、生きものの豊かさを検証し、トキの生息環境を把握する科学的データの評価手法も導入されている。「トキのGPSデータとモニタリングデータ」は研究機関の行った生物調査や農業者の「生きもの調査」を役立てるため、佐渡市で整備済みの「農地GIS」を改修して、環境省のトキモニタリングデータや新潟大学などで行われている生物種と密度調査を組み込むシステムだ。これにより、生き物を育む農法が、生物へ与える効果やトキが好む餌場の把握が科学的にできる。
に2割(1200ha)にも達している。さらに、生きものの豊かさを検証し、トキの生息環境を把握する科学的データの評価手法も導入されている。「トキのGPSデータとモニタリングデータ」は研究機関の行った生物調査や農業者の「生きもの調査」を役立てるため、佐渡市で整備済みの「農地GIS」を改修して、環境省のトキモニタリングデータや新潟大学などで行われている生物種と密度調査を組み込むシステムだ。これにより、生き物を育む農法が、生物へ与える効果やトキが好む餌場の把握が科学的にできる。 中谷宇吉郎の研究業績と人となりを紹介する「中谷宇吉郎雪の科学館」=写真=を昨日訪ねた。宇吉郎の出身地である加賀市片山津温泉に建物がある。館内を巡ると、北海道大学で世界で初めて人工的に雪の結晶を作り出したこと、雪や氷に関する科学の分野を次々に開拓し、その活躍の場をグリーンランドなど世界各地に広げたことが分かる。館内では、アイスボックスの中でダイヤモンドダストを発生させる実験も行っている。意外だったのは、多彩な趣味だ。絵をよく描き、とくに随筆では日常身辺の話題から科学の解説まで幅広い広い。海外で学術学会があるたびに蓄音機とレコードと踊りの小道具を持参し、パーティ後に日本の踊りを披露していたとのエピソードがあるくらい。陽性な人柄が目に浮かぶ。『霜の花』など科学映画の草分けとしても知られる。
中谷宇吉郎の研究業績と人となりを紹介する「中谷宇吉郎雪の科学館」=写真=を昨日訪ねた。宇吉郎の出身地である加賀市片山津温泉に建物がある。館内を巡ると、北海道大学で世界で初めて人工的に雪の結晶を作り出したこと、雪や氷に関する科学の分野を次々に開拓し、その活躍の場をグリーンランドなど世界各地に広げたことが分かる。館内では、アイスボックスの中でダイヤモンドダストを発生させる実験も行っている。意外だったのは、多彩な趣味だ。絵をよく描き、とくに随筆では日常身辺の話題から科学の解説まで幅広い広い。海外で学術学会があるたびに蓄音機とレコードと踊りの小道具を持参し、パーティ後に日本の踊りを披露していたとのエピソードがあるくらい。陽性な人柄が目に浮かぶ。『霜の花』など科学映画の草分けとしても知られる。 瑣細な盲点のために著しく左右されるようなこともありそうである」と記した。科学を一般の人々に分りやすく伝える方法として随筆を書いたのだった。
瑣細な盲点のために著しく左右されるようなこともありそうである」と記した。科学を一般の人々に分りやすく伝える方法として随筆を書いたのだった。 「痛車(いたしゃ)」という言葉をご存知だろうか。車体に漫画やアニメ、ゲームのキャラクターなどのステッカーを貼り付けたり、塗装した乗用車のことだ。あるいはそのような改造を車のことを指すそうだ。「萌車(もえしゃ)」とも呼ばれるようだ(「ウイキペディア」より)。面白いのは、同様の原付やバイクを「痛単車(いたんしゃ)」、自転車の場合は「痛チャリ(いたチャリ)」、アニメの装飾を施したラッピング電車を「痛電車(いたでんしゃ)」とこの世界では呼ぶようだ。。ただ、イタリア車を意味する「イタ車」なら、その意味は分かるが、なぜ「痛車」と呼ぶのか、ネットで調べてもよく分からない。
「痛車(いたしゃ)」という言葉をご存知だろうか。車体に漫画やアニメ、ゲームのキャラクターなどのステッカーを貼り付けたり、塗装した乗用車のことだ。あるいはそのような改造を車のことを指すそうだ。「萌車(もえしゃ)」とも呼ばれるようだ(「ウイキペディア」より)。面白いのは、同様の原付やバイクを「痛単車(いたんしゃ)」、自転車の場合は「痛チャリ(いたチャリ)」、アニメの装飾を施したラッピング電車を「痛電車(いたでんしゃ)」とこの世界では呼ぶようだ。。ただ、イタリア車を意味する「イタ車」なら、その意味は分かるが、なぜ「痛車」と呼ぶのか、ネットで調べてもよく分からない。
 年4月から9月に放送されたテレビアニメ『花咲くいろは』(全26話)の聖地なのだ。東京育ちの女子高生「松前緒花」が石川県の「湯乃鷺(ゆのさぎ)温泉」の旅館「喜翆荘」を経営する祖母のもとに身を寄せ、旅館の住み込みアルバイトとして働きながら学校に通う。個性的な従業員との確執や、人間模様の中で成長しいく。湯乃鷺温泉の舞台となったのが湯涌温泉だった。菓子屋の店員に尋ねると、毎週末には「なんとなく集まってくる」のだという。
年4月から9月に放送されたテレビアニメ『花咲くいろは』(全26話)の聖地なのだ。東京育ちの女子高生「松前緒花」が石川県の「湯乃鷺(ゆのさぎ)温泉」の旅館「喜翆荘」を経営する祖母のもとに身を寄せ、旅館の住み込みアルバイトとして働きながら学校に通う。個性的な従業員との確執や、人間模様の中で成長しいく。湯乃鷺温泉の舞台となったのが湯涌温泉だった。菓子屋の店員に尋ねると、毎週末には「なんとなく集まってくる」のだという。 島根県海士町は隠岐諸島で水が豊富に湧き出ることで知られる。日本の名水百選にも選ばれた「天川の水」は鉱物臭さを感じさせない口当たりのよい水だった。また、湧水を利用した田んぼがところどころに広がる=写真・上=。ここで獲れた米は隠岐の他の島に「輸出」をしている。
島根県海士町は隠岐諸島で水が豊富に湧き出ることで知られる。日本の名水百選にも選ばれた「天川の水」は鉱物臭さを感じさせない口当たりのよい水だった。また、湧水を利用した田んぼがところどころに広がる=写真・上=。ここで獲れた米は隠岐の他の島に「輸出」をしている。 から起きていて、歴史性がある。輪島の海士町は江戸時代の漁労集団がそのまま地名になった感がある。歴史の尺度に違いがあり、ルーツを云々するということには無理があると気がついた。
から起きていて、歴史性がある。輪島の海士町は江戸時代の漁労集団がそのまま地名になった感がある。歴史の尺度に違いがあり、ルーツを云々するということには無理があると気がついた。 (「Iターンの島」~3からの続き、山内道雄・海士町長の講演から) ブランド化はユーザーや消費者の評価を通しての言葉だ。日本で一番きびしい評価を通りくぐらなければブランドにならない。それは東京の市場だ。隠岐牛を平成18年3月に初めて3頭を出荷した。このとき全て高品位のA5に格付けされ、肉質は松阪牛並の評価を受けた。ことし3月までに742頭を東京に出荷したが、A5の格付率は52%だ。リーマン・ショック(2008年9月)以降は、高級牛の価格は下がったが、それでもこれまで枝肉最高値1㌔当たり4205円、これは店頭値で3万円もする。枝肉の平均価格でも2169円。これを一頭当りで換算すると91万円となる。
(「Iターンの島」~3からの続き、山内道雄・海士町長の講演から) ブランド化はユーザーや消費者の評価を通しての言葉だ。日本で一番きびしい評価を通りくぐらなければブランドにならない。それは東京の市場だ。隠岐牛を平成18年3月に初めて3頭を出荷した。このとき全て高品位のA5に格付けされ、肉質は松阪牛並の評価を受けた。ことし3月までに742頭を東京に出荷したが、A5の格付率は52%だ。リーマン・ショック(2008年9月)以降は、高級牛の価格は下がったが、それでもこれまで枝肉最高値1㌔当たり4205円、これは店頭値で3万円もする。枝肉の平均価格でも2169円。これを一頭当りで換算すると91万円となる。 の出荷をこれまでの25万個から50万個に、また岩ガキだけでなく、旬感凍結「活いか」といった加工商品など続々と誕生している。
の出荷をこれまでの25万個から50万個に、また岩ガキだけでなく、旬感凍結「活いか」といった加工商品など続々と誕生している。 この高校には町の職員4人を派遣している。実践的なまちづくりや商品開発などを通して地域づくりを担うリーダー育成を目指す「地域創造コース」と、少人数指導で難関大学にも進学できる「特別進学コース」がある。生徒が企画した地域活性に向けた観光プラン「ヒトツナキ」が観光甲子園でグランブリを受賞した。学校連携型の公営塾「隠岐国学習センター」を平成22年に創設し、従来の塾の枠を超えた高校との連携により、学習意欲を高め、学力に加え社会人基礎力も鍛える独自のプログラムも展開している。特徴的なのは、全国から意欲ある生徒の募集に向け、寮費食費の補助などの「島留学」制度を平成22年から新設し、意欲ある高校生が集まることで、小規模校の課題である固定化された人間関係と価値観の同質化を打破したい、これによって刺激と切嵯琢磨を生み出すことを目指した。この財源には、町職員の給与カット(縮減)分を充てている。この取り組みで平成20年度27人だった入学者は、関東や関西などから応募者があり、今年度は59人となった。
この高校には町の職員4人を派遣している。実践的なまちづくりや商品開発などを通して地域づくりを担うリーダー育成を目指す「地域創造コース」と、少人数指導で難関大学にも進学できる「特別進学コース」がある。生徒が企画した地域活性に向けた観光プラン「ヒトツナキ」が観光甲子園でグランブリを受賞した。学校連携型の公営塾「隠岐国学習センター」を平成22年に創設し、従来の塾の枠を超えた高校との連携により、学習意欲を高め、学力に加え社会人基礎力も鍛える独自のプログラムも展開している。特徴的なのは、全国から意欲ある生徒の募集に向け、寮費食費の補助などの「島留学」制度を平成22年から新設し、意欲ある高校生が集まることで、小規模校の課題である固定化された人間関係と価値観の同質化を打破したい、これによって刺激と切嵯琢磨を生み出すことを目指した。この財源には、町職員の給与カット(縮減)分を充てている。この取り組みで平成20年度27人だった入学者は、関東や関西などから応募者があり、今年度は59人となった。 それまでの「地縁血縁の選挙」だった島の町長選挙に、町議2期をつとめた山内道雄氏が大胆な行政改革を訴えて当選した。山内氏は元NTT社員。電電公社からNTTに変革したときの経験を活かし、「役場は住民のためのサービス総合株式社である」と町職員の意識改革を迫った。意識を変えるために年功序列を廃止して適材適所、組織を現場主義へと再編していく。その延長線上に「Iターンの島」がある。視察3日目(6月10日)、その山内町長が「離島発!地域再生への挑戦~最後尾から最先端へ~」と題して講演した。74歳、話す言葉が理詰めで聞きやすい。以下、講演を要約する。
それまでの「地縁血縁の選挙」だった島の町長選挙に、町議2期をつとめた山内道雄氏が大胆な行政改革を訴えて当選した。山内氏は元NTT社員。電電公社からNTTに変革したときの経験を活かし、「役場は住民のためのサービス総合株式社である」と町職員の意識改革を迫った。意識を変えるために年功序列を廃止して適材適所、組織を現場主義へと再編していく。その延長線上に「Iターンの島」がある。視察3日目(6月10日)、その山内町長が「離島発!地域再生への挑戦~最後尾から最先端へ~」と題して講演した。74歳、話す言葉が理詰めで聞きやすい。以下、講演を要約する。 9日朝、ときおり小雨が降る梅雨空。七類(しちるい)港を午前9時30分発のフェリー「くにが」(2375㌧)に乗り込んだ。フェリー乗り場は釣り客などでにぎわっていた。壁には「『竹島』かえれ島と海」と書かれた看板が掲げられていた。「竹島の領土権の確立と漁業の安全操業の確保を」と記された島根県の看板だ。
9日朝、ときおり小雨が降る梅雨空。七類(しちるい)港を午前9時30分発のフェリー「くにが」(2375㌧)に乗り込んだ。フェリー乗り場は釣り客などでにぎわっていた。壁には「『竹島』かえれ島と海」と書かれた看板が掲げられていた。「竹島の領土権の確立と漁業の安全操業の確保を」と記された島根県の看板だ。 視察の目的の本論に入る。なぜ海士町が注目されているのか。2300人の小さな島にこの7年間で310人も移住者(Iターン)が来ているのだ。この島は水が湧き、米が採れ、魚介類も豊富で暮らしやすい。でも、そのような地域は日本でほかにもある。なぜ海士町なのか、それを考えるワークショップが午後2時から海士町中央公民館で開かれた。参加者は今回の視察ツアーを企画した島根大学名誉教授の保母武彦氏、一橋大学教授の寺西俊一氏、国連大学高等研究所、静岡大学、大阪大学、自治体など40人余り。町側は山内道雄町長ほか若き移住者ら5人が集った。事例報告したのはその移住者の一人で、ソニーで人材育成事業に携わった経験がある岩本悠氏。「学校魅力化による地域魅力化への挑戦」と題して、少子化の影響を受け、統廃合の危機が迫る地域の県立島前(どうぜん)高校をテコに、「子育ての島・人づくりの島」へと教育ブランドへと盛り上げてきたプロセスを詳細に語った。「ピンチは変革と飛躍のチャンス」ととらえ、県立高校に町がかかわり、ときに対立しながらも一体となって高校改革を進めていく。そのコンセプトを地域創造に。生徒たちは、地域を元気にする観光プランを競う「観光甲子園」にエントリーしてグランプリを獲得した。この島では、農水産物だけでなく教育まで魅力あるもに発信する。そして全国から高校生が集まり、島の生徒と合わせ60人、2クラスになった。その「島前高校魅力化プロデューサー」が岩本氏だ。
視察の目的の本論に入る。なぜ海士町が注目されているのか。2300人の小さな島にこの7年間で310人も移住者(Iターン)が来ているのだ。この島は水が湧き、米が採れ、魚介類も豊富で暮らしやすい。でも、そのような地域は日本でほかにもある。なぜ海士町なのか、それを考えるワークショップが午後2時から海士町中央公民館で開かれた。参加者は今回の視察ツアーを企画した島根大学名誉教授の保母武彦氏、一橋大学教授の寺西俊一氏、国連大学高等研究所、静岡大学、大阪大学、自治体など40人余り。町側は山内道雄町長ほか若き移住者ら5人が集った。事例報告したのはその移住者の一人で、ソニーで人材育成事業に携わった経験がある岩本悠氏。「学校魅力化による地域魅力化への挑戦」と題して、少子化の影響を受け、統廃合の危機が迫る地域の県立島前(どうぜん)高校をテコに、「子育ての島・人づくりの島」へと教育ブランドへと盛り上げてきたプロセスを詳細に語った。「ピンチは変革と飛躍のチャンス」ととらえ、県立高校に町がかかわり、ときに対立しながらも一体となって高校改革を進めていく。そのコンセプトを地域創造に。生徒たちは、地域を元気にする観光プランを競う「観光甲子園」にエントリーしてグランプリを獲得した。この島では、農水産物だけでなく教育まで魅力あるもに発信する。そして全国から高校生が集まり、島の生徒と合わせ60人、2クラスになった。その「島前高校魅力化プロデューサー」が岩本氏だ。