★能登の「田の神」とイフガオの「ブルル」
ユネスコ無形文化遺産に登録されている「奥能登のあえのこと」は、田の神をもてなす農 耕儀礼として知られている。毎年12月5日、その家の主(あるじ)は田んぼに神様を迎えに行く。あたかもそこに神がいるがごとく身振り手振りで迎え、自宅に招き入れる。お風呂に入ってもらい、座敷でご馳走でもてなす。田の神は目が不自由であるとの設定になっていて、ホスピタリティ(もてなし)が行き届く丁寧な所作が特徴だ。もてなし方は土蔵で執り行うパターンなど、その家々によって流儀が異なる。田の神に恵みに感謝し、1年の疲れを癒してもらうコンセプトは同じだ。
耕儀礼として知られている。毎年12月5日、その家の主(あるじ)は田んぼに神様を迎えに行く。あたかもそこに神がいるがごとく身振り手振りで迎え、自宅に招き入れる。お風呂に入ってもらい、座敷でご馳走でもてなす。田の神は目が不自由であるとの設定になっていて、ホスピタリティ(もてなし)が行き届く丁寧な所作が特徴だ。もてなし方は土蔵で執り行うパターンなど、その家々によって流儀が異なる。田の神に恵みに感謝し、1年の疲れを癒してもらうコンセプトは同じだ。
昨年1月に訪れたフィリピン・ルソン島のイフガオ棚田にも田の神ブルル(Bulul)が祀られている。イフガオ族の人々に稲作を教えたのがブルルとの言い伝えがある。木彫りのブルルが田の畦(あぜ)に置かれ、米づくりをするイフガオの人々と稲の実りを見守っている。能登 でもイフガオでも、稲作は神からの授かりものという概念に、モンスーンアジアにおける文化の共通性を感じる。
でもイフガオでも、稲作は神からの授かりものという概念に、モンスーンアジアにおける文化の共通性を感じる。
能登の里山里海とイフガオ棚田はともに国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS)に認定されている。世界に12あるGIAHSサイトの関係者が集っての国際フォーラムがことし5月下旬、能登半島で開催される。隔年開催の同フォーラムはこれまでローマ、ブエノスアイレス、北京で開かれている。フォーラムの開催にあたっては、昨年5月、石川県の谷本正憲知事がローマにあるFAO本部にグラジアノ・ダ・シルバ事務局長を訪ね、石川県での開催を提案し、受け入れられた。いわば、国際会議のトップセールスだった。ちなみに、前回(2011年6月)のフォーラムは、FAOと中国科学アカデミーなどが共同で北京で開催した。
GIAHS国際フォーラムの目的は、各国のGIAHSサイトが国際的なパートナーシップを確認するとともに、それぞれのサイトが有する独自の伝統的な農業システムや農業の生物多様性や文化を互いに学ぶことにある。これによって、「小規模、先住民、地域社会」の単なる遺産として忘れ去られがちな独自の伝統的な農業システムが、歴史で磨かれた人類の知識と経験を国際的に意見交換するというグローバルな意義づけを持つことになる。
もう一つ、この国際フォーラムでは、FAOが新たなGIAHSサイトを認定する。報道によると、800年の伝統を有する静岡の茶生産の伝統農法「茶草場」の認定に向けて、掛川市など5市町がFAO日本事務所(横浜市)に申請書を提出した(2012年12月29日付・中日新聞ホームページ)。また、中国では、雲南省の「プーアル茶」産地が認定に向けて動いている(2012年9月、浙工省紹興市で開催されたGIAHS国際ワークショップで中国側発表)。日本と中国の茶どころのほか、スペインのイベリコ豚の産地も希望している(2011年6月、北京国際フォーラムでの報告)。
伝統的な農産品ブランドがGIAHSの仲間入りを目指す能登での国際フォーラムは国内外で注目を集めそうだ。冒頭で述べた、能登の農耕儀礼「あえのこと」とイフガオ棚田のブルルをテーマに文化交流や研究が進むことで、これまでと違った視点の文化価値が生まれることにもなる。そして能登地域にとっても、フォーラムを通じた国際発信という意味ではまたとないチャンスが巡ってきたといえる。
⇒3日(木)朝・金沢の天気 ゆき
 観なことか。経済から外交、そして地域、職場、家庭までその「在り様」がパノラマのように広がって見える。
観なことか。経済から外交、そして地域、職場、家庭までその「在り様」がパノラマのように広がって見える。
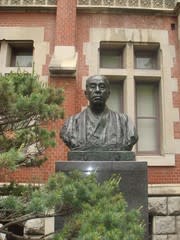 「近隣外交」という言葉ほど面倒なものはないと、日本人の多くは思っているのではないだろうか。尖閣諸島をめぐる中国側の執拗な動きは連日のように報道されている。「(日本)政府は29日、中国が東シナ海での大陸棚設定について、今月14日に国際機関の大陸棚限界委員会に申請した案を検討しないよう、同委員会に求めた。大陸棚は領海の基線から200カイリまでが基本だが、地形の特徴にもよる。中国は、中国大陸から尖閣諸島を含む沖縄トラフまで大陸棚が自然に延びていると主張。日本は、尖閣諸島が固有の領土であるため全く受け入れられないと表明した。」(12月29日付・朝日新聞ホームページ)
「近隣外交」という言葉ほど面倒なものはないと、日本人の多くは思っているのではないだろうか。尖閣諸島をめぐる中国側の執拗な動きは連日のように報道されている。「(日本)政府は29日、中国が東シナ海での大陸棚設定について、今月14日に国際機関の大陸棚限界委員会に申請した案を検討しないよう、同委員会に求めた。大陸棚は領海の基線から200カイリまでが基本だが、地形の特徴にもよる。中国は、中国大陸から尖閣諸島を含む沖縄トラフまで大陸棚が自然に延びていると主張。日本は、尖閣諸島が固有の領土であるため全く受け入れられないと表明した。」(12月29日付・朝日新聞ホームページ) 松井選手のホームタウンは石川県能美市にある。私は金沢のテレビ局時代に何度か自宅を取材に訪れた。松井選手が星稜高校の時代、「夏の甲子園」石川大会の中継、本大会での取材と夏は松井一色だった。強打者ぶりは「伝説」にもなった。1992年夏の全国高校野球選手権2回戦の明徳義塾(高知)戦で、5打席連続敬遠されて論議を呼んだ。
松井選手のホームタウンは石川県能美市にある。私は金沢のテレビ局時代に何度か自宅を取材に訪れた。松井選手が星稜高校の時代、「夏の甲子園」石川大会の中継、本大会での取材と夏は松井一色だった。強打者ぶりは「伝説」にもなった。1992年夏の全国高校野球選手権2回戦の明徳義塾(高知)戦で、5打席連続敬遠されて論議を呼んだ。 猪瀬氏のキャラクターが面白い。国にものを言う前職の石原慎太郎氏とイメージがだぶる。さらに、小泉政権時代に、道路公団の民営化で無駄を徹底的に追及した行動力と改革力は記憶に新しい。そして、今回の選挙では、勝利したにもかかわらず、あえて万歳はせず、「東京は日本の心臓。東京から日本を変える」「東京が日本沈没を防がないといけない」など、官僚や国の規制に立ち向かう姿勢を強調した。前例の踏襲を嫌うタイプという。
猪瀬氏のキャラクターが面白い。国にものを言う前職の石原慎太郎氏とイメージがだぶる。さらに、小泉政権時代に、道路公団の民営化で無駄を徹底的に追及した行動力と改革力は記憶に新しい。そして、今回の選挙では、勝利したにもかかわらず、あえて万歳はせず、「東京は日本の心臓。東京から日本を変える」「東京が日本沈没を防がないといけない」など、官僚や国の規制に立ち向かう姿勢を強調した。前例の踏襲を嫌うタイプという。 その理由のいくつかを考えてみる。民主が分裂したこと。さらに、政党の離合集散で12政党が候補者を出し、まさに多党乱立。前回の「政権選択」といった明確な選挙の構図に比べ、争点が分かりにくかったことだろう。
その理由のいくつかを考えてみる。民主が分裂したこと。さらに、政党の離合集散で12政党が候補者を出し、まさに多党乱立。前回の「政権選択」といった明確な選挙の構図に比べ、争点が分かりにくかったことだろう。 昨日、北朝鮮が弾道ミサイルの技術を使って、自前の運搬手段で人工衛星を打ち上げた世界10番目の国になったと報じられた。最初に打ち上げたのはソビエト(当時、1957年)で、韓国も人工衛星を打ち上げているが、自前のものではなく、ランキング上では北朝鮮に抜かれた格好だ。
昨日、北朝鮮が弾道ミサイルの技術を使って、自前の運搬手段で人工衛星を打ち上げた世界10番目の国になったと報じられた。最初に打ち上げたのはソビエト(当時、1957年)で、韓国も人工衛星を打ち上げているが、自前のものではなく、ランキング上では北朝鮮に抜かれた格好だ。 昨夜のテレビ報道を見ていると、脱原発世論の高まりを背景に「今のままだと選ぶ政党がない」「党、または個人で手を挙げてくれる人に『この指止まれ』方式で呼びかけたい」と新党設立を理由を説明した。その、基本的な政策は「全原発廃炉の道筋をつくる『卒原発』」「消費税を増税する前に徹底的した行政の無駄を排除する『脱増税』「地域中心の行政を実現する『脱官僚』」を柱とすると述べた。ただ、嘉田氏自身は代表を務めるが総選挙には立候補せず、知事は続投する。あくまでも関西1200万人の水がめである琵琶湖の「守護人」との立場を崩さない。
昨夜のテレビ報道を見ていると、脱原発世論の高まりを背景に「今のままだと選ぶ政党がない」「党、または個人で手を挙げてくれる人に『この指止まれ』方式で呼びかけたい」と新党設立を理由を説明した。その、基本的な政策は「全原発廃炉の道筋をつくる『卒原発』」「消費税を増税する前に徹底的した行政の無駄を排除する『脱増税』「地域中心の行政を実現する『脱官僚』」を柱とすると述べた。ただ、嘉田氏自身は代表を務めるが総選挙には立候補せず、知事は続投する。あくまでも関西1200万人の水がめである琵琶湖の「守護人」との立場を崩さない。 今朝7時35分ごろ、金沢市内の平野部で霰(あられ)が降った=写真=。自宅近くでも1分間ほど降り、登校の子どもたちが騒ぎながら小走りで学校へと急いだ。きょうの朝刊も騒がしい。「卒原発」を掲げる滋賀県の嘉田由紀子知事が、新党結成に動き出したことでもちきりだ。きょう27日午後、記者会見するという。
今朝7時35分ごろ、金沢市内の平野部で霰(あられ)が降った=写真=。自宅近くでも1分間ほど降り、登校の子どもたちが騒ぎながら小走りで学校へと急いだ。きょうの朝刊も騒がしい。「卒原発」を掲げる滋賀県の嘉田由紀子知事が、新党結成に動き出したことでもちきりだ。きょう27日午後、記者会見するという。
 市長が「大分裂」と言ったのは、決議支持率が低迷する中の解散・総選挙では民主の苦戦が必至で、すでに同党の一部議員による新党結成や、有力議員の日本維新の会への合流など離党の動きが出ている。そこで、13日の民主党常任幹事会で「党の総意」として年内解散に反対する方針で合意していた。にもかかわらず、野田総理は党の分裂を覚悟で、「16日解散」を表明したのである。市長の読みは的中したことになる。
市長が「大分裂」と言ったのは、決議支持率が低迷する中の解散・総選挙では民主の苦戦が必至で、すでに同党の一部議員による新党結成や、有力議員の日本維新の会への合流など離党の動きが出ている。そこで、13日の民主党常任幹事会で「党の総意」として年内解散に反対する方針で合意していた。にもかかわらず、野田総理は党の分裂を覚悟で、「16日解散」を表明したのである。市長の読みは的中したことになる。