★能登の風景を変える人々
先月9日、水戸市に出かけた。平成24年度「地域づくり総務大臣表彰」を受けるためだ。金沢大学が能登半島の先端で展開する「能登里山マイスター」養成プログラム運営委員会(代表:中村浩二教授)が授賞したのだ。中村教授に随行者として同行した。このブログでも何度となく紹介したが、「地域づくりは人づくり」、この地道な5年間のプログラムを振り返ってみる。
 日本海に突き出た能登半島に金沢大学の能登学舎(石川県珠洲市)がある。しかも、地元の人たちが「サザエの尻尾の先」と呼ぶ、半島の先端である。ここに廃校となっていた小学校施設を市から無償で借り受けて、平成18年から研究交流拠点として活用している。学舎の窓からは、日によって海の向こうに立山連峰のパノラマが展開する。この絶好のロケーションで、環境に配慮した農林漁業をテーマに社会人のための人材育成が行われている。
日本海に突き出た能登半島に金沢大学の能登学舎(石川県珠洲市)がある。しかも、地元の人たちが「サザエの尻尾の先」と呼ぶ、半島の先端である。ここに廃校となっていた小学校施設を市から無償で借り受けて、平成18年から研究交流拠点として活用している。学舎の窓からは、日によって海の向こうに立山連峰のパノラマが展開する。この絶好のロケーションで、環境に配慮した農林漁業をテーマに社会人のための人材育成が行われている。
能登半島は過疎・高齢化が進み、耕作放棄地も目立っている。追い討ちをかけるように、平成19年3月25日、能登半島地震(震度6強)が起き、2000棟もの家屋が全半壊した。能登の地域再生は待ったなしとなった。震災の発生する2月前に文部科学省科学技術振興調整費(当時)のプログラム「地域再生人材創出拠点の形成」に「能登里山マイスター」養成プログラムを申請していた。5月に正式採択されたが、喜びよりもミッション遂行の責任の重さがずっしりと肩にのしかかってきたとの思いだった。石川県が仲介役となって、金沢大学と石川県立大学、そして奥能登にある2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の6者が「地域づくり連携協定」を結び、同年10月に開講にこぎつけた。連携する自治体は、広報やケーブルテレビを通じて受講生の募集業務やプログラムを受講する職員の推薦、移住してくる受講生の窓口の役割を担ってもらった。実際、このプログラムを受講した移住組は14人に上った。
能登の地域再生を目指す人材像を3タイプに分けて、毎週土曜に講義と演・実習を2年間受講する形式を取った。その3つのタイプとは、「環境に配慮した農林漁業人材」、「付加価値をつけ流通させるビジネス人材」、「地域リーダー人材」である。事業の最大の成果は、修了生62人(45歳以下)のうち52人が奥能登に定着し(定着率84%)、能登を活性化する多様な取り組みの中心として活躍していることである。たとえば、農林漁業人材では、水産加工会社社員(男性)が同社の新規農業参入(耕作面積26㌶)の中心的役割を果たし、地域の耕作放棄地を減少させている。製炭業職人(男性)は高付加価値の茶道用の高級炭の産地化に向けて、地域住民らともに荒廃した山地に広葉樹の植林運動を毎年実施している。この男性は平成22年度の地域づくり総務大臣表彰で個人表彰を受けた。
定着率が高いのは、2年間のカリキュラムを通して、受講生同士の情報交換や仲間意識といったネットワークづくりが奏功したのだと分析している。また、追い風もある。平成23年6月、国連食糧農業機関(FAO)から「能登の里山里海」と「トキと共生する佐渡の里山」が世界農業遺産(GIAHS)に認定され、持続可能型社会のモデルとして国内外で注目され始めている。5年間で終了した「能登里山マイスター」養成プログラムの後継事業として、平成24年10月から能登「里山里海マイスター」育成プログラムが大学と自治体の出資でリニューアルスタートとした。受講生は40人余り。東京から通いで学んでいる女性たちもいる。マイスター修了生の活動の輪がさらに広がり、近い将来、能登の風景を明るく変えてくれるに違いない、と楽しみにしている。
※写真は、農産物の販売実習の風景
⇒12日(火)夜・金沢の天気 はれ
 8日に能登半島の七尾市に所要で出かけた。金沢もそうだったが、どんよりと空がかすんでいた。一時雨が降ったが、雨が上がってもどんよりとした土色のかすみが空を覆い、晴れ上がることはなかった=写真=。黄砂がやってきた、と直感した。毎年この季節はかすむのである。ただ、ことしの黄砂は目と鼻に刺激が強いのだ。
8日に能登半島の七尾市に所要で出かけた。金沢もそうだったが、どんよりと空がかすんでいた。一時雨が降ったが、雨が上がってもどんよりとした土色のかすみが空を覆い、晴れ上がることはなかった=写真=。黄砂がやってきた、と直感した。毎年この季節はかすむのである。ただ、ことしの黄砂は目と鼻に刺激が強いのだ。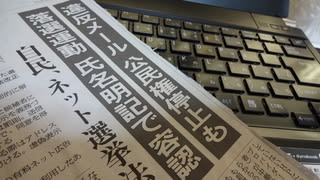 インターネットの活用を選挙で解禁するにあたり、ネックとなっていたのは、現行の公職選挙法は、公示・告示後の選挙期間中は、法律で定められたビラやはがきなどを除き、「文書図画(とが)」を不特定多数に配布することを禁じていたからである。候補者のホームページやツイッターなどソーシャルメディアの発信は、こうした文書図画に相当し、現行では認められていないのだ。
インターネットの活用を選挙で解禁するにあたり、ネックとなっていたのは、現行の公職選挙法は、公示・告示後の選挙期間中は、法律で定められたビラやはがきなどを除き、「文書図画(とが)」を不特定多数に配布することを禁じていたからである。候補者のホームページやツイッターなどソーシャルメディアの発信は、こうした文書図画に相当し、現行では認められていないのだ。 これに関して、現地で共同通信の記者のインタビューを受けた井上氏は「政治的に解決できないことが(両国間で)あるとしたら、僕らみたいなのが穴をあけ、互いの疎通を図ることが必要だ」「第九は平和を望む内容の曲。(演目として)僕から持ちかけ(北朝鮮側が)すんなり乗ってくれた」「音楽だけでなく、できることがある人は何とかつながりを持ち、この国にいろいろな情報を入れてあげないといけない」と話した(8日付・北陸中日新聞)。
これに関して、現地で共同通信の記者のインタビューを受けた井上氏は「政治的に解決できないことが(両国間で)あるとしたら、僕らみたいなのが穴をあけ、互いの疎通を図ることが必要だ」「第九は平和を望む内容の曲。(演目として)僕から持ちかけ(北朝鮮側が)すんなり乗ってくれた」「音楽だけでなく、できることがある人は何とかつながりを持ち、この国にいろいろな情報を入れてあげないといけない」と話した(8日付・北陸中日新聞)。 鈴木教授の専門は放射線病理、放射線疫学。最初に「低線量遷延被ばく、内部被ばくの健康リスクとどう付き合うか」と題して話した。「遷延被ばく」とは、福島第一原発の事故のように、環境中にばらまかれた放射性降下物からのゆっくりとした被ばくのこと。「内部被ばく」は放射性物質が含まれている飲み物や食べ物、空気体内に摂取したり吸ったりすることで起きる被ばくのこと。鈴木教授は、放射線リスクは「ある」「ない」で論じられるが、この世にゼロリスクはない。「リスクは低ければ低いほどよい」と一般的に認識されるているが、低めるに当たり失うものを考慮しないと、誤った価値判断に陥る。「低線量被ばく、内部被ばくは、急性被ばく(たとえば原爆による被ばく)よりリスクが何百倍も高い」との話が広まっているが、これを裏付ける疫学的なデータはない、と述べた。以上の点から、専門家としては「安全のお墨付き」というものを与えることはできないが、放射線リスクの「値ごろ感」というものを伝えることができる。そのために、「個々人、あるいは地域のみなさんに『受容レベル』を価値判断するための材料を提供できる」と慎重な言い回しで語った。
鈴木教授の専門は放射線病理、放射線疫学。最初に「低線量遷延被ばく、内部被ばくの健康リスクとどう付き合うか」と題して話した。「遷延被ばく」とは、福島第一原発の事故のように、環境中にばらまかれた放射性降下物からのゆっくりとした被ばくのこと。「内部被ばく」は放射性物質が含まれている飲み物や食べ物、空気体内に摂取したり吸ったりすることで起きる被ばくのこと。鈴木教授は、放射線リスクは「ある」「ない」で論じられるが、この世にゼロリスクはない。「リスクは低ければ低いほどよい」と一般的に認識されるているが、低めるに当たり失うものを考慮しないと、誤った価値判断に陥る。「低線量被ばく、内部被ばくは、急性被ばく(たとえば原爆による被ばく)よりリスクが何百倍も高い」との話が広まっているが、これを裏付ける疫学的なデータはない、と述べた。以上の点から、専門家としては「安全のお墨付き」というものを与えることはできないが、放射線リスクの「値ごろ感」というものを伝えることができる。そのために、「個々人、あるいは地域のみなさんに『受容レベル』を価値判断するための材料を提供できる」と慎重な言い回しで語った。 この地震速報の前後でパネルディカッションが熱気を帯びていた。そのキーワードは「徐前の費用対効果」だった。飯館村村長の菅野典雄氏は、放射能で汚染された土壌の改良、つまり除染に関しては、国家プロジェクトでやってほしいと述べた。つまり、避難している村民が戻ってきて、仕事や生活ができるような環境は、除染が大前提である、と。費用3200億円(20年間)をかけて除染を急いでいる。「放射能とは長い戦いになる。しかし、除染をすれば数値は下がる。これ(除染)をやらなければ避難している村民に戻ろうと言えない」、「それを『費用対効果』で語る政治家がいるのは残念だ」と述べた。
この地震速報の前後でパネルディカッションが熱気を帯びていた。そのキーワードは「徐前の費用対効果」だった。飯館村村長の菅野典雄氏は、放射能で汚染された土壌の改良、つまり除染に関しては、国家プロジェクトでやってほしいと述べた。つまり、避難している村民が戻ってきて、仕事や生活ができるような環境は、除染が大前提である、と。費用3200億円(20年間)をかけて除染を急いでいる。「放射能とは長い戦いになる。しかし、除染をすれば数値は下がる。これ(除染)をやらなければ避難している村民に戻ろうと言えない」、「それを『費用対効果』で語る政治家がいるのは残念だ」と述べた。 福島市に来ている。積雪はJR福島駅周辺で25㌢ほどだろうか=写真=。新聞やテレビのニュースを見ていると、地吹雪や視界不良で磐越自動車道が一時交通止めになったり、山形新幹線が一時立ち往生、南会津町でスキー大会が中止、きょう25日の国公立大学2次試験で会津大学の試験時間を2時間繰り下げたと報じている。
福島市に来ている。積雪はJR福島駅周辺で25㌢ほどだろうか=写真=。新聞やテレビのニュースを見ていると、地吹雪や視界不良で磐越自動車道が一時交通止めになったり、山形新幹線が一時立ち往生、南会津町でスキー大会が中止、きょう25日の国公立大学2次試験で会津大学の試験時間を2時間繰り下げたと報じている。
 大友さんによると、室町期に書かれ、元旦から大晦日までの宮中行事100余を記した『公事根源』に、「延喜11年(911)」の年に「後院より七種を供す」と記述があり、当時すでに宮中で唐土(中国大陸)からの厄病を運ぶ鳥の退散を期する七草の行事が行われていたようだ。この季節の風習は行事は、徳川期に入っても「若菜節句」と称して幕府の年中行事に取り入れられ、諸大名が将軍家へ登城してお祝いを述べ、将軍以下全員が「七種の粥」を食したようだ。次第に諸大名から武家へ、商家へ、庶民へと広まった。ただ、現在では「七種の粥」が一般の家庭で行われている話は見たことも聞いたこともない。食糧自給や予防医学の発展で、人々の健康体が保てるようになったからかもしれない。あるいは、「唐土の鳥」という迷信の正体が黄砂ではないのかと知れ渡るようになったからではないか、とも推察している。
大友さんによると、室町期に書かれ、元旦から大晦日までの宮中行事100余を記した『公事根源』に、「延喜11年(911)」の年に「後院より七種を供す」と記述があり、当時すでに宮中で唐土(中国大陸)からの厄病を運ぶ鳥の退散を期する七草の行事が行われていたようだ。この季節の風習は行事は、徳川期に入っても「若菜節句」と称して幕府の年中行事に取り入れられ、諸大名が将軍家へ登城してお祝いを述べ、将軍以下全員が「七種の粥」を食したようだ。次第に諸大名から武家へ、商家へ、庶民へと広まった。ただ、現在では「七種の粥」が一般の家庭で行われている話は見たことも聞いたこともない。食糧自給や予防医学の発展で、人々の健康体が保てるようになったからかもしれない。あるいは、「唐土の鳥」という迷信の正体が黄砂ではないのかと知れ渡るようになったからではないか、とも推察している。 七草は、大友楼ではセリ(野ぜり)、ナズナ(バチグサ、ペンペン草)、五行=御行(ハハコグサ)、ハコベラ(あきしらげ)、仏の座(オオバコ)、すず菜(蕪)、スズシロ(大根)のこと。これを台所の七つ道具でたたき=写真=、音を立てて病魔をはらう行事で、3代藩主利常の時代から明治期まで行われたという。面白いのは、たたくときの掛け声だ。「ナンナン、、七草、なずな、唐土の鳥が日本の土地に渡らぬ先にかち合せてボートボトノー」と。つまり、旧暦正月6日の晩から7日の朝にかけて唐の国(中国)から海を渡って日本へ悪い病気の種を抱えた鳥が飛んで来て、空から悪疫のもとを降らすというので、この鳥が我家の上に来ない様にとの願いが込められている。「平安時代からの行事とされる」と、藩主の御膳所を代々勤めた大友家の7代目の大友佐俊さんは言う。
七草は、大友楼ではセリ(野ぜり)、ナズナ(バチグサ、ペンペン草)、五行=御行(ハハコグサ)、ハコベラ(あきしらげ)、仏の座(オオバコ)、すず菜(蕪)、スズシロ(大根)のこと。これを台所の七つ道具でたたき=写真=、音を立てて病魔をはらう行事で、3代藩主利常の時代から明治期まで行われたという。面白いのは、たたくときの掛け声だ。「ナンナン、、七草、なずな、唐土の鳥が日本の土地に渡らぬ先にかち合せてボートボトノー」と。つまり、旧暦正月6日の晩から7日の朝にかけて唐の国(中国)から海を渡って日本へ悪い病気の種を抱えた鳥が飛んで来て、空から悪疫のもとを降らすというので、この鳥が我家の上に来ない様にとの願いが込められている。「平安時代からの行事とされる」と、藩主の御膳所を代々勤めた大友家の7代目の大友佐俊さんは言う。 前年(2011)に比べNHKは4.2点、新聞3.1点、民放テレビは3.5点それぞれ下げたことになる。新聞、テレビ、ラジオ、インターネットの情報信頼度が、いずれも調査を始めた2008年以来最低となった。気になるのはメディアとしてのインターネットは53.3点取っている。ラジオは58.6点なので、その差は5点。民放テレビとも7点差だ。年代別の結果で、20代、30代ではインターネットとラジオ・テレビの差がさらに縮まる。これは、テレビ・ラジオの経営者としてはショックだろう。「信頼度がインターネットとそれほど変わらないのであれば、われわれの存在価値はどこにあるのか」などと自問せざるを得ない。
前年(2011)に比べNHKは4.2点、新聞3.1点、民放テレビは3.5点それぞれ下げたことになる。新聞、テレビ、ラジオ、インターネットの情報信頼度が、いずれも調査を始めた2008年以来最低となった。気になるのはメディアとしてのインターネットは53.3点取っている。ラジオは58.6点なので、その差は5点。民放テレビとも7点差だ。年代別の結果で、20代、30代ではインターネットとラジオ・テレビの差がさらに縮まる。これは、テレビ・ラジオの経営者としてはショックだろう。「信頼度がインターネットとそれほど変わらないのであれば、われわれの存在価値はどこにあるのか」などと自問せざるを得ない。