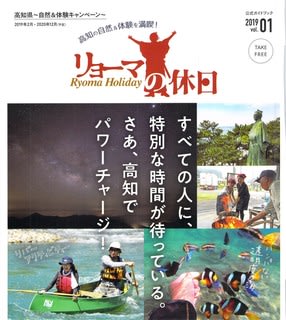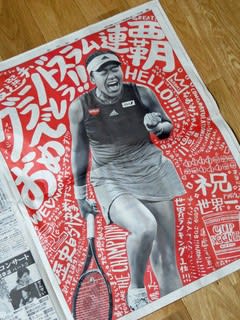けさ3日の各紙は共同通信が1日と2日に実施した緊急世論調査(電話)の結果を報じている。新元号については73%が「好感が持てる」と答え、「好感が持てない」は15%だった。好感が持てると答えた理由は「新時代にふさわしい」35%、「耳で聞いて響きがよい」35%、「伝統を感じさせる」28%だった。逆に好感が持てない理由は「使われている漢字がよくない」42%、「耳で聞いて響きがよくない」38%だった。(※写真は総理官邸ホームページより)
 世論調査の結果は、周囲の反応と同じだ。「語感がスマートでいいね」「万葉集からの出典が新しさを感じさせる」という知人が多い中で、「令という文字が命令を連想して気にくわない」と顔をしかめた人もいた。
世論調査の結果は、周囲の反応と同じだ。「語感がスマートでいいね」「万葉集からの出典が新しさを感じさせる」という知人が多い中で、「令という文字が命令を連想して気にくわない」と顔をしかめた人もいた。
1989年1月に小渕官房長官が「平成」を発表したとき、「薄っぺらい文字だ」との印象だった。その後、『史記』にある「内平外成」(内平かに外成る)の言葉を知り、国内が平和であってこそ、他国との関係も成立するという意味だと理解した。軍部の台頭から大戦を招いた昭和の経験を平成の世に活かそうという意義が二文字に込められているとも教えられ、大いに納得したものだ。
それにしても新元号の発表によって、内閣支持率が前月から9ポイント伸びて52%、不支持率は8ポイント減り32%となった。一過性の数字かもしれないが、それだけ新元号の評価が高かった、ということだろう。
ところが、海外メディアの反応をリサーチすると、「the new Japanese Era」「REIWA」を伝えているが、全般に「冷たい」との印象だ。イギリス「BBCテレビ」Webニュースでは、Japan has announced that the name of its new imperial era, set to begin on 1 May, will be “Reiwa” – signifying order and harmony.(日本は5月1日に始まる新しい天皇の時代の名称が「レイワ」になると発表、これは秩序と調和を意味する)と、令をorderとあて、淡々と伝えている。
1日付のアメリカ「ニューヨークタイムズ」には首を傾げた。見出しでJapan’s New Era Gets a Name, but No One Can Agree What It Means(日本の新時代の名称は決まったが、誰もそれが意味するものに同意できない)。Agreeは単に「意味が分かりにくい」という解釈かと思ったがそうではなかった。政治的な意味合いだった。
記事では、Naruhito’s reign will be called Reiwa, a term with multiple meanings, including “order and peace,” “auspicious harmony” and “joyful harmony,” according to scholars quoted in the local news media.(日本の報道によると、ナルヒトの治世は「レイワ」と呼ばれ、「秩序と平和」「縁起の良い調和」「喜びの調和」などさまざまな意味がある)と述べている。
その後の記事で、Some commentators noted that Mr. Abe’s cabinet, which is right-leaning and has advocated an expanded military role for Japan, chose a name containing a character that can mean “order” or “law”.(一部の評論家は、右寄りの安倍内閣は軍事的役割を拡大することを主張しているが、「秩序」または「法」を意味する文字を含む名前を選んだ、と述べた)と。全体の文脈は、安倍内閣は軍国化を進めるために、 “order” or “law”を意味する「令」という文字を込めており、この政治的に意図された元号に国民は同意していない、となる。
この記事を読むと、日本人の感覚と随分とずれていると感じる。それでは、同意していない国民の世論の73%が新元号に好感を持つと答えた理由をニューヨークタイムズの記者にぜひ分析してほしいものだ。
⇒3日(水)夜・金沢の天気 くもり
 金沢大学の能登で実施している人材育成プログラム「能登里山里海マイスター」の修了生で、工芸作家の岩崎京子さんから加賀ゆびぬきの魅力について取材した。かつては加賀友禅をつくる仕立て人のお針子さんたちが自分たちの指にはめるために指ぬきをつくった。それも、友禅の作成過程で余った絹糸や布、真綿などをためておき、自分の好みの指ぬきを創作したという。岩崎さんの指ぬきは能登の植物を染色に生かす。廃材となった漆の木材チップや能登ヒバ「アテ」の葉、クルミの皮、海藻のホンダワラなどで絹糸を染める。漆の染め物は黒色や黄金色が鮮やかで高級感が漂う。「能登の自然を色という視点から見つめ直して、能登の自然を物語にしてみたんです」と。確かに指ぬきをじっと見ているとその色の背景にある里山里海の風景が浮かんでくる。
金沢大学の能登で実施している人材育成プログラム「能登里山里海マイスター」の修了生で、工芸作家の岩崎京子さんから加賀ゆびぬきの魅力について取材した。かつては加賀友禅をつくる仕立て人のお針子さんたちが自分たちの指にはめるために指ぬきをつくった。それも、友禅の作成過程で余った絹糸や布、真綿などをためておき、自分の好みの指ぬきを創作したという。岩崎さんの指ぬきは能登の植物を染色に生かす。廃材となった漆の木材チップや能登ヒバ「アテ」の葉、クルミの皮、海藻のホンダワラなどで絹糸を染める。漆の染め物は黒色や黄金色が鮮やかで高級感が漂う。「能登の自然を色という視点から見つめ直して、能登の自然を物語にしてみたんです」と。確かに指ぬきをじっと見ているとその色の背景にある里山里海の風景が浮かんでくる。