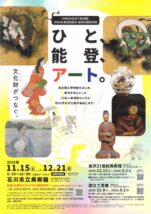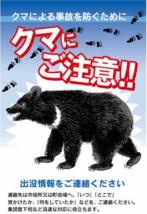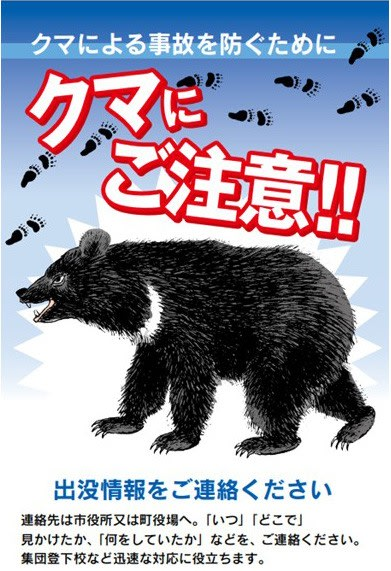☆トキ放鳥は6月に続き9月も 能登各地で「トキよ来い」と取り組み
今月4日付のブログ「国の特別天然記念物トキ 能登での放鳥まであと6ヵ月」の続き。石川県の馳知事は先日5日の年頭記者会見で能登で実施される国の特別天然記念物トキの放鳥について、予定している6月に加え、9月にも実施することを明らかにした。環境省の決定を受け、馳知事が報告した。9月の放鳥場所はまだ未定のようだ。地元メディア各社が報じている。

能登での1回目の放鳥は6月上旬ごろに羽咋市南潟地区(邑知潟周辺)で実施される。知事の説明によると放鳥式を同市の余喜グラウンドゴルフ場で実施しする。皇族を招く予定で交渉中のようだ。放鳥を予定しているトキは佐渡市で順化訓練を受けた個体で、15羽から20羽を予定している。9月に放鳥予定のトキは5羽から10羽で、場所や方法については、国や専門家からの助言を受け、県や能登の市町、JAなど関係団体でつくる「能登地域トキ放鳥受入推進協議会」で決めていくようだ。(※写真は、輪島市三井町洲衛の空を舞うトキ=1957年、岩田秀男氏撮影)
トキの放鳥をめぐって地域の人たちのいろいろな取り組みが動き出している。奥能登に位置する穴水町は、「本州で最後の一羽」と呼ばれたオスの「能里(のり)」が1970年に捕獲された場所だ。穴水町では、トキ復活を心待ちにする人たちが「能登トキファンクラブ」を設立し、エサ場になる池を自分たちで掘って環境整備や生き物の生息調査を行っている。
輪島の白米千枚田でも新たな取り組みが始まっている。棚田を耕す愛耕会では、去年から農法を除草剤などの農薬を使わない無農薬栽培に切り替えた。6月にトキが放鳥されることを意識した取り組みで、トキのエサとなるドジョウやメダカなどが繁殖する田んぼづくりくりに転換した。除草剤などの農薬を使わないとなると草取りなどに手間ひまがかかるのは言うまでもない。コメの収穫量も減るだろう。それでもトキが訪れる棚田にしたいという想いが募っているようだ。コメの収穫量が減ることになったとしても、千枚田の無農薬米が市場に出回れば、「千枚田のトキ米」として一気にブランド化するのではないだろうか。
本州最後の野生のトキが棲息していた能登では、トキはドゥと呼ばれれていた。水田に植えた苗を踏み荒らす「害鳥」とされ、ドゥとは「ドゥ、ドゥと追っ払う」という意味である。昭和30年代、地元の小学校の校長らがこれは国際保護鳥で、国指定の特別天然記念物のトキだと周囲に教え、仲間を募って保護活動を始めた。それでも能登ではトキは減っていった。時代は流れ、いまは逆にトキが舞い降りる田んぼにしようと各地で工夫を凝らす動きが出ている。トキの放鳥は、トキと共に能登半島が元気になっていくスタート地点なのかも知れない。
⇒8日(木)午前・金沢の天気 あめ