☆「山一つ」「海二つ」曳山の醍醐味-上
この季節、能登でよく使われる言葉がある。「盆や正月に帰らんでいい。祭りには帰っておいで」と。これは古里を離れて都会などで暮らす子どもたちに対して親が使う。この言葉には2つの意味があると土地の人たちから教わった。能登の夏祭りや秋祭りでは「キリコ」と呼ぶ高さ10㍍ほどの奉灯(ほうとう)や、曳山(ひきやま)を動かす。祭りは地域や集落ごとに執り行われ、それぞれの家では親戚などを招いてご馳走でもてなすヨバレがある。年に一度の「我が家のビックイベント」でもあるので、子どもたちにも参加を呼びかける。
粋な能登の祭り「黒島天領祭」に学生と行く
もう一つの意味がキリコや曳山を動かす担ぎ手としての役割である。担ぎ手は1軒ごとに2人、あるいは3人と割り当てがある。かつては大家族だったので担ぎ手には不自由しなかったろう。今では能登でも核家族化が進み、さらに少子化でどこの地域や集落でも若い担ぎ手が不足している。この「盆や正月に帰らんでいい。祭りには帰っておいで」は親の願いであり、地域の願いでもあるのだ。
 輪島市門前町黒島の祭礼「黒島天領祭」(17、18日)に学生43人を連れて参加した。かつて北前船船主が集住した黒島は貞享元年(1684)に江戸幕府の天領(直轄地)となり、立葵(たちあおい)の紋が贈られたことを祝って始まった祭礼とされる。祭りはキリコを担ぐ能登のほかの祭りとは異なり、都(みやこ)風な趣がある。2基の曳山は輪島塗に金箔銀箔を貼りつけた豪華さ、「百貫」(375㌔㌘)の神輿(みこし)、小学生による奴(やっこ)振り道中など。地元の人たちは麻の黒い半纏(はんてん)を粋に羽織っている。
輪島市門前町黒島の祭礼「黒島天領祭」(17、18日)に学生43人を連れて参加した。かつて北前船船主が集住した黒島は貞享元年(1684)に江戸幕府の天領(直轄地)となり、立葵(たちあおい)の紋が贈られたことを祝って始まった祭礼とされる。祭りはキリコを担ぐ能登のほかの祭りとは異なり、都(みやこ)風な趣がある。2基の曳山は輪島塗に金箔銀箔を貼りつけた豪華さ、「百貫」(375㌔㌘)の神輿(みこし)、小学生による奴(やっこ)振り道中など。地元の人たちは麻の黒い半纏(はんてん)を粋に羽織っている。
2011年から黒島天領祭にかかわってる。きっけは2007年3月の能登半島地震だった。奥能登を中心に家屋が多く損壊し、過疎化に拍車がかかった。11年3月に奥能登の2市2町(輪島、珠洲、穴水、能登)と大学(金沢大、県立大学、看護大、星稜大)で構成する能登キャンパス構想推進協議会を発足させ、事業テーマの一つとして学生たちが能登の祭りを支援すると同時に祭りを通じて能登の歴史文化を学ぶことを掲げた。すると、黒島の祭礼実行委員会から真っ先に「学生のチカラを借りたい」とSOSの手が上がった。それ以来のかかわりとなった。
⇒18日(土)夜・金沢の天気 はれ
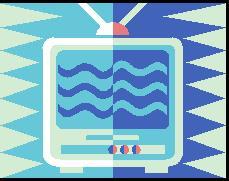

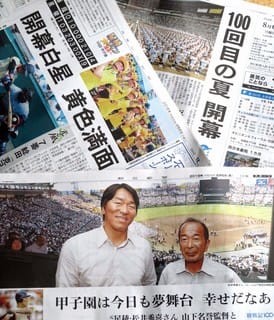


 留学生は以前、兼六園を散策に行き、そのときインバウンド観光客の団体を案内していた日本人のガイドが「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と言っていたのを聞いて、「加賀百万石」のことかとガイドの案内に耳をそばだて納得したようだ。そのとき、ガイドは金沢城の石垣を指さして説明していたので、とても腑に落ちたという。「百万個もの石を使って、お城を造り、そして金沢に用水をはりめぐらせた加賀のお殿様はとても有能な方だったのですね」と留学生。
留学生は以前、兼六園を散策に行き、そのときインバウンド観光客の団体を案内していた日本人のガイドが「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と言っていたのを聞いて、「加賀百万石」のことかとガイドの案内に耳をそばだて納得したようだ。そのとき、ガイドは金沢城の石垣を指さして説明していたので、とても腑に落ちたという。「百万個もの石を使って、お城を造り、そして金沢に用水をはりめぐらせた加賀のお殿様はとても有能な方だったのですね」と留学生。 が推測しにくいパスワード設定をする ■ブラウザでTwitterなどのサービスにアクセスする際に、パスワードを覚えさせない設定にする
が推測しにくいパスワード設定をする ■ブラウザでTwitterなどのサービスにアクセスする際に、パスワードを覚えさせない設定にする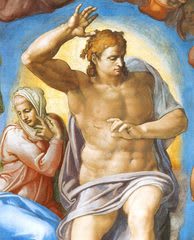 今は売り手市場の時代なので、ある意味で「学生のわがまま」と言ってしまえば、そうなのかもしれないが、学生の志向は確実に「ナンバーワン」から「オンリーワン」へとシフトしているのではないかと直感している。先日も生態系を学ぶ学生と話をしていると具体的な企業名が話題となった。大量に廃棄される残さを乾燥・炭化処理するバイオマス炭化プラントを製造する「明和工業」という金沢市の企業だった。
今は売り手市場の時代なので、ある意味で「学生のわがまま」と言ってしまえば、そうなのかもしれないが、学生の志向は確実に「ナンバーワン」から「オンリーワン」へとシフトしているのではないかと直感している。先日も生態系を学ぶ学生と話をしていると具体的な企業名が話題となった。大量に廃棄される残さを乾燥・炭化処理するバイオマス炭化プラントを製造する「明和工業」という金沢市の企業だった。 「そうですね。私は金沢大学で地域連携コーディネーターという役割を担って12年目になります。この石川という地域を一つの価値ある研究フィールド、あるいは教育フィールドとしてとらえ、地域を活用して大学の研究力、教育力を伸ばしていく、そして、それを地域にお返ししていくことで地域の解題解決をはかる、あるいは新たな産業を興す技術を提供する。そのようなことが大学の使命、ミッションだと考えています」と。
「そうですね。私は金沢大学で地域連携コーディネーターという役割を担って12年目になります。この石川という地域を一つの価値ある研究フィールド、あるいは教育フィールドとしてとらえ、地域を活用して大学の研究力、教育力を伸ばしていく、そして、それを地域にお返ししていくことで地域の解題解決をはかる、あるいは新たな産業を興す技術を提供する。そのようなことが大学の使命、ミッションだと考えています」と。