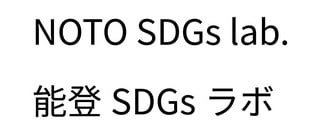★地域課題のキーワード「継業」と「就域」
きのう(2日)金沢大学能登学舎(石川県珠洲市)で人材養成プロジェクト「能登里山里海マイスター育成プログラム」の卒業課題研究の報告会があった。審査員を依頼され、受講生の発表を終日聞くことができた。受講生は1年間の研究成果を発表12分・質疑8分で発表し審査を受ける。主査、副査、外部評価員の3人が(1)着眼点・問題設定力、(2)論理性・説得力、(3)具体性・実現可能性、(4)プレゼンテーション力(発表のわかりやすさ)、(5)質疑に対する対応力、(6)地域振興における意義の6つ評価項目でチェックをする。
能登里山里海マイスター育成プログラムは45歳以下の社会人が講義、実習、先進地視察、課題研究に取り組む。ことしは農業者や行政職、地域おこし協力隊、工芸家、鍛冶師、建築家、JICAスタッフなど多彩な人材がそろう。1年かけて自己実現に向けて理論構築、実施プランを発表する。それが近い将来、職場や地域における働き方、新商品開発のイノベーション、創業・起業へとつながっていく。ことし12年目、これまで165人のマイスター修了生を輩出している。昨年2月には、実績が 評価され、国が後援する「イノベーションネットアワード2018」において最高賞の文部科学大臣賞を受賞した。
評価され、国が後援する「イノベーションネットアワード2018」において最高賞の文部科学大臣賞を受賞した。
話は卒業課題研究に戻る。報告会では、時代のトレンドを読む面白い発想や言葉が飛び出した。いくつか紹介する。自治体の移住コーディネーターとして移住・定住の窓口業務を担っている男性(地域おこし協力隊メンバー)の発表だ。彼は82世帯136人の移住者を担当し、「継業(けいぎょう)」を勧めている。事業継承は身内が生業や事業を引き継ぐことを指すが、継業は第三者(移住者・町民)が継ぐことをいう。「身内が引き継いでくれた方が安心であることは承知の上で、後継者がいなければ、第三者による新たな視点で事業を発展させてくれる可能性があれば継業を経営者に提案していきたい」と熱く語った。
もう一つ、「就域(しゅういき)」。学生や若者の就職支援センター「ジョブカフェ石川」に勤務する女性が発した言葉だ。地域の中小企業と行政、金融機関などが連携して、地域ぐるみで若者を定着を支援する取り組みのことを意味する。これまで、同じ地域にいても利害が異なるため採用競合の状態だったが、地域振興を図るという共通の目的のために地域ぐるみで採用に取り組む。石川県の求人倍率は1.96倍と人出不足が慢性化し、北陸新幹線による「ストロー現象」も顕在化している。彼女は「とくに能登には就域が必要です。入ってみないと分からないという学生・若者の不安を解消し、お互いのミスマッチを防ぐことができれば彼らは能登に入ってきますよ」と語った。
「継業」と「就域」、この場で初めて聞いた言葉だが、能登の未来可能性を語る受講生たちの厚い志(こころざし)が伝わってきてた。と同時に、能登をはじめ少子高齢化の地域が課題解決に向きあうキーワードだと察した。
⇒3日(日)夜・金沢の天気 くもり