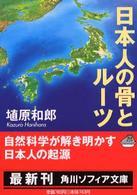★もともと学び舎だった

そこで、きょうはこの古民家の説明を簡単にします。旧白峰村(現・石川県白山市)の地元に伝わる話として、家は記録されているだけで築280年なのですが、それ以前は越前(福井県)にあったそうです。間口14間(25㍍)・奥行き6間(11㍍)、建面積83坪のどっしりとした造り。特に、家に入るとむき出しになった黒光りする棟木に家の風格というものを感じます。かつて養蚕農家だったこの家は3層構造でしたが、大学では2層にし、2階部分を一部吹き抜けにしました。
写真は客間に当たり、さらにこの奥が仏間でした。これらのスペースを大学ではセミナー室などに利用することにし、すでに法学部や経済学部のゼミなどに使われています。この仏間ですが、白峰地方では浄土真宗が盛んで、大きな仏間のことを「道場(どうじょう)」と呼んでいたそうです。ここに人々が集い、仏教を学ぶ拠点としたのです。ですから、この家はもともと学び舎としての「宿命」を背負っていた、と私は思いをめぐらせています。