★モリアオガエルの卵と心臓

昨夜(8日)、金沢大学教授(自然計測応用センター)の中村浩二教授が朝日新聞金沢総局で「里山に学ぶ~金沢大学の実践から~」というテーマで講演しました。以下は要約です。「里山(さとやま)」という言葉は割りと新しく、岩波書店の「広辞苑」で登場したのは1998年の第5版でした。むしろ、「奥山(おくやま)」という言葉の方が古いようです。これは、ひとえに注目度の違いです。奥山は原生的な森であるのに対し、里山はどこにでもある農山村です。ようするに有難味のない風景なのです。その里山が俄然注目を集めたのは、去年、西日本を中心に起きた「クマ騒動」でした。新聞紙面に「里山にクマ出没」「里山になぜクマが」などと見出しが躍りました。里山と奥山の区別がつかないほど里山が荒れ、クマ自身がその領域の見分けがつかず、里山に迷い込んでくるのです。これを人災と見るか、害獣の侵入と理解するかは人間の感性の問題なのかもしれません。
里山がなぜ荒れるのかー。講演会が終了して、講師と聞き手を交えた意見交換がありました。林業として農業として成り立たない、つまり里山に住むことの経済効果が得られない、だから過疎化する、というのは誰もが理解することだと思います。ところが、ヨーロッパ、特にドイツでは「自然療法士」というセラピストがいて、里山をフィールドとした山野草の摘み取りから摂取、森林浴の効果的なノウハウを指導しています。医療分野での里山の利用価値は十分にあるのです。また、子供たちへの教育の場としての里山活用法も紹介されました。
昨夜はサッカー・ワールドカップ・ドイツ大会アジア最終予選「日本VS北朝鮮戦」がバンコクであり、講演と同じ時間帯にテレビ中継(関東地区の視聴率43.4%・ビデオリサーチ調べ)されました。日本がバーレーン戦(6月3日)に勝って、W杯出場の可能性が出た段階で、講演に人は集まるのだろうかと心配していました。ところが、定員50人のセミナールームは満杯でした。こんなに里山に対する関心度が高いのか、と驚いたくらいです。これもクマ騒動が一石を投じてくれたお蔭でしょうか。
⇒9日(木)午後・金沢の天気 晴れ


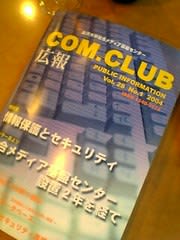

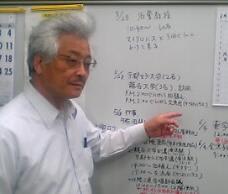

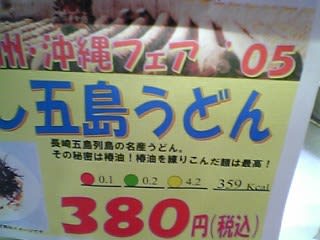

 畑のある風景
畑のある風景


