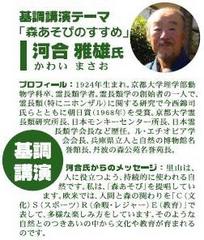☆「漢字&カタカナ」仕事の名刺
私の仕事もカタカナ職業の一つだ。しかも初めに4字の漢字がつき、合わせて12文字にもなる。名刺を交換すると、「地域連携コーディネーターってどのような仕事ですか」とよく問われる。当初、返答に窮した。なにしろ、金沢大学の制度としても新しく、手本となる先輩もいない。手探りの毎日である 。
。
所属する金沢大学社会貢献室には3人の地域連携コーディネーターがいる。私は民間のテレビ局を途中退社した転職組、石川県庁OBで農業関連のスペシャリスト、そして県内の私学の理事が「出向」というかたちで派遣されている。この顔ぶれだけでも国立大学法人としては異色と映るだろう。
では、具体的にどのような活動を行っているのかというと、大学の社会貢献の柱の一つ、「里山プロジェクト」をケースに紹介したい。このプロジェクトは、かつて金沢の里山でもあった角間キャンパス(201㌶)の一部を地域の人たちに開放し、社会教育や子どもたちの活動の場として使ってもらおうという事業だ。これまで650人余りが登録し、自然観察や農業体験、森林や竹林の整備、藍染などと幅広く活動を展開している。これらの活動を総称して「角間の里山自然学校」と呼んでいる。
先日、ひきこもりの子どもたちをサポートしているNPOのスタッフが子どもたちを連れて里山自然学校にやってきた。「活動に参加させてほしい」という。子どもたちはコンピュータに興味があるというので、コンピュータ・グラフィックス(CG)でバッタのジャンプを再現している大学院生に頼んで研究室を案内してもらった。研究室から帰ってきて、寡黙だった子どもたちが少し話すようになっていた。11月初めにあった大学祭では、里山自然学校が出店するドングリを使った工作の店を手伝ってもらった。随分と忙しい思いをしたらしい。
かつて金沢城内にあった金沢大学の教員や学生は旧制四高の時代からの気風を受け継ぎ、地域の人たちとよく交わった。それが平成に入り総合移転した。金沢大学がいち早く社会貢献室を組織して地域の人たちと接点を持とうとしているのは、疎遠になりがちな地域とのよき関係を続けたいとのアピールである。大学に対する地域のニーズは限りない。われわれコーディネーターはその「橋渡し」を担っている。ただしマニュアルはない。
(※今回の「自在コラム」は週刊「教育資料」2005年11月14日号で掲載された記事に一部加筆して転載した)
⇒19日(土)朝・金沢の天気 くもり
 。このシステムにはいろいろな意味が可能性が込められている。
。このシステムにはいろいろな意味が可能性が込められている。