☆続々・奥能登へ早春行
「金沢大学・タウンミーティングin能登」 (3月4日、5日・石川県能登町)では2日目に分科会があり、私は「食文化と地域資源」をテーマにした分科会のコーディネーターの役回りをつとめた。前述の星野さんを始め6人のパネリストの協力をいただいた。その分科会では、 ある一つのテーマで意見が相違した。
ある一つのテーマで意見が相違した。
能登の食文化や食材を使って何をやるのか、である。星野さんは「能登に生きる人たちがその豊かさを自覚し、目が輝くことが大切だ。里山や自然をビジネスで考えるな」との持論を述べる。一方、輪島市の名勝、千枚田の近くで天然塩をつくり、「塩千俵」のブランドで売り出している山下昌展さんは「能登の食材や資源を使って魅力ある地域ブランドを生み出し、それぞれでビジネスモデルをつくり、たくましく能登で生きてこそ」と訴える。
 もう少し説明する。山下さんの塩は東京の代理店のネットワークを通じて、フランス料理で有名な三國清三氏や、京都の茶懐石「辻留」が使うようになった。それがきっかけでネット通販などでも有名商品となっている。奥能登の天然塩をブランド化し、ネット通販で全国に販売するというビジネスモデルをつくり上げた。小泉総理が有名にした「米百俵」をとらえて「塩千俵」をネーミングにし、全国で知られる千枚田の横に製塩所を置くという発想はかなり練り上げられたものだ。
もう少し説明する。山下さんの塩は東京の代理店のネットワークを通じて、フランス料理で有名な三國清三氏や、京都の茶懐石「辻留」が使うようになった。それがきっかけでネット通販などでも有名商品となっている。奥能登の天然塩をブランド化し、ネット通販で全国に販売するというビジネスモデルをつくり上げた。小泉総理が有名にした「米百俵」をとらえて「塩千俵」をネーミングにし、全国で知られる千枚田の横に製塩所を置くという発想はかなり練り上げられたものだ。
星野さんは前回の「続・奥能登へ早春行」で記したように、自分の語りや食文化で能登をアピールしている。能登の魅力を知ってほしい、訪ねてほしいと願っている。人が能登に来て土地の触れて、能登の人の目も輝く。それが能登の活力になるというのだ。
星野さん、山下さんとはまた違った意見を持つある人の意見を聞きたかった。高市範幸さん。山中でそばを打ち、豆腐の燻製を「畑のチーズ」との商品名でネット通販をするほか、ブルーベリーワインや魚しょう油「牡蠣(かき)いしり」などオリジナル商品を持つ。元々、地域振興を指導する村役場の職員だったが、職を辞して自ら実践をしている。分科会ではパネリストとしてお招きしたものの、身内に不幸があり、急きょ深夜にUターン。コーディネーターの私にすればハプニングとなった。後日意見をうかがうことにする。
で、相違する意見はまとまったのかというと、別にまとめようという主旨のタウンミーティングではない。おそらく永遠に続くテーマではある。
⇒8日(水)朝・金沢の天気 くもり
 打ちたて、ゆでたての「三たて」にこだわる。そして「豆腐に旅は禁物」とその日に食する人だけに売る。
打ちたて、ゆでたての「三たて」にこだわる。そして「豆腐に旅は禁物」とその日に食する人だけに売る。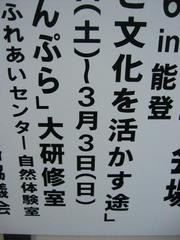 の石川県能登町のホテル「のときんぷら」に着いた。これは能登の方言かと思ってしまうが、県の宿泊施設でかつては能登勤労者プラザと呼ばれていた。地元の人たちが愛称でキンプラと呼んでいたので「のときんぷら」をホテル名にした。ハプニングが起きた。会場入り口のタウンミーティングの看板を女性スタッフが見て大声を上げた。「こりゃダメだ。間違っている」
の石川県能登町のホテル「のときんぷら」に着いた。これは能登の方言かと思ってしまうが、県の宿泊施設でかつては能登勤労者プラザと呼ばれていた。地元の人たちが愛称でキンプラと呼んでいたので「のときんぷら」をホテル名にした。ハプニングが起きた。会場入り口のタウンミーティングの看板を女性スタッフが見て大声を上げた。「こりゃダメだ。間違っている」  顔見知りだったので、こちらから声をかけた。「安田さん、中国が木炭の輸出を禁止しましたが、国内産の炭の価格が上がって、儲かっているんでしょう」と。すると安田さんは「大手の貿易会社は確かに手を引いたが、日本の個人のバイヤーが中国の役人に鼻薬(はなぐすり)を効かせて地方の港からどんどん密輸しているんだよ。だから我々が期待したほど木炭価格は上がっていない。あの国は法律はつくってもザルやな、ガハハハ」と。
顔見知りだったので、こちらから声をかけた。「安田さん、中国が木炭の輸出を禁止しましたが、国内産の炭の価格が上がって、儲かっているんでしょう」と。すると安田さんは「大手の貿易会社は確かに手を引いたが、日本の個人のバイヤーが中国の役人に鼻薬(はなぐすり)を効かせて地方の港からどんどん密輸しているんだよ。だから我々が期待したほど木炭価格は上がっていない。あの国は法律はつくってもザルやな、ガハハハ」と。 の手を止めさせたのではないか。
の手を止めさせたのではないか。 粧に見とれていたのである。
粧に見とれていたのである。 た映画のシーンのように見えたら…(同・下)。まさに幻想の世界である。
た映画のシーンのように見えたら…(同・下)。まさに幻想の世界である。 私のオフィスがある金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」は春めいたとは言え、上の写真でご覧の通り、大屋根にまだ雪を頂いている。
私のオフィスがある金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」は春めいたとは言え、上の写真でご覧の通り、大屋根にまだ雪を頂いている。 るこの頃ではある。
るこの頃ではある。 大雪にあって、雪を楽しむ。これほどぜいたくなことはない。金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」ではきょう27日から「雪だるままつり」が始まった。市民ボランティア「里山メイト」の面々や市民参加で思い思いの雪だるまをつくって楽しむという趣向だ。
大雪にあって、雪を楽しむ。これほどぜいたくなことはない。金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」ではきょう27日から「雪だるままつり」が始まった。市民ボランティア「里山メイト」の面々や市民参加で思い思いの雪だるまをつくって楽しむという趣向だ。 その中で、凝った作品を一つ紹介する。「チョンマゲだるま」とでも名付けたらよいのだろうか、殿様の雪だるまである。これは髷(まげ)を雪で作るのがが難しい。そして顔の表情がとてもユーモラスである。
その中で、凝った作品を一つ紹介する。「チョンマゲだるま」とでも名付けたらよいのだろうか、殿様の雪だるまである。これは髷(まげ)を雪で作るのがが難しい。そして顔の表情がとてもユーモラスである。 ッフは建物の周囲の雪かきでこの一年のスタートを切った。
ッフは建物の周囲の雪かきでこの一年のスタートを切った。 雪のまぶしさを久しぶりに感じた朝だった。雪原の純白さと、空の青さがなんとも言えぬ透明感があった。透明に近いブルーなのだ。この光景が目にしみて涙が出た。
雪のまぶしさを久しぶりに感じた朝だった。雪原の純白さと、空の青さがなんとも言えぬ透明感があった。透明に近いブルーなのだ。この光景が目にしみて涙が出た。 昨夜、深々と雪が降る中、この「角間の里」であるセミナーが開かれた。テーマは「新技術コグニティブ無線とアメリカの取り組み」。端末が自分で空いている周波数帯を探し出して通信を始めることから、ユビキタスネットやブロードバンドで広く応用が期待される「コグニティブ無線」について、電波の規制改革が進むアメリカの実情を知るのがその内容だ。講師は、米FCC(連邦通信委員会)法律顧問のジェームス・ミラー弁護士。冷え込んだ外とは対照的に、古民家の中は随分と参加者の熱気にあふれていた。
昨夜、深々と雪が降る中、この「角間の里」であるセミナーが開かれた。テーマは「新技術コグニティブ無線とアメリカの取り組み」。端末が自分で空いている周波数帯を探し出して通信を始めることから、ユビキタスネットやブロードバンドで広く応用が期待される「コグニティブ無線」について、電波の規制改革が進むアメリカの実情を知るのがその内容だ。講師は、米FCC(連邦通信委員会)法律顧問のジェームス・ミラー弁護士。冷え込んだ外とは対照的に、古民家の中は随分と参加者の熱気にあふれていた。 去年から相次いで起きた身近な山でのクマの出没騒動に端を発して、一体いま山で何が起きているのか不思議でした。でも、よく考えてみれば、山と言えば白山や富士山、ヒマラヤを思い浮かべ、海と言えば沖縄やハワイの海に恋焦がれてきた私たちです。しかし、身近にある海や山には見向きもせず、随分とほったらかしにしてきました。
去年から相次いで起きた身近な山でのクマの出没騒動に端を発して、一体いま山で何が起きているのか不思議でした。でも、よく考えてみれば、山と言えば白山や富士山、ヒマラヤを思い浮かべ、海と言えば沖縄やハワイの海に恋焦がれてきた私たちです。しかし、身近にある海や山には見向きもせず、随分とほったらかしにしてきました。 ア「里山メイト」が自主的に栽培したダイコン畑。雨上がりで土壌が軟らかかったこともあり、ダイコンは意外とすっぽりと抜けた。
ア「里山メイト」が自主的に栽培したダイコン畑。雨上がりで土壌が軟らかかったこともあり、ダイコンは意外とすっぽりと抜けた。 

