☆能登の発酵食文化、現場を訪ねる
 このプロジェクトは、日本の食を支えている発酵・醸造の技術や文化を世界に発信し広めようと、醤油メーカー大手「キッコーマン」(千葉県野田市)のOBらが発起人となって立ち上げた。ツアーには日本糀文化協会のメンバーも参加し、総勢15人。羽田空港から能登空港に降りた一行はバスで能登町、珠洲市、輪島市、七尾市、中能登町を1泊2日で巡った。
このプロジェクトは、日本の食を支えている発酵・醸造の技術や文化を世界に発信し広めようと、醤油メーカー大手「キッコーマン」(千葉県野田市)のOBらが発起人となって立ち上げた。ツアーには日本糀文化協会のメンバーも参加し、総勢15人。羽田空港から能登空港に降りた一行はバスで能登町、珠洲市、輪島市、七尾市、中能登町を1泊2日で巡った。
最初の発酵食は「なれずし」。魚を塩と米飯で乳酸発酵させたなれずしは琵琶湖産のニゴロブナを使った「ふなずし」が有名だが、能登でも伝統食だ。昼食で能登町にある「かじ旅館」を訪ねると、アジ、ブリ、アユのなれずしを出してくれた。この旅館では、注文を受けた客にしか出さない。というもの、なれずし独特の匂いがあり、なじめない客も多い。ただ、食通にはたまらない味と匂いなのだという。今回出されたアユは5年もの。料理長が「ヒネものです」と説明してくれた。ヒネものとは2年以上漬け込んだもの。昼から地酒とのマッチングも楽しんだ。
「アンチョビ蔵」。イワシを米糠で漬け込んだ「こんかいわし」も能登では盛んにつくられている。ブルーベリーワインを製造している同町の「柳田食産」は昨年から、廃線となった能登鉄道のトンネルを活用して漬け込んでいる=写真・上=。湿度と温度が一定しているので製造には好条件だ。樽の中で発酵し熟成されたこんかいわしを焼いてほぐしたものや、オリーブ油や香草と合わせたオイルソースはまさにアンチョビだ。これをクラッカーに少し塗り、ワインを飲む。この相性のよさはマリアージュ。そして、廃線のトンネルをアンチョビ蔵として蘇らせたアイデアに脱帽した。
 「広辞苑は間違っています」。こんな話が出たのは同町小木で魚醤油を製造している「ヤマサ商事}を訪ねた時だった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」=写真・下=だ。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓を「いしり」と呼ぶ。製造担当者は「ところが、広辞苑ではいしりはいしるの別称となっている。別称ではなく、材料が違うんです」と続けた。小木(おぎ)は北海道の函館、青森の八戸と並んで日本海のイカ漁の拠点の一つ。「いしり」の産地でもある。ただ、全国的に商品化すると少々ややこしいので、商品表記を「いしる(いか)」「いしる(いわし)」としているメーカーもある。
「広辞苑は間違っています」。こんな話が出たのは同町小木で魚醤油を製造している「ヤマサ商事}を訪ねた時だった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」=写真・下=だ。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓を「いしり」と呼ぶ。製造担当者は「ところが、広辞苑ではいしりはいしるの別称となっている。別称ではなく、材料が違うんです」と続けた。小木(おぎ)は北海道の函館、青森の八戸と並んで日本海のイカ漁の拠点の一つ。「いしり」の産地でもある。ただ、全国的に商品化すると少々ややこしいので、商品表記を「いしる(いか)」「いしる(いわし)」としているメーカーもある。
能登杜氏は今が一番忙しい。そんな中、能登を代表する酒蔵の一つである珠洲市の造り酒屋「宗玄」を訪ねた。「試食してみてください」と杜氏が板状になった酒粕を勧めてくれた。まさにチーズの味がした。普段日本酒を飲まない男性参加者が一枚食べ切り、「酒粕ですっかり酔いました」とうれしそうに話した。先月20日に解禁となった純米生原酒をテイスティングした。ジュワッと広がる飲み口がまさに初しぼり。バスに乗り込むと周囲は暗くなっていた。
2日目は輪島市の醤油蔵「谷川醸造」を見学。代々「サクラ醤油」のブランド名で。輪島は魚介類の水揚げが多い。ちょっと甘めの味が刺身にぴったり。この地で育まれ、花開いた「糀の文化」の印象だ。最近では、能登の地豆である「大浜大豆」と塩田でつくられた塩を原材料にした、こだわりの「能登の丸大豆醤油」をつくっている。
昼食は七尾湾を望むカキ料理の専門店でフルコースを味わった。焼いて、生で、フライで、釜飯で合わせて10個は食べた。それにしても能登の冬の食材はぜいたく過ぎる。ひょっとして海の食材の豊かさが発酵の食文化も育んているのかもしれないと思った。外に出て駐車場を見渡すと7割は県外ナンバーだった。
ツアーの締めくくりは「どぶろく」だった。中能登町の天日陰比咩(あまひかげひめ)神社を訪ねる。蒸した酒米に麹、水を混ぜ、熟成するのを待つ。ろ過はしないため白く濁る。「濁り酒」とも呼ばれる。毎年12月5日の新嘗祭で参拝客に振る舞われる。今年はこれまで最高の333㍑を造った。同神社は2千年余りの歴史をもつ延喜式内社でもある。禰宜の方から話を聞き、どぶろくを頂いて、一行が外に出たとたんに大粒の雨がザッと降ってきた。禰宜は「当神社は雨乞い所でして、神様が皆さんの来訪を喜んでおられるのですよ」と目を細めた。
⇒22日(月)朝・金沢の天気 あめ
 酒蔵と別棟の杜氏と蔵人(くらんど)の詰め所に案内された。朝の作業が終わり休憩中だった。「よう来てくださった」。張りのある声だった。昭和7年(1932)12月生まれ、85歳だ。杜氏室に案内され、開口一番に「世界に通じる酒を造りたいと、この歳になって頑張っておるんです」と。いきなりカウンターパンチを食らった気がした。グローバルに通じる日本酒をつくる、と。そこで「世界に通じる日本酒とはどんな酒ですか」と突っ込んだ。「のど越し。のど越しのキレと含み香、果実味がある軽やかな酒。そんな酒は和食はもとより洋食に合う。食中酒やね」。整然とした言葉運びに圧倒された。
酒蔵と別棟の杜氏と蔵人(くらんど)の詰め所に案内された。朝の作業が終わり休憩中だった。「よう来てくださった」。張りのある声だった。昭和7年(1932)12月生まれ、85歳だ。杜氏室に案内され、開口一番に「世界に通じる酒を造りたいと、この歳になって頑張っておるんです」と。いきなりカウンターパンチを食らった気がした。グローバルに通じる日本酒をつくる、と。そこで「世界に通じる日本酒とはどんな酒ですか」と突っ込んだ。「のど越し。のど越しのキレと含み香、果実味がある軽やかな酒。そんな酒は和食はもとより洋食に合う。食中酒やね」。整然とした言葉運びに圧倒された。 この歳になると片足を棺桶に突っ込んでいるようなものだから、どうせなら酒蔵に戻ろうと。弥助寿司の森田さんも、陶芸の吉田さん(美統、人間国宝)も同じ歳、皆現役で頑張っておられるからね」。酒造り2季のブランクを経て、建物の設計などにかかわり、満を持して昨年暮れに酒造りの現場に復帰した。
この歳になると片足を棺桶に突っ込んでいるようなものだから、どうせなら酒蔵に戻ろうと。弥助寿司の森田さんも、陶芸の吉田さん(美統、人間国宝)も同じ歳、皆現役で頑張っておられるからね」。酒造り2季のブランクを経て、建物の設計などにかかわり、満を持して昨年暮れに酒造りの現場に復帰した。 旅館の従業員に法師(ほうし)という名前の由来を尋ねると、「それはですね」とちょっと身を乗り出すようにして説明してくれた。加賀地方で霊峰と呼ばれる白山(はくさん)は泰澄大師が荒行を積んだことでも知られる。その泰澄にインスピレーションが働いて粟津の地で村人といっしょに温泉を掘り当てた。そこで、弟子の一人の雅亮法師(がりょうほうし)に命じて湯守りをさせた。それが旅館の始まり、とか。一時期、もっとも古い温泉旅館としてギネスブックにも登録されたこともあるそうだ。
旅館の従業員に法師(ほうし)という名前の由来を尋ねると、「それはですね」とちょっと身を乗り出すようにして説明してくれた。加賀地方で霊峰と呼ばれる白山(はくさん)は泰澄大師が荒行を積んだことでも知られる。その泰澄にインスピレーションが働いて粟津の地で村人といっしょに温泉を掘り当てた。そこで、弟子の一人の雅亮法師(がりょうほうし)に命じて湯守りをさせた。それが旅館の始まり、とか。一時期、もっとも古い温泉旅館としてギネスブックにも登録されたこともあるそうだ。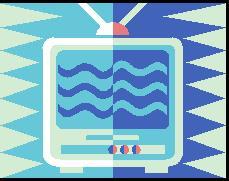 判決の内容をよく読むと、NHKが契約を求める裁判を起こし、勝訴すれば、契約が成立し、テレビを設置した時点からの受信料を支払わなければならない。つまり、最高裁が出した答えは「義務」と同じだ。納得いかないのは、その義務を親から仕送りをもらって学んでいる学生たちにも課しているという点なのだ。
判決の内容をよく読むと、NHKが契約を求める裁判を起こし、勝訴すれば、契約が成立し、テレビを設置した時点からの受信料を支払わなければならない。つまり、最高裁が出した答えは「義務」と同じだ。納得いかないのは、その義務を親から仕送りをもらって学んでいる学生たちにも課しているという点なのだ。 今月12月に新書『実装的ブログ論―日常的価値観を言語化する』(幻冬舎ルネッサンス新書)を出版した。実は、この本を出版した動機の一つとして、若者たちにブログを書いてほしいという思いがあったからだ。
今月12月に新書『実装的ブログ論―日常的価値観を言語化する』(幻冬舎ルネッサンス新書)を出版した。実は、この本を出版した動機の一つとして、若者たちにブログを書いてほしいという思いがあったからだ。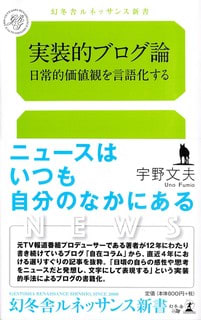 ブログを書く作業は、フェイスブックやツイッター、インスタグラムなどのSNSと違って実に孤独だ。ただ、誰にも気兼ねせず、邪魔されずに自分の価値観を言語として実装するには最高の場でもあると実感している。では、ブログ自体の価値はどこにあるのだろうか。ブログ、つまりウェブログ(ウェブ上の記録)は書き溜めである。日々使うことができるブログに一体何を書き溜めるのか。
ブログを書く作業は、フェイスブックやツイッター、インスタグラムなどのSNSと違って実に孤独だ。ただ、誰にも気兼ねせず、邪魔されずに自分の価値観を言語として実装するには最高の場でもあると実感している。では、ブログ自体の価値はどこにあるのだろうか。ブログ、つまりウェブログ(ウェブ上の記録)は書き溜めである。日々使うことができるブログに一体何を書き溜めるのか。 23日夜、ハノイに到着。24日にハノイから100㌔ほど離れたハナム省モックバック村に向かった。ここに「革命烈士の墓」がある。ベトナムは1954年のディエンビエンフーの戦いでフランスを破り、その後、ベトナム戦争でアメリカを相手に壮絶な戦いを繰り広げた。革命烈士の墓は普段は入口の門の鍵がかかる、まさに聖地なのだ。日本名は分からないが、ベトナム独立のために命を捧げた日本人の墓地があると管理人の女性が案内してくれた。
23日夜、ハノイに到着。24日にハノイから100㌔ほど離れたハナム省モックバック村に向かった。ここに「革命烈士の墓」がある。ベトナムは1954年のディエンビエンフーの戦いでフランスを破り、その後、ベトナム戦争でアメリカを相手に壮絶な戦いを繰り広げた。革命烈士の墓は普段は入口の門の鍵がかかる、まさに聖地なのだ。日本名は分からないが、ベトナム独立のために命を捧げた日本人の墓地があると管理人の女性が案内してくれた。 質問が集中したのは海上保安庁に対してだった。海上保安庁も巡視船で退去警告や放水で違法操業に対応していたのが、イタチごっこの状態だった。漁業関係者からは「退去警告や放水では逆に相手からなめられる(疎んじられる)」と声が上がった。違法操業の漁船に対して、漁船の立ち入り調査をする臨検、あるいは船長ら乗組員の拿捕といった強い排除行動を実施しないと取り締まりの効果が上がらない、と関係者は苛立ちを募らせ、石川県漁協の組合長が強い排除行動を求める要望書を手渡したのだった。
質問が集中したのは海上保安庁に対してだった。海上保安庁も巡視船で退去警告や放水で違法操業に対応していたのが、イタチごっこの状態だった。漁業関係者からは「退去警告や放水では逆に相手からなめられる(疎んじられる)」と声が上がった。違法操業の漁船に対して、漁船の立ち入り調査をする臨検、あるいは船長ら乗組員の拿捕といった強い排除行動を実施しないと取り締まりの効果が上がらない、と関係者は苛立ちを募らせ、石川県漁協の組合長が強い排除行動を求める要望書を手渡したのだった。 ことし3月、元Googleアメリカ本社副社長兼日本法人代表取締役の村上憲郎氏の講演を聴く機会に恵まれた。話の中でショックだったのは、人がこなしてきた仕事が近い将来、AIに取って代わられるかもしれないということだった。そのポイントが言語処理。「推論機構」という、複雑な前提条件からIf、Then、など言葉のルールを駆使して結論を推論するハードウエアの開発だ。村上氏が述べたAIに取って代わられるかもしれない仕事がたとえば、簿記の仕訳や弁護士の業務を補助するパラリーガルだという。
ことし3月、元Googleアメリカ本社副社長兼日本法人代表取締役の村上憲郎氏の講演を聴く機会に恵まれた。話の中でショックだったのは、人がこなしてきた仕事が近い将来、AIに取って代わられるかもしれないということだった。そのポイントが言語処理。「推論機構」という、複雑な前提条件からIf、Then、など言葉のルールを駆使して結論を推論するハードウエアの開発だ。村上氏が述べたAIに取って代わられるかもしれない仕事がたとえば、簿記の仕訳や弁護士の業務を補助するパラリーガルだという。 つい、いっしょに歌いたくなるようなインスピレーションが働く。古代、バビロニア王ナブッコがユダヤの国に攻め込み、捕らえられ、強制労働を強いられるユダヤ人たちが故郷を想って歌う合唱曲なのだ。力強く、したたかに、希望を持って、そしてゆっくりと。
つい、いっしょに歌いたくなるようなインスピレーションが働く。古代、バビロニア王ナブッコがユダヤの国に攻め込み、捕らえられ、強制労働を強いられるユダヤ人たちが故郷を想って歌う合唱曲なのだ。力強く、したたかに、希望を持って、そしてゆっくりと。 朝鮮の木造漁船はさらに転覆軒数が増えるのではないかと不安がよぎる。それはまさに自分の中にあるニュースだ。
朝鮮の木造漁船はさらに転覆軒数が増えるのではないかと不安がよぎる。それはまさに自分の中にあるニュースだ。