☆「ネットどぶ板選挙」を読む
 確かに実に分かりやすい。小沢氏の戦略には、民主党の独自色といった概念より、自民党の候補者よりどぶ板選挙を徹底して選挙に勝つこと、それが政権構想そのものだと訴えたに等しい。しかし、その選挙手法はかつての自民党そのものだ。去年9月の郵政民営化を問う総選挙のように、政策の違いがはっきり理解できなければ有権者は戸惑い、しらける。
確かに実に分かりやすい。小沢氏の戦略には、民主党の独自色といった概念より、自民党の候補者よりどぶ板選挙を徹底して選挙に勝つこと、それが政権構想そのものだと訴えたに等しい。しかし、その選挙手法はかつての自民党そのものだ。去年9月の郵政民営化を問う総選挙のように、政策の違いがはっきり理解できなければ有権者は戸惑い、しらける。
逆に「民主党的」なのが自民党だ。きのう6月4日、自民党青年局を中心にした全国一斉街頭行動を行った。「次世代へ繋ぐ安心と安全」をテーマに各都道府県レベルで街頭に立ち、北朝鮮による拉致問題の早期解決や街の安全、食の安心などを政策推進を求めるという内容だ。注目を集めたのが、武部勤幹事長がラジオCMで統一行動への市民参加を呼びかけ、「詳しくは自民党ホームページを見て下さい」とコメントしていたことだ。その自民のホームページを見ると各都道府県でキャンペーンが行われる場所や内容が詳しく掲載されていた。ラジオからインターネットへのメディアを連動なのである。放送媒体やインターネットを使って呼びかけ、全国一斉くまなく街頭に立つという意味ではこれもある意味でのどぶ板と言えるかもしれない。
そもそも統一行動の呼びかけにラジオを使ういう発想は従来の自民党にはなかったのではないか。おそらく、党広報本部副本部長の世耕弘成氏(参院議員)ら若手が仕掛けたに違いないと思った。というのも、世耕氏らは来年夏の参院選挙で解禁される予定の選挙のインターネット利用を念頭に置いて、すでに党内でワーキンググループを結成し、選挙対策をすでに始めている。つまり、来年の参院選挙は「ネット選挙」が注目され、いかにインターネットをメディアとして駆使するか、放送メディアとインターネットを連動させるか、という選挙戦略に練っているのである。今回の統一行動のラジオCMもそのシュミレーションの一つと見てよい。
従来の「労組まわり」や「地盤」を歩くどぶ板戦略を踏襲する小沢・民主と、放送メディアとインターネットで「どぶ板」戦略を打ち出す自民が鋭く対立するのが来年の選挙である。どちらのどぶ板が勝つのか。こんな視点で見ると、随分と選挙も面白く見えてくるのではないだろうか。
⇒5日(月)午前・金沢の天気 はれ
 ませるらしい。
ませるらしい。 という意味だが、今回は「地球八分の一」が実感できるような話だ。
という意味だが、今回は「地球八分の一」が実感できるような話だ。 るのかというと。南極の昭和基地からのデータは電波信号にして、太平洋をカバーしている通信衛星「インテルサット」を介して、山口県の受信施設に送られる。山口から東京の国立極地研究所は光ファイバーでデータが送られ、さらに金沢大学に届くという訳だ。それを双方向で結ぶとテレビ電話になる。
るのかというと。南極の昭和基地からのデータは電波信号にして、太平洋をカバーしている通信衛星「インテルサット」を介して、山口県の受信施設に送られる。山口から東京の国立極地研究所は光ファイバーでデータが送られ、さらに金沢大学に届くという訳だ。それを双方向で結ぶとテレビ電話になる。 界に広まった。
界に広まった。 然学校」の拠点でもある。
然学校」の拠点でもある。 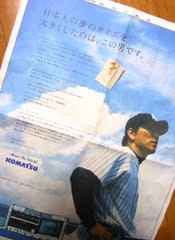 コピーの続き。「松井は野球の天才ではない。努力の天才なのだ」と言い、「コマツは、どうだろう。自分たちの技術に誇りを持ち、よりよい商品づくり心がけているだろうか。」と問う。そして、最後に小さく、「松井選手の今回のケガに際し、一日も早い復帰をお祈りしております」と締めている。松井の出身地である石川県能美市に近い小松市に主力工場を持つコマツは、ヤンキース入りした直後から松井選手のスポンサーになった。嫌みのない、実にタイムリーな広告企画ではある。
コピーの続き。「松井は野球の天才ではない。努力の天才なのだ」と言い、「コマツは、どうだろう。自分たちの技術に誇りを持ち、よりよい商品づくり心がけているだろうか。」と問う。そして、最後に小さく、「松井選手の今回のケガに際し、一日も早い復帰をお祈りしております」と締めている。松井の出身地である石川県能美市に近い小松市に主力工場を持つコマツは、ヤンキース入りした直後から松井選手のスポンサーになった。嫌みのない、実にタイムリーな広告企画ではある。 確かに、同研究所は板橋区加賀1丁目9番10号が所在地だ。加賀といえば加賀藩、つまり金沢なのである。加賀という地名は偶然ではない。かつて、加賀藩の江戸の下屋敷があったエリアなのである。それが今でも地名として残っている。
確かに、同研究所は板橋区加賀1丁目9番10号が所在地だ。加賀といえば加賀藩、つまり金沢なのである。加賀という地名は偶然ではない。かつて、加賀藩の江戸の下屋敷があったエリアなのである。それが今でも地名として残っている。 を想定したのだ。
を想定したのだ。 あの松井秀喜選手はどうなっているのか、楽しみにしていた。きょう(9日)、久しぶりに東京のJR浜松町駅にきた。なんと、松井選手はサッカーボールを持っていた。駅構内の広告のことである。なぜ松井がサッカーボールをと思うだろう。答えは簡単。松井のスポンサーになっている東芝はFIFAワールドカップ・ドイツ大会のスポンサーでもある。その大会に東芝は2000台以上のノートパソコンを提供するそうだ。理由はどうあれ、サッカーボールを持った松井選手というのは珍しいので、その広告をカメラで撮影した。
あの松井秀喜選手はどうなっているのか、楽しみにしていた。きょう(9日)、久しぶりに東京のJR浜松町駅にきた。なんと、松井選手はサッカーボールを持っていた。駅構内の広告のことである。なぜ松井がサッカーボールをと思うだろう。答えは簡単。松井のスポンサーになっている東芝はFIFAワールドカップ・ドイツ大会のスポンサーでもある。その大会に東芝は2000台以上のノートパソコンを提供するそうだ。理由はどうあれ、サッカーボールを持った松井選手というのは珍しいので、その広告をカメラで撮影した。
 JR浜松町駅近くに東芝の本社があり、ここでしか見れない、いわば「ご当地ポスター」のようなもの。去年の大晦日に見た松井選手の広告は本物のゴジラと顔を並べていた。
JR浜松町駅近くに東芝の本社があり、ここでしか見れない、いわば「ご当地ポスター」のようなもの。去年の大晦日に見た松井選手の広告は本物のゴジラと顔を並べていた。