☆「パラダイス鎖国」
「パラダイス鎖国」という言葉を初めて聞いた。10月10日夜、能登空港4F講義室で開かれた金沢大学「地域づくり支援講座」で、ゲストスピーカーの金子洋三氏(元JICA青年海外協力隊事務局長、社団法人「青年海外協力協会」会長)が使った言葉だ。「青年海外協力隊のボランティアに応募する若者が減っている。パラダイス鎖国という言葉がありますが、日本に安住して、外に向かって何か挑戦しようという意識が薄れているのかもしれない」と述べた。
 もともとは、ことし3月に出版された「パラダイス鎖国 忘れられた大国・日本」 (海部美知、アスキー新書)のタイトルから引用された言葉だ。ことし1月のダボス会議で、「Japan: A Forgotten Power?(日本は忘れられた大国なのか)」というセッションが開かれ、国際的に日本の内向き志向が論議になったという。高度経済成長から貿易摩擦の時代を経て、日本はいつの間にか、世界から見て存在感のない国になってしまっている。その背景には、安全や便利さ、そしてモノの豊かさ日本は欧米以上になり、外国へのあこがれも昔ほど持たなくなったことがある。明治以来の欧米に追いつけ追い越せのコンプレックスは抜け切ったともいえる。ハングリー精神とかチャレンジ精神という言葉は死語になりつつあり、リスクを取らないことが美徳であるかのような社会の風潮だ。これでは人は育たず、社会も会社も停滞する。
もともとは、ことし3月に出版された「パラダイス鎖国 忘れられた大国・日本」 (海部美知、アスキー新書)のタイトルから引用された言葉だ。ことし1月のダボス会議で、「Japan: A Forgotten Power?(日本は忘れられた大国なのか)」というセッションが開かれ、国際的に日本の内向き志向が論議になったという。高度経済成長から貿易摩擦の時代を経て、日本はいつの間にか、世界から見て存在感のない国になってしまっている。その背景には、安全や便利さ、そしてモノの豊かさ日本は欧米以上になり、外国へのあこがれも昔ほど持たなくなったことがある。明治以来の欧米に追いつけ追い越せのコンプレックスは抜け切ったともいえる。ハングリー精神とかチャレンジ精神という言葉は死語になりつつあり、リスクを取らないことが美徳であるかのような社会の風潮だ。これでは人は育たず、社会も会社も停滞する。
古代ローマ帝国が滅亡もしたのもこうした社会の活気が減退したのが原因といわれていいる。ローマ市民や、ローマに奉仕した属州民の特権であったローマ市民権を属州のすべての人々に無条件に与えたことで、ローマ市民権の価値が下落して、地中海最強とうたわれたローマの重装歩兵のアイデンティティ(自負心に根ざしたローマ防衛の意志)も拡散してしまった。また、ローマ市民としての歴史性と自尊心を持つ兵士の数が減少したことにより、ローマ軍の質的な低下を招いた。さらに、ローマ市民内部に固定的な経済階層が生まれたことで、経済の活力や市民の上昇志向は衰退したといわれる。
パラダイス鎖国が産業面で蔓延したらどうなるのか。ブロードバンドのインフラで世界に先行しているにもかかわらず、ITの新興勢力となる企業はどこにいるのか見えない。高品質、高性能、先進的というジャパン・ブランドは確かに健在であるものの、売れているのは日本だけで、海外では押されているのではないか。ソーラー発電のパネルなどかついてはお家芸といわわれた分野がいまではワン・オブ・ゼムではないのか。このままでは日本はいずれパラダイスですらなくなる。※写真は古代ローマ帝国のコロセウム
⇒12日(日)夜・金沢の天気 くもり
 さて、シリーズ「能登の旋風(かぜ)」は里山里海国際交流フォーラム「能登エコ・スタジアム2008」のイベントで拾った話題を紹介している。9月13日から17日にかけての「能登エコ・スタジアム2008」は3つのフォーラム、6つのプログラム、1つのツアーから構成されていたが、17日にシニアコース(シニア短期留学)の修了式をもって、すべてのメニューを完了した。また、同日は生物多様性条約のムハマド・ジョグラフ事務局長の能登視察も終了した。一連のイベントメニューの中でのVIP視察だった。
さて、シリーズ「能登の旋風(かぜ)」は里山里海国際交流フォーラム「能登エコ・スタジアム2008」のイベントで拾った話題を紹介している。9月13日から17日にかけての「能登エコ・スタジアム2008」は3つのフォーラム、6つのプログラム、1つのツアーから構成されていたが、17日にシニアコース(シニア短期留学)の修了式をもって、すべてのメニューを完了した。また、同日は生物多様性条約のムハマド・ジョグラフ事務局長の能登視察も終了した。一連のイベントメニューの中でのVIP視察だった。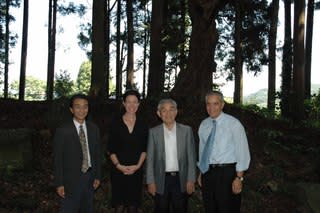 今回のイベントで印象に残った2枚の写真。持続可能なこと、それは地下に封じ込められた化石燃料を掘り出して、燃焼させ、二酸化炭素を排出することではない。二酸化炭素を吸収し、光合成によって成長した植物をエネルギー化すること。里の生えるススキ、カヤ類を燃料化する試みが始まっている。それらをペレット化して燃料、あるいは家畜の飼料にする。奥能登では戦後、1800haもの畑地造成が行われたが、そのうち1000haが耕作放棄されススキ、カヤが生い茂っている。それをなんとかしたいとの発想でバイオマス研究から実用化の段階に向けて試行が続いている。能登エコ・スタジアムのコース「バイオエコツーリズム」ではその試みに興味を持った若者たちが大勢集まってきた。そして実際にススキを刈り取り、ペレット化を体験したのである。上の写真はその刈り入れの様子だ。地域エネルギーの可能性を感じさせる光景に見えた。
今回のイベントで印象に残った2枚の写真。持続可能なこと、それは地下に封じ込められた化石燃料を掘り出して、燃焼させ、二酸化炭素を排出することではない。二酸化炭素を吸収し、光合成によって成長した植物をエネルギー化すること。里の生えるススキ、カヤ類を燃料化する試みが始まっている。それらをペレット化して燃料、あるいは家畜の飼料にする。奥能登では戦後、1800haもの畑地造成が行われたが、そのうち1000haが耕作放棄されススキ、カヤが生い茂っている。それをなんとかしたいとの発想でバイオマス研究から実用化の段階に向けて試行が続いている。能登エコ・スタジアムのコース「バイオエコツーリズム」ではその試みに興味を持った若者たちが大勢集まってきた。そして実際にススキを刈り取り、ペレット化を体験したのである。上の写真はその刈り入れの様子だ。地域エネルギーの可能性を感じさせる光景に見えた。 能登半島地震の発生翌日、被害がもっとも大きいとされた門前地区に入った。住民のうち65歳以上が47%を占める。金沢大学の地域連携コーディネーターとして、学生によるボランティア支援をどのようなかたちで進めたらよいかを調査するのが当初の目的だった。そこで見たある光景をきっかけに、「震災とメディア」をテーマに調査研究を実施することになる。震災当日からテレビ系列が大挙して同町に陣取っていた。現場中継のため、倒壊家屋に横付けされた民放テレビ局のSNG(Satellite News Gathering)車をいぶかしげに見ている被災者の姿があった。この惨事は全国中継されるが、被災地の人たちは視聴できないのではないか。また、半壊の家屋の前で茫然(ぼうぜん)と立ちつくすお年寄り、そしてその半壊の家屋が壊れるシーンを撮影しようと、ひたすら余震を待って身構えるカメラマンのグループがそこにあった=写真・上=。こうしたメディアの行動は、果たして被災者に理解されているのだろうか。それより何より、メディアはこの震災で何か役立っているのだろうか、という素朴な疑問があったからだ。 当時、カメラマンたちが狙っていた半壊の家はいまどうなっているのか確認したかった。その家はカメラマンたちが期待したようにはならなかった。つまり、余震での倒壊は免れた。しかし、住めるような状態ではなかったので、そのままになっているのか、取り壊して更地なっているのか、再建されているのか…。何かの折に再び訪ねてみたいと思っていた。
能登半島地震の発生翌日、被害がもっとも大きいとされた門前地区に入った。住民のうち65歳以上が47%を占める。金沢大学の地域連携コーディネーターとして、学生によるボランティア支援をどのようなかたちで進めたらよいかを調査するのが当初の目的だった。そこで見たある光景をきっかけに、「震災とメディア」をテーマに調査研究を実施することになる。震災当日からテレビ系列が大挙して同町に陣取っていた。現場中継のため、倒壊家屋に横付けされた民放テレビ局のSNG(Satellite News Gathering)車をいぶかしげに見ている被災者の姿があった。この惨事は全国中継されるが、被災地の人たちは視聴できないのではないか。また、半壊の家屋の前で茫然(ぼうぜん)と立ちつくすお年寄り、そしてその半壊の家屋が壊れるシーンを撮影しようと、ひたすら余震を待って身構えるカメラマンのグループがそこにあった=写真・上=。こうしたメディアの行動は、果たして被災者に理解されているのだろうか。それより何より、メディアはこの震災で何か役立っているのだろうか、という素朴な疑問があったからだ。 当時、カメラマンたちが狙っていた半壊の家はいまどうなっているのか確認したかった。その家はカメラマンたちが期待したようにはならなかった。つまり、余震での倒壊は免れた。しかし、住めるような状態ではなかったので、そのままになっているのか、取り壊して更地なっているのか、再建されているのか…。何かの折に再び訪ねてみたいと思っていた。 MさんとNさんをお誘いして門前入りした9月16日午前、車を降りて、問題のシーンと遭遇した場所に再び立ってみた。その民家は再建途中だった=写真・下=。まもなく完成するだろう。おそらくこの家の家族はまだ避難所生活と想像するが、まもなく新居での生活が始まるだろう。そう考えると、正直にうれしかった。震災から1年6ヵ月余り。それにしても、被災者とメディア側の溝は深い。メディア側で被災者の目線というものを体験しなければこの溝は埋まらない。そこで、「震災とメディア」の調査報告書には下記の一文をつけた。
MさんとNさんをお誘いして門前入りした9月16日午前、車を降りて、問題のシーンと遭遇した場所に再び立ってみた。その民家は再建途中だった=写真・下=。まもなく完成するだろう。おそらくこの家の家族はまだ避難所生活と想像するが、まもなく新居での生活が始まるだろう。そう考えると、正直にうれしかった。震災から1年6ヵ月余り。それにしても、被災者とメディア側の溝は深い。メディア側で被災者の目線というものを体験しなければこの溝は埋まらない。そこで、「震災とメディア」の調査報告書には下記の一文をつけた。 た。9月16日午前のプログラム自由時間を利用して、MさんとNさんを誘って門前地区を訪ねた。
た。9月16日午前のプログラム自由時間を利用して、MさんとNさんを誘って門前地区を訪ねた。 次に訪れた総持寺もまた被災し再興途中だった。僧堂の再建工事は屋根の部分まで進んでいた。MさんとNさんはここで「瓦寄進」をした。瓦に祈願の文字を書き、お布施をする。亡き父親が当地出身というMさんは「先祖供養」と書いていた。鶴見の総持寺と縁があるNさんは「一家繁栄」を祈願した。Nさんはさらに総持寺と縁を感じることになる。僧堂の建築現場に近づいてみると、長男が勤める建築事務所(東京都)がこの僧堂の設計・管理に携わっていたのだ。「大変名誉な仕事をさせてもらっている。親として素直にうれしい」と目を輝かせた。
次に訪れた総持寺もまた被災し再興途中だった。僧堂の再建工事は屋根の部分まで進んでいた。MさんとNさんはここで「瓦寄進」をした。瓦に祈願の文字を書き、お布施をする。亡き父親が当地出身というMさんは「先祖供養」と書いていた。鶴見の総持寺と縁があるNさんは「一家繁栄」を祈願した。Nさんはさらに総持寺と縁を感じることになる。僧堂の建築現場に近づいてみると、長男が勤める建築事務所(東京都)がこの僧堂の設計・管理に携わっていたのだ。「大変名誉な仕事をさせてもらっている。親として素直にうれしい」と目を輝かせた。 とき腫瘍を患って他界しました。それから12年経ちます…」と語り始めた。約束を果たさぬまま先立った息子への思いも募ったのか、Mさんの顔は曇りがちだった。
とき腫瘍を患って他界しました。それから12年経ちます…」と語り始めた。約束を果たさぬまま先立った息子への思いも募ったのか、Mさんの顔は曇りがちだった。 参加者の構成は東京都3人、兵庫県3人、大阪府2人、滋賀県1人、京都府1人、神奈川県1人である。年齢は60歳から84歳。男女比は女性7人、男性4人の構成。11日に開講式があり、懇親会があった。さっそく「シニア短期留学を研究する協議会をつくってはどうか」「金沢人、不親切論」なども飛び出して、侃侃諤諤(かんかんがくがく)の状態となった。「論客が多すぎる」。これが第一印象だった。反省もあった。参加者には予めパンフレットで講義内容を簡単に説明してあったが、金沢大学がどのような学習サービスを提供してくれるのか、イメージとしてはインプットされていなかったのだろう。要は、説明不足。だから、懇親会での話が講義内容に集中するのではなく、ベクトルがバラバラな方向に展開したのだった。出だしはこんなふうだった。
参加者の構成は東京都3人、兵庫県3人、大阪府2人、滋賀県1人、京都府1人、神奈川県1人である。年齢は60歳から84歳。男女比は女性7人、男性4人の構成。11日に開講式があり、懇親会があった。さっそく「シニア短期留学を研究する協議会をつくってはどうか」「金沢人、不親切論」なども飛び出して、侃侃諤諤(かんかんがくがく)の状態となった。「論客が多すぎる」。これが第一印象だった。反省もあった。参加者には予めパンフレットで講義内容を簡単に説明してあったが、金沢大学がどのような学習サービスを提供してくれるのか、イメージとしてはインプットされていなかったのだろう。要は、説明不足。だから、懇親会での話が講義内容に集中するのではなく、ベクトルがバラバラな方向に展開したのだった。出だしはこんなふうだった。 というのも、田の神は目が不自由とされ、迎え入れる主人は想像力をたくましくしながら、「田の神さま、廊下の段差がありますのでお気をつけください」「料理は向かって左がお頭つきのタイでございます」などとリテールにこだわった丁寧な案内と説明をすることになる。これはある意味で高度なホスピタリティ(もてなし)である。招き入れる家の構造、料理の内容はその家によって異なり、自ら目が不自由だと仮定して、どのように案内すれば田の神が転ばずに済むか、居心地がよいか(満足か)とイマジネーションを膨らませトレーニングする。これがホスピタリティ(もてなし)の原点となる。万人に通用するように工夫された外食産業の店員対応マニュアルとは対極にある。
というのも、田の神は目が不自由とされ、迎え入れる主人は想像力をたくましくしながら、「田の神さま、廊下の段差がありますのでお気をつけください」「料理は向かって左がお頭つきのタイでございます」などとリテールにこだわった丁寧な案内と説明をすることになる。これはある意味で高度なホスピタリティ(もてなし)である。招き入れる家の構造、料理の内容はその家によって異なり、自ら目が不自由だと仮定して、どのように案内すれば田の神が転ばずに済むか、居心地がよいか(満足か)とイマジネーションを膨らませトレーニングする。これがホスピタリティ(もてなし)の原点となる。万人に通用するように工夫された外食産業の店員対応マニュアルとは対極にある。 実は今回のイベント「能登エコ・スタジアム2008」もその関連会議のシュミレーションとしての意味合いで金沢セッション、能登エクスカーションが構成された。ジョグラフ氏の能登訪問は2010年の能登エクスカーションの「下見」との意義付けもある。もし、ジョグラフ氏がここで「能登で見るべきもの、学ぶべきものはない」と感じれば、2010年の能登エクスカーションは沙汰やみになる。迎えるスタッフもプラン段階から気を遣った。では、ジョグラフ氏の反応はどうだったのか。
実は今回のイベント「能登エコ・スタジアム2008」もその関連会議のシュミレーションとしての意味合いで金沢セッション、能登エクスカーションが構成された。ジョグラフ氏の能登訪問は2010年の能登エクスカーションの「下見」との意義付けもある。もし、ジョグラフ氏がここで「能登で見るべきもの、学ぶべきものはない」と感じれば、2010年の能登エクスカーションは沙汰やみになる。迎えるスタッフもプラン段階から気を遣った。では、ジョグラフ氏の反応はどうだったのか。 まず、「能登エコ・スタジアム2008」の概要を説明しよう。金沢大学などが企画し,地域自治体と連携して開催した初めての大型イベント。4日間で3つのシンポジウム、6つのイベント、1つのツアーを実施した。生物多様性などの環境問題を理解するとともに、海や山を活用した地域振興策を探ろうという内容。13日に開催したキックオフシポジウム「里山里海から地球へ」=写真=には市民ら280人が参加し、国連大学の武内和彦副学長(東京大学教授)や生物多様性ASEANセンターのG.W.ロザリアストコ部長、女子美術大学の北川フラム教授が講演した。
まず、「能登エコ・スタジアム2008」の概要を説明しよう。金沢大学などが企画し,地域自治体と連携して開催した初めての大型イベント。4日間で3つのシンポジウム、6つのイベント、1つのツアーを実施した。生物多様性などの環境問題を理解するとともに、海や山を活用した地域振興策を探ろうという内容。13日に開催したキックオフシポジウム「里山里海から地球へ」=写真=には市民ら280人が参加し、国連大学の武内和彦副学長(東京大学教授)や生物多様性ASEANセンターのG.W.ロザリアストコ部長、女子美術大学の北川フラム教授が講演した。 この文を書いていたとき、実は念頭に石川県の谷本正憲知事のことがあった。失礼な言い方になるかもしれないが、谷本氏はことし春ごろまで、それほど里山や里海といった言葉に深い造詣を抱いてはおられなかったと思う。ところが、この4月に金沢で設置された国連大学の研究所(いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット)が里山里海を研究テーマにしていること、さらにドイツでの環境視察(5月22日-29日)、その視察の最中で生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)の関連会議でスピーチをきっかけとして猛勉強され、いまではおそらく「里山知事」を自認するまでになった。そして、環境への取り組みとして、里山里海をテーマに行政施策に反映させてもいる。谷本知事には里山里海の風景がこれまでとまったく違って見えているのだ。
この文を書いていたとき、実は念頭に石川県の谷本正憲知事のことがあった。失礼な言い方になるかもしれないが、谷本氏はことし春ごろまで、それほど里山や里海といった言葉に深い造詣を抱いてはおられなかったと思う。ところが、この4月に金沢で設置された国連大学の研究所(いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット)が里山里海を研究テーマにしていること、さらにドイツでの環境視察(5月22日-29日)、その視察の最中で生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)の関連会議でスピーチをきっかけとして猛勉強され、いまではおそらく「里山知事」を自認するまでになった。そして、環境への取り組みとして、里山里海をテーマに行政施策に反映させてもいる。谷本知事には里山里海の風景がこれまでとまったく違って見えているのだ。 ~里山里海(さとやまさとうみ)という言葉が最近よく使われるようになってきました。日本ではちょっと郊外に足を運べば里山があり里海が広がります。実はそこは多様な生物を育む生態系(エコシステム)であるとことを、私たち日本人は忘れてしまっていたようです。二酸化炭素の吸収、生物多様性、持続可能な社会など、環境を考えるさまざまなキーワードが里山里海に潜んでいます。「能登エコ・スタジアム2008」ではこれらのキーワードを探す旅をします。それを発見したとき、あなたが見える里山里海の風景は一変するはずです。~
~里山里海(さとやまさとうみ)という言葉が最近よく使われるようになってきました。日本ではちょっと郊外に足を運べば里山があり里海が広がります。実はそこは多様な生物を育む生態系(エコシステム)であるとことを、私たち日本人は忘れてしまっていたようです。二酸化炭素の吸収、生物多様性、持続可能な社会など、環境を考えるさまざまなキーワードが里山里海に潜んでいます。「能登エコ・スタジアム2008」ではこれらのキーワードを探す旅をします。それを発見したとき、あなたが見える里山里海の風景は一変するはずです。~