☆「新しい資本主義」その実現可能性はあるのか
前回の話の続き。岸田総理はきのう14日の衆院解散後の記者会見で、今回の衆院選挙を「未来選択選挙」と位置づけ、「コロナとの戦い、危機的な状況を乗り越えた先に、どんな社会を見ていくのか。これがまず大きな争点になるんだと思う」と述べた。具体策として、「成長の果実が幅広く行き渡る『成長と分配の好循環』を実現する」とし、数十兆円規模の経済対策を最優先で行うと説明した。成長と分配の好循環は岸田氏が総裁選でも繰り返し述べてきた「新しい資本主義」の基本理念なのだろうが、その仕組みや具体策が見えない。結局、数十兆円規模のバラまきとしか理解できなかった。
そもそも、「新しい資本主義」と発言しているが、既存の資本主義を岸田氏はどう捉えていて、どのように改革するのか。もし、経済学者に新しい資本主義の理論を再構築せよと迫っても、おそらく逃げ出すだろう。「資本主義」という言葉そのものが重く深い。安易に「新しい資本主義」という言葉を使うべきではないと考えるのだが。それでも、岸田内閣は「新しい資本主義」に向けて一歩踏み出した。
 NHKニュースによると、きょう政府は、岸田総理を本部長にすべての閣僚が参加する「新しい資本主義実現本部」を設置し=写真、首相官邸公式ホームページより=、経済成長の具体策を検討してきた「成長戦略会議」を廃止して、本部のもとに「新しい資本主義実現会議」を設けることを決定した。会議のメンバーの有識者15人のうち、半数近い7人が女性。日本総合研究所の翁百合理事長やAIコンサルティングの会社「シナモン」(東京)社長の平野未来氏らが参加する。経済3団体と連合の代表、中小・新興企業の経営者も出席する。
NHKニュースによると、きょう政府は、岸田総理を本部長にすべての閣僚が参加する「新しい資本主義実現本部」を設置し=写真、首相官邸公式ホームページより=、経済成長の具体策を検討してきた「成長戦略会議」を廃止して、本部のもとに「新しい資本主義実現会議」を設けることを決定した。会議のメンバーの有識者15人のうち、半数近い7人が女性。日本総合研究所の翁百合理事長やAIコンサルティングの会社「シナモン」(東京)社長の平野未来氏らが参加する。経済3団体と連合の代表、中小・新興企業の経営者も出席する。
政府の肝いりで「新しい資本主義実現会議」を立ち上げのだから、今後のどのような議論の展開があるのか注目したい。課題はいくつもある。経済成長が止まってしまっている日本をどのように成長させるのか。さらに、日本は世界最速で高齢化と人口減少が進んでいる国だ。マーケットが縮小する中で、どのように成長と配分の好循環を産み出していくのか。
日本は「低欲望社会」とも言われ、投資より貯蓄に励む。日本銀行がことし9月17日に公表した「資金循環統計速報」によると、6月末時点の家計金融資産残高は1992兆円だった。家計金融資産に占める現金・預金の割合は2020年度末が53%だった。つまり、1000兆円余りがそのまま眠っている。貯蓄が増えてお金が市場に回らないのだ。日本にはさまざま災害があるので、手元にキャッシュを置く指向があるとも言われている。岸田総理が新しい資本主義を唱えても、国民は投資しない、できない現実がある。
日本が発した「新しい資本主義」は、おそらく世界の経済学者や投資家が注目している。途中で挫折すれば物笑いのネタになる。
⇒15日(金)夜・金沢の天気 はれ
 ネットで「飛び恥」を検索してみると、この言葉は、若き環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが育ったスウェーデンが発祥の地のようだ。2019年9月、16歳のグレタさんが参加した国連気候行動サミット(国連本部)には、温室効果ガス排出量が大きい飛行機には乗らないと、太陽光パネルと水中タービン発電機が付いたヨット船で父親らと大西洋を横断してニューヨーク港に着いたことが、世界のメディアに大きく取り上げられた。
ネットで「飛び恥」を検索してみると、この言葉は、若き環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが育ったスウェーデンが発祥の地のようだ。2019年9月、16歳のグレタさんが参加した国連気候行動サミット(国連本部)には、温室効果ガス排出量が大きい飛行機には乗らないと、太陽光パネルと水中タービン発電機が付いたヨット船で父親らと大西洋を横断してニューヨーク港に着いたことが、世界のメディアに大きく取り上げられた。 実にタイムリーな受賞ではある。今月31日からイギリス・グラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催され、各国の代表やNGOが脱炭素の目標や具体策について話し合う。今回のノーベル賞受賞で、温室効果ガスの削減こそ国際的な課題として広く認知されることになるだろう。
実にタイムリーな受賞ではある。今月31日からイギリス・グラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催され、各国の代表やNGOが脱炭素の目標や具体策について話し合う。今回のノーベル賞受賞で、温室効果ガスの削減こそ国際的な課題として広く認知されることになるだろう。 りながら視聴していると、間もなくして、2機目が同じワールドトレードセンターの別棟に突っ込んできた。リアルタイムの映像で衝撃的だった。世界の多くの視聴者が「9・11」テロリズム(terrorism)の目撃者になった。
りながら視聴していると、間もなくして、2機目が同じワールドトレードセンターの別棟に突っ込んできた。リアルタイムの映像で衝撃的だった。世界の多くの視聴者が「9・11」テロリズム(terrorism)の目撃者になった。 ワシンポストは記事で、タリバン支配下でアフガンの女性は伝統的な役割と服装にとどまることが強いられる。アフガンの女性テコンドー選手は、男性と一緒に訓練している姿を見るだけでも、タリバンは「私たちを撃ってくるだろう」とインタビューで語ったと伝えている。文中では「two athletes ended Sunday in a poignant scene」と表現し、アフガンの2人の選手によって(パラが閉会した)日曜日は痛烈な場面で終わったと評している。
ワシンポストは記事で、タリバン支配下でアフガンの女性は伝統的な役割と服装にとどまることが強いられる。アフガンの女性テコンドー選手は、男性と一緒に訓練している姿を見るだけでも、タリバンは「私たちを撃ってくるだろう」とインタビューで語ったと伝えている。文中では「two athletes ended Sunday in a poignant scene」と表現し、アフガンの2人の選手によって(パラが閉会した)日曜日は痛烈な場面で終わったと評している。 前回のオリンピック開会式(7月23日)との違いは主役がいて統一感があったことだ。とくに、車イスに乗って「片翼の小さな飛行機」の物語を演じた和合由依さんは実に表情豊かだった。中学2年の13歳。先天性の病気で、手足が自由に使えない。演技経験はなかったが、一般公募でオーディションに合格したと紹介されていた。その主役を盛り立てる演技も心に響いた。
前回のオリンピック開会式(7月23日)との違いは主役がいて統一感があったことだ。とくに、車イスに乗って「片翼の小さな飛行機」の物語を演じた和合由依さんは実に表情豊かだった。中学2年の13歳。先天性の病気で、手足が自由に使えない。演技経験はなかったが、一般公募でオーディションに合格したと紹介されていた。その主役を盛り立てる演技も心に響いた。 なしの仕方は家々で異なるが、共通することが一つある。それは、田の神さまは目が不自由という設定になっている。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂でうっかり目を突いてしまったなどの伝承がある。
なしの仕方は家々で異なるが、共通することが一つある。それは、田の神さまは目が不自由という設定になっている。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂でうっかり目を突いてしまったなどの伝承がある。  すでにイスラエルなど始まっている新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種。アメリカではバイデン大統領が2回目の接種を終えてから8ヵ月経った人に対し、9月20日から3回目の接種を行う方針を明らかにした(8月19日付・NHKニュースWeb版)。アメリカでは3回目接種を「booster shot」と称している。追加接種の意味だ。
すでにイスラエルなど始まっている新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種。アメリカではバイデン大統領が2回目の接種を終えてから8ヵ月経った人に対し、9月20日から3回目の接種を行う方針を明らかにした(8月19日付・NHKニュースWeb版)。アメリカでは3回目接種を「booster shot」と称している。追加接種の意味だ。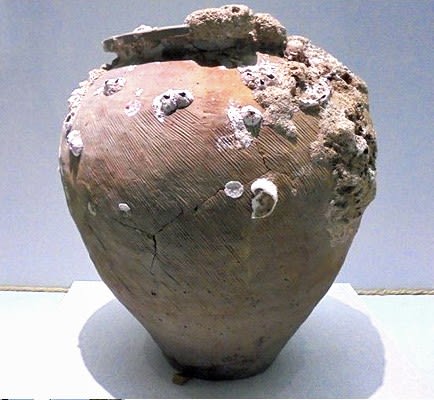 数多くある。市民の協力を得て蔵ざらえした文物をアーティストと専門家が関わり、博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館「スズ・シアター・ミュージアム」が新たに開設される。芸術祭の総合ディレクター、北川フラム氏のアイデアで、「失われゆくモノから新たな社会共通資本をつくろう」と新たなアートの可能性を創造する。
数多くある。市民の協力を得て蔵ざらえした文物をアーティストと専門家が関わり、博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館「スズ・シアター・ミュージアム」が新たに開設される。芸術祭の総合ディレクター、北川フラム氏のアイデアで、「失われゆくモノから新たな社会共通資本をつくろう」と新たなアートの可能性を創造する。 米粒を通すほどの荒い目の金網と通さない細か目の金網の2種を近くの「カーマホームセンター」で購入。ポリバケツの上に金網を乗せて、その上から虫のついた玄米を注ぎ込む。虫は数種類いる。ガはパッと飛び散り、クワガタのような黒い虫は逃げ回っている。インターネットなどで調べると、ガのようなものは「ノシメマダラメイガ」、クワガタのようなものは「コクゾウムシ」、別名「米食い虫」と言うようだ。変色した米粒が白い糸のようなものでつながっているのは、ノシメマダラメイガのサナギが出す分泌物という。(※写真・左がノシメマダラメイガ、右がコクゾウムシ=「Wikipedia」より)
米粒を通すほどの荒い目の金網と通さない細か目の金網の2種を近くの「カーマホームセンター」で購入。ポリバケツの上に金網を乗せて、その上から虫のついた玄米を注ぎ込む。虫は数種類いる。ガはパッと飛び散り、クワガタのような黒い虫は逃げ回っている。インターネットなどで調べると、ガのようなものは「ノシメマダラメイガ」、クワガタのようなものは「コクゾウムシ」、別名「米食い虫」と言うようだ。変色した米粒が白い糸のようなものでつながっているのは、ノシメマダラメイガのサナギが出す分泌物という。(※写真・左がノシメマダラメイガ、右がコクゾウムシ=「Wikipedia」より) と。これだけだ。「オリンピックの場」における政治的なブロパガンダなどは許されないと限定的な解釈だ。
と。これだけだ。「オリンピックの場」における政治的なブロパガンダなどは許されないと限定的な解釈だ。