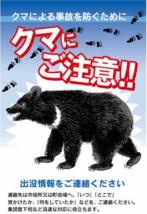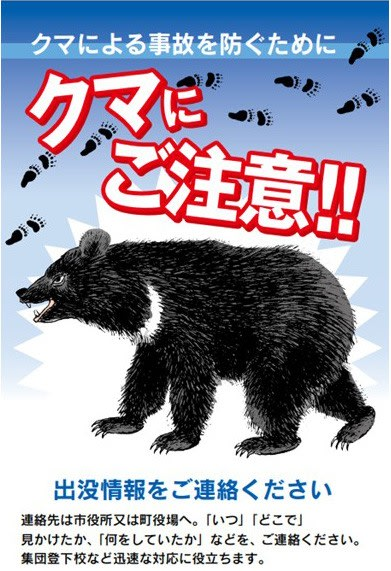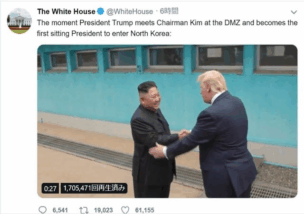☆能登被災地・町野のFMラジオ NHK連続ドラマのモデルに
能登がNHKの連続ドラマの舞台となるのは2015年放送の『まれ』以来ではないだろうか。NHKの公式サイトによると、来年2026年春放送の連続ドラマ『ラジオスター』の制作が能登の輪島市で始まり、NHKはきのう(27日)出演者のコメントを発表した。
ドラマは、主人公の柊カナデ(福地桃子)は大阪で働いていて、恋人の故郷である能登を旅行中に地震に遭い、避難所で松本功介(甲本雅裕)の世話になる。松本はコメ農家で米粉を使ったパン屋を営んでいたものの、地震と豪雨で田んぼと店を失い、妻と息子とは離れて暮らしていた。カナデはボランティアとして再び能登に入り、松本と再会する。そのころ、地元では笑えるFMラジオを開設する話で盛り上がり、番組づくりの経験がない主婦の小野さくら(常盤貴子)ら町の人たちが集まっていた。予算もない、スタジオもない、電波もない状況だが、気持ちは盛り上がる。そんな中で、恩人の松本からの頼みでカナデがラジオのパーソナリティーを担当することになる、というストーリーだ。

出演者のコメントによると、福地は「演じるカナデも生まれも育ちも別の場所で、いろいろなご縁があって能登にやって来ます。この町の人ではない彼女だからこそ、ドラマを見る人の心に届けられるものがあると信じています」とアピールした。甲本は「僕らはうつむいている場合ではなく、このドラマを明るくて楽しい作品にしないといけないなと思っています」と語った。『まれ』にも出演した常盤は「1ヵ月ぶりに能登を訪れて、いまの能登は(被災した建物の)解体が終わって時間がたち、『さて、ここからどうしよう』という局面に立たされているんだなと感じました。今だからこそ、みんなで盛り上げていきたい」と能登にエールを送った。
連続ドラマ『ラジオスター』にはモデルがある。輪島市町野町には地元の有志らがことし2月23日に臨時に開設したFMラジオがあり、当日、その様子を見学に行った。被災地のこうしたFM放送は「災害FM」と呼ばれ、災害の軽減に役立つ情報を伝える目的で開局が可能だ。この日は公開スタジオが設けられ、元NHKアナウンサーの女性とフリーパーソナリティの男性が司会を務め、地元の住民がゲスト出演していた=写真=。主催する団体「町野復興プロジェクト実行委員会」ではその後、クラウドファンディングなどで開業資金を集め、7月7日に「まちのラジオ」のネーミングで開局にこぎつけた。農家や医師、消防士など10人のボランティアが、パーソナリティも含めた運営を担っている。
被災者にとっては「情報こそライフライン」である。NHKの連続ドラマがさらに後押しとなって、地域の人たちの輪をつなぐ和やかなラジオ局となることに期待している。
⇒28日(金)夜・金沢の天気 あめ