海のGIAHSにも目を向けてみたい
世界農業遺産国際会議の前日(5月28日)、金沢市文化ホールでは、国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)が主催する国際会議のサイブイベントとしてワークショップ「アジアのGIAHSサイトにおける経験と教訓」が開かれた。この中で、国連大学の武内和彦上級副学長は「GIAHSの認定地域19のうち、アジアには11のサイトがある。欧州がユネスコの世界遺産をリードしたように、農業遺産はアジアがリードできる」と述べた。日本、中国、韓国のアジア3ヵ国が連携して、GIAHSを盛り立てていこうというグローバルな視野で語った。こうした国連大学側の思い、GIAHSの仲間入りを果たしたいという韓国側の思いが合致して、済州島でのワークショップが実現した。きょうど1年前の8月には、中国・紹興市で「世界農業遺産の保全と管理に関する国際ワークショップ」(主催:中国政府農業部、国連食糧農業機関、中国科学院)が開催されている。
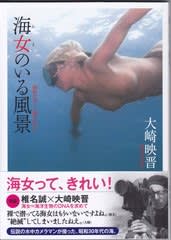 今回の旅程で個人的に楽しみにしているは、25日に訪れる「海女博物館」だ。自分自身も新聞記者時代に輪島市舳倉島(へぐらじま)の海女さんたちをルポールタージュ形式で取材した。1983年ごろ、今から30年も前の話になる。いまでも、輪島市では200人余りがいる。ウエットスーツを着用して、素潜りである。そのころ、18㍍の水深を潜ってアワビ漁をしていた海女さんたちがいた。このように深く潜る海女さんたちは「ジョウアマ」あるいは「オオアマ」と呼ばれていた。重りを身に付けているので、これだけ深く潜ると自力で浮上できない。そこで、夫が船上で、命綱からクイクイと引きの合図があるのを待って、妻でもある海女を引き上げるのだ。こうして夫婦2人でアワビ漁をすることを「夫婦船(めおとぶね)」と今でも呼ばれている。輪島の海女、済州島の海女の潜り方、使っている道具、漁の仕方などを済州島の海女博物館で見学したいと思っている。共通性と違いはどこにあるのか、比較もしてみたい。
今回の旅程で個人的に楽しみにしているは、25日に訪れる「海女博物館」だ。自分自身も新聞記者時代に輪島市舳倉島(へぐらじま)の海女さんたちをルポールタージュ形式で取材した。1983年ごろ、今から30年も前の話になる。いまでも、輪島市では200人余りがいる。ウエットスーツを着用して、素潜りである。そのころ、18㍍の水深を潜ってアワビ漁をしていた海女さんたちがいた。このように深く潜る海女さんたちは「ジョウアマ」あるいは「オオアマ」と呼ばれていた。重りを身に付けているので、これだけ深く潜ると自力で浮上できない。そこで、夫が船上で、命綱からクイクイと引きの合図があるのを待って、妻でもある海女を引き上げるのだ。こうして夫婦2人でアワビ漁をすることを「夫婦船(めおとぶね)」と今でも呼ばれている。輪島の海女、済州島の海女の潜り方、使っている道具、漁の仕方などを済州島の海女博物館で見学したいと思っている。共通性と違いはどこにあるのか、比較もしてみたい。
海女の文化を伝えようと、ことし10月に輪島市で、全国各地の海女さんたちが集う「海女サミット」が開催される。これには済州島の海女たちも参加する。海女の伝統漁法と文化を国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産登録を目指しているのだ。私が知る海女さんたちは実に気高く、人に媚びようとしない。素潜りにより自然と向き合い、共生しながら漁をする海女さんたちの生き様、その知恵がもっと見直され、国際評価がされていいと考えている。
万葉の歌人、大伴家持が越中国司として748年、能登を巡検している。輪島で詠んだ歌、「沖つ島 い行き渡りて潜くちふ あわび珠もが包み遣やらむ」。そのころから能登ではアワビが採取されていた。稲作とともに漁労も能登の特徴だ。能登のGIAHS認定のタイトルは「NOTO’s Satoyama and Satoumi(能登の里山里海)」である。1260年余りも続き、アワビという資源を枯渇させない能登の漁労とは何か、そんなことも今後探ってみたい。
※写真は、大崎映晋著『海女のいる風景』(自由国民社)
⇒10日(水)朝・金沢の天気 はれ
