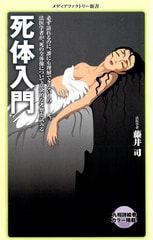 金沢大学の共通教育授業でマスメディア論を教えている。その中で、学生たちに問いかけるテーマの一つが、「マスメディアはなぜ遺体、あるいは死体の写真や映像を掲載・放送しないのか」という論点である。東日本大震災での遺体写真の掲載については、新聞各社は原則、死体の写真を掲載していない。被災地の死者(死体)の尊厳を貶めることにもなりかねないとの各社の判断があり、あえて掲載していない。リアルな現場というのは、遺体(死体)の写真をストレートに見せることはしなくても、なんらかの見せ方によって、犠牲者の多さや無念の死というものを表現することは可能との意見が多い。そのような話を周囲の研究者にすると、「では、これを読んでみてください」と薦められたのがこの本だった。マスメディアで掲載・放送するしないの論議以前の話として、日常生活で遺体(死体)と接することがめったになく、遺体(死体)そのものについて我々は無知である。これでは何も語れない、イメージと感情だけで論じることに等しいと思い、向学のために本を注文した。
金沢大学の共通教育授業でマスメディア論を教えている。その中で、学生たちに問いかけるテーマの一つが、「マスメディアはなぜ遺体、あるいは死体の写真や映像を掲載・放送しないのか」という論点である。東日本大震災での遺体写真の掲載については、新聞各社は原則、死体の写真を掲載していない。被災地の死者(死体)の尊厳を貶めることにもなりかねないとの各社の判断があり、あえて掲載していない。リアルな現場というのは、遺体(死体)の写真をストレートに見せることはしなくても、なんらかの見せ方によって、犠牲者の多さや無念の死というものを表現することは可能との意見が多い。そのような話を周囲の研究者にすると、「では、これを読んでみてください」と薦められたのがこの本だった。マスメディアで掲載・放送するしないの論議以前の話として、日常生活で遺体(死体)と接することがめったになく、遺体(死体)そのものについて我々は無知である。これでは何も語れない、イメージと感情だけで論じることに等しいと思い、向学のために本を注文した。
衝撃的な記述が次々と目に飛び込んでくる。アメリカのテネシー大学には「ボディ・ファーム(死体牧場)」がある。1㌶ほどの土地に、20体ほどの死体が地面に放置され、半ば埋められ、ゴミ袋に詰められたものもある。そして死体がどのような条件下でそのように腐敗していくかの実験が進めらている。これまで主観的や経験と勘で判断されていた死亡推定時刻を、科学的なデータの蓄積で解析していこうという研究なのだ。1981年に施設が設立された。同じ大学関係者や学生たちからの苦情やストライキなど難問が立ちふさがったが、それを乗り越え、いまやテネシー大学は死体の腐敗研究では最高権威となった、という。さらに驚くことに、この腐敗実験に用いられる死体は、生前に自身が登録して献体するボランティアなのだ。
日本の大学での解剖学の献体のシステムについても語られている。献体登録した方が亡くなると、病院から解剖学教室に連絡が入る。教室員が遺体を引き取りにやってきて、遺族を意思も確認される。大学では遺体を清潔にし、髪も切る。血管に保存液を注入し防腐処置をする。その後、アルコール溶液に漬ける作業が行われ、遺体は一体一体丁寧に包まれ保管される。献体は「ホルマリンのプール漬けになっている」や「死体洗いのアルバイトがある」などは私自身も学生時代に噂として聞いたが、真実と嘘が混じっているようだ。ただ、この献体は解剖学教室員の以外の人は関与しないので、医学部の中でも知られていないは事実のようだ。
日本人は死をどのように見つめてきたのか。写実的な観察した記録もある。九州国立博物館に所蔵されている『九相詩絵巻』(14世紀)はその最古の絵巻といわれる。女性の「生前相」「新死相」「肪脹相」「血塗相」など腐敗の過程が骨がバラバラになるまで9つのプロセスで描かれている。絵に描かれるほど、死体は古くから一般的でなく、謎だった。
意外だったのはこんな数字。人間に限らずすべての動物には体の中に細菌が棲みつく。成人した人間の体内では約500種、100兆個の細菌が体内に同居して酵素を分泌している。その細菌の重量を合計すると、1㌔㌘にもなると考えられるという。人が死ぬと、これら体内の細菌は酵素を分泌してたんぱく質を分解し始める。これが腐敗、「自己融解」である。くだんの『九相詩絵巻』はその体の腐敗の過程を色の変化で見事にとらえている。
終わりに、著者はこう訴えている。「不必要に死体をおそれ、死体への興味を育まない社会も問題ではないだろうか。死体に関心を持つことさえ許さない風潮がある」「誰もが最終的にたどり着く姿であり、ありふれた存在であるはずの死体が徹底的に隠される現状のほうが異常ではないですか?」と。そして、無縁社会と称される現在、たった一人で亡くなり、ミイラ化した死体が日本では約5日に1件発見されているという事実。孤独をまぎらわすために犬やネコを飼う独居老人も多い。飼い主が死亡した場合、その犬やネコはどのような行動をとるのだろうか…。
この本を読んで、死を見つめるバリエーションはかくも多いと気づく。そして、死体について我々は知らぬことばかりだ。
⇒16日(金)夜・金沢の天気 ゆき
