前回、アメリカのレイチェル・カーソンの名著「サイレント・スプリング(沈黙の春)」(1962年)を取り上げた。「春になっても鳥は鳴かず、生きものが静かにいなくなってしまった」の一文は、環境以外にもいろいろな解釈ができる。たとえば、テレビメディアだ。画面は華やかだけれども、現場のプライドは薄れ、制作者はいなくなった・・・と。07年1月に捏造問題が発覚した番組「発掘!あるある大辞典」の調査報告書を読み返してみて、ふとそんなことを考えた。
制作の矛盾が番組に曝露するとき
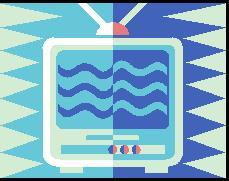 組織には何がしかの光と影がある。テレビ局の場合、どれだけ視聴率を取って、スポットライトを浴びた番組であっても、影の部分を残したまま増幅させてしまうと、その矛盾がいつかは番組に曝露してしまうものだ。520回余り続き、平均視聴率15%も取った「発掘!あるある大辞典」が問題発覚からわずか6日で番組打ち切りが宣言された。その影とは下請け問題だった。調査報告書によると、関西テレビから元請け会社(テレワーク)に渡った制作費は1本当たり3162万円だったが、孫請け会社(アジトなど9社)へは887万円だった。テレワークの粗利益率は18.6%あったという。しかし、孫請け会社は過酷な条件下に置かれた。
組織には何がしかの光と影がある。テレビ局の場合、どれだけ視聴率を取って、スポットライトを浴びた番組であっても、影の部分を残したまま増幅させてしまうと、その矛盾がいつかは番組に曝露してしまうものだ。520回余り続き、平均視聴率15%も取った「発掘!あるある大辞典」が問題発覚からわずか6日で番組打ち切りが宣言された。その影とは下請け問題だった。調査報告書によると、関西テレビから元請け会社(テレワーク)に渡った制作費は1本当たり3162万円だったが、孫請け会社(アジトなど9社)へは887万円だった。テレワークの粗利益率は18.6%あったという。しかし、孫請け会社は過酷な条件下に置かれた。
その第一は、納品された放送制作物の委託料の支払いが、納期日からではなく、放送日の月末締めで翌々月の10日だった。捏造が問題となった納豆ダイエットをテーマにした番組は07年1月7日放送だったので、委託料の支払いは3月10日となり、納期日からなんと75日後ということになる。改正下請代金遅延等防止法では、元請けに対し、納品から60日以内、しかもできるだけ速やかな支払い求めているので、これだけでも違法であり、不当である。財務余力がある大企業ならいざ知らず、番組制作会社には零細企業が多く、資金繰りは相当苦しかったに違いない。
さらに、孫請け会社が元請け会社に「専従義務」を負い、にもかかわらず、死亡や負傷、疾病には、元請けは一切責任を負わないこことになっていた。ことほどさように、元請けは孫請けに対して優越的地位を濫用したのである。 調査報告書は「下請け条件を課されながら仕事をしなければならないという環境が、末端の制作現場で番組制作に携わる制作者からプライドを失わせ…」「期日どおりにやり抜かなければならないという点にのみ神経が集中してしまう傾向を醸し出した」と断じている。そして、制作責任があるキー局側に番組の内容をしっかりと見回す人がいない状態が生じたとき、捏造が起きた。つまり、矛盾が曝露したのである。別の表現をすれば、番組制作上の膿(うみ)が一気に噴出し、最終的に番組そのものが消えてしまった。
最近、TBS番組「サンデー・ジャポン」の捏造シーン問題など、放送倫理・番組向上機構(BPO)による勧告が相次いでいる。「発掘!あるある大辞典」と同根の問題がテレビ業界全体に横たわっているのではないかと睨んでいる。
⇒10日(月)夜・金沢の天気 くもり
